最終講義 おわり(複数形)にあたって
吉岡知哉(立教大学名誉教授)
*本最終講義は2018年3月3日(土)におこなわれたものです。
**本稿は立教法学会『法学周辺』NO.48(2018年10月)に掲載されました。転載を快くお認めくださった立教法学会のみなさま、そして吉岡知哉さまのご厚意に感謝申し上げます。
***なお本稿には、新たな画像の挿入のほか、加筆修正が行われています 。

はじめに
吉岡です。お集まりくださってありがとうございます。最終講義ということですが、普段の講義でもこんなに人が集まったことはない(笑)。だいたい登録が百何十人かなんかで、出てくるのはだいたい30~40人ぐらいというのが私の講義の基本で、しかもだいたい後ろのほうにいるというのが普通でした。
最終講義は、若い頃からあまりやるつもりはなかったのです。法学部の先生たちの中にも結構そういう方はおられるんですが、通常どおりの授業をして、最後のところで、「じゃ、これで終わります」と言う。これがなかなか格好いいと思っていたので、やらないつもりだったんですが、「やっぱりやらなくちゃいけない」という声もあって、やることにしました。
[司会の]竹中千春さんからは若い人にメッセージをということですが、若い人はあまりいないなというのがこの場に来ての最初の印象で、そうだろうなと(笑)。考えてみると、8年間講義からもゼミからも離れておりまして、若い人というのはいないし、感覚はずいぶん狂っているなという気がします。でも、久しぶりに教壇に立ったわけでそれはちょっとうれしいなという気もします。
「おわり(複数形)」というのは別に大した意味はありません。何かタイトルを付けろと言われたので、そろそろ終わりだなと。立教大学の定年と総長の任期がピッタリ合ってしまって、両方とも終わりだということで、まず考えたのはそれです。終わりだなというので。でも、まあ、複数形にしておこうというので、複数形と付けたということです。
1980年に立教に勤め始めて、最初は助手として基礎文献講読を担当しました。きょうは舟田正之先生がお見えになっていますけど、最初の基礎文は、私は助手で舟田先生と組みました。あとは栗原彬先生でしたが、それを1年間やりました。この3月で38年間で、いま立教大学の教員の中ではたぶん最年長で、いつの間にかこんなになってしまいました。
ただ、考えてみると、助手のときは講義をしていなくて、研究休暇は法学部流の最初の2年と、あとは1年間を2回取っていて、本当はもっと取れたはずだなと思わないのではないんですけど、合計4年取っています。それから学部長を2期4年やって、総長を2期8年やっているので、合計すると17年間も講義はしていないんですね(笑)。だから、38年間だけど、講義していたのはそのうちの21年で、なんか大して働いていなかったんだという気がしています。
それから、終わりと言いましても、実はまだ総長は任期中で、本当に申し訳ないんですけれど、最終講義の準備を本当にする暇がなくて、今日は基本的に雑談するぞ(笑)というつもりで来ています。どうぞお許しください。
教員になって最初の頃に、友人に「お前、教師になってどうするつもりだ」と言われたときに、「いや、教壇で人生は語らない」ということを言ったことがありまして、あとは「教壇で義を講じない」というのもあるんですけども、今日はちょっと少しこれを破ることになるかもしれません。やはりなんとなく振り返らざるを得ないという気がしています。
この最終講義のポスターに出ているんですが、下の囲みのところで「欧州政治思想史を極めてこられた」とありますが、全然極めていないというのが一つです。ちなみに「極める」の字は、探究の「究」であるべきだろうと。これは極道のほうですので(笑)。
さて、お手元に1枚紙をお配りしました。パワーポイントをつくったりもしないし、資料を付け加えたりもしていません。資料ぐらい付け加えたいと思わないでもなかったんですが、全然そんな時間がなかったということでお許しいただきたいと思います。一応、今日の章立てになっています。
ここで5つ項目を挙げているんですけども、この5つは、これまでだいたい50年ぐらいの間になんとなく関心を持っていた柱みたいなものでもあるんですね。そのことと今日の話とが重なっているということです。
新しい研究からもちろん離れていますし、やはり学生に講義をしていないと、自分の考えもリフレッシュされないんですね。しかも自分がやったことも含めて、いろいろな細かいことを忘れてしまっているんですけれども、そういう意味では昔、思想史に関わり始めたときにどういうことが気になっていたのかということから、ちょっとお話ししたいと思います。

1.政治思想とテクスト
思想史に対する向かい方というか、あるいは思想家の扱い方というのが、最初の問題です。思想について語る、あるいは思想について研究するというのにはいくつかパターンがあります。一つは、その思想家に言寄せて自分の思想を語るとか、自分の考えを述べる。これは、ごく普通によくあることです。そういう意味では、そもそも解釈する気はなくて、その場合、通常みんなが知っていることを使って自分の主張を説明する。例えばプラトンは私の説に賛同してこう言っているみたいな、そういうことですね。
そうではなくて、ある種の客観的な解釈であった場合でも、解釈者の見方が入るということは当然なわけです。それがなければ、解釈の意味はないというのもそのとおりでしょうが、少なくともそのことについて無自覚であってはならないだろうとは思います。このように、思想家に言寄せて自分のことを話すというのが一つです。
もう一つは、自分がその思想家になってしまうのに近いのがあります。守護霊と対話するのに近いわけですが、要するに、例えば現代の諸問題について語るときに、ルソーならばこう言うとか、マルクスならこう言うというような形で、自分がその人に実はなってしまっている。そういうパターンがあります。
別にそれはそれでいいのですが、もうちょっとアカデミックな、いわゆる研究の場合も、研究をして、この思想家の思想はこのようなものであるということを示す、そのプロセスで、つまりこの人の本当の思想はこれだ、という言明に結び付くということはよくあることです。この思想家が本当に言いたかったことはこれなんだと。
特に矛盾があると言われるような思想家とか、叙述が分かりにくいとか、それからさまざまな解釈が成立している、著作によって言っていることが違う、あるいはそのように思える、それを統一的に解釈するというのは研究上非常に重要なことなんですけれども、でも「思想家はいろいろとこういうことを言っているんだけれども、この思想家が本当に言いたいことはこういうことだ」という説明の仕方は、ごく普通にあるだろうと思います。
これに対して非常に素朴な疑問が最初からありまして、それはそうかもしれないけど、そうなのだろうか。それならばなぜそう書かないのか。その人がそのように言っているのだったら、なぜその人はそのように書かないで、そういう凝った書き方をするのか。難しい書き方をするのか。そこに矛盾を持ち込むのか。そのことは最初から気になっていました。
ある場合には、要するに頭がいい人がいて、研究対象の思想家よりも頭がいい。解釈者のほうが頭がいいわけですね。つまり思想家はこのことをちゃんと言えないので、私が代わりに言ってやるということです。思想家の代わりに思想家が本当に言いたいことを言うというのが研究者かという問題と、それに付随して、いったいその権利はどこから来るのか、それが言える権利とはどういうものなのかと。
いま言ったようなことが必ずしも明確であったわけではないですが、ずっと考えていたことです。
こういう問題が、集中的に表れるのがルソーだと思います。もちろん私が多くの政治思想家の著作をちゃんと読んで、その中からこれに合っている、このことを論じるのに大切なのがルソーだと思ったわけではないですし、ルソーは学生のときにも読みましたけども、特に好きな思想家だというわけでもありません。ただ、ある種の出会いがあったと言えば、そのとおりだろうと思います。
ルソーの著作の矛盾というのは昔からよく言われていて、私が研究を始めた40年ぐらい前はそういうことが非常によく言われていました。例えば自然と文明の問題で、最初の著作である『学問芸術論』では文明の進歩を徹底的に批判していくけれども、『社会契約論』などを見ると、そういう形で文明の進歩を否定しているわけではない。『エミール』も、読み方によりますけども、文明に馴染ませていくという側面があるわけですね。
それから『社会契約論』では「市民」ということがしきりに言われているのに、『エミール』では「自然人」ということが言われ、ルソーの著作の中で大事なのは市民の問題なのか、自然人の問題なのかみたいな議論がある。
あるいはその「自然」ということについても、著作によって結構いろいろな違いがある。ルソーが「自然に帰れ」とは言わなかったというのは、ある時期から、ようやく普通に言われるようになったのですが、ではその自然観、自然に対してルソーはどういう態度を取っていたのか、あるいはもう少し別の言い方をすると、ルソーが何に価値を置いていたのか、というようなことですね。
例えば『不平等起源論』の自然状態論と、『学問芸術論』でしきりに引っ張り出される古典古代の価値みたいなものが、どういう関係になっているのかといった議論があったわけです。言っている内容に一貫性がないとか、ルソーにおける理性と感情の問題であるとか、ルソー自身がそういうところがゴチャゴチャになっている人間だみたいな話にまでなっていくわけですし、ルソー自身がこういうルソー像に加担していくというところがあります。
今日は立教の仏文の教授でルソーの自伝の研究者である桑瀬章二郎さんが見えているので、あまりそこら辺の話もしたくないですが、自伝三部作と言われる、いわゆる『告白』というものと、それから『ルソー、ジャン=ジャックを審判する』あるいは「裁く」という対話篇と、それから『孤独な散歩者の夢想』という三つの自伝があるんですけれども、その中で「ルソーが描き出しているルソー」というものが、非常に問題を錯綜させているところがあります。
政治思想でいうと、ルソーの政治思想の評価、その「評価」という言い方自体もある意味ではおもしろい言い方だと思いますが、ルソーが民主主義者なのか、全体主義者なのか、あるいは個人主義者なのか、集団主義者なのかという議論も、戦後の例えばナチズムの評価の問題等も含めて、40年くらい前はかなり中心的な議論だったと思います。
その後、こういう現代の概念枠組みを著作の解釈に持ち込むことに対する批判というのがあって、その後はあまりそういう言い方はされなくなったように思います。当時ナイーブな議論が多かったということも確かなのですが、ただ一方で、どんな解釈者であっても、現在の解釈枠組みから、さらに言うと、現在の言語体系から自由であるわけではないので、それは駄目だと言っても、それでは全然問題は解決しないということがあります。それから逆に、例えば現代の、と言っていいかどうか分かりませんけれども、一定の概念枠組みを持ち込むことで分かってくることも確かにあるわけです。最大の効果は、その概念枠組みが無効だと分かるということですが、それは重要なことで、一概に批判すべきことではないとは思いました。

2.作品と読者
(1)解釈の権利
2番目の「作品と読者」というタイトルのところに入ろうと思います。先ほど言った素朴な疑問ですね。つまりルソーで言えば、ルソーが言っているのはこういうことだと解釈を提示する。でも、何でルソーはそう書かなかったのかという、非常に素朴な疑問があったわけです。
研究者がルソーに成り代わって、ルソーの思想を述べることの権利はどこから来るのかと、先ほどちょっと言いましたが、権利はあるんだと思うんです。つまり解釈の権利というのが一方にあって、これはさらに言うと、ある種の誤読の権利みたいなものがあって、誤読とか曲解というのは権利と言っていいかどうか分かりませんが、ごく普通に起こる。そもそも政治思想史というのは、テキストの誤読の歴史で、誤読されることによって歴史がつくられてきているわけですから、だから駄目だと言っても、実は始まらないわけです。
それからもう一つ、思想にもいろいろな関わり方があると思いますけど、例えばルソーとフランス革命とか、レーニンとロシア革命とか、あるいはマルクスとロシア革命でもいいんですが、歴史的な変動と思想が結び付いてくる場合、当然そこには誤解であるとか曲解であるとかいう問題が常にある。
それに対して、正しい解釈というのを対置するのかという問題があるだろうと思います。では、そこで言う解釈というのは何なのか。その著者が意図していたところを的確に示すということが正しい解釈なのかという問題ですね。この辺のところは実はよく分からないのです。
思い出すのは、助手論文の審査のときに、京極純一先生から「あなたが言いたいことは分かった」と、「じゃ、あなたからすれば、これまでのルソー解釈は全部間違いだったということですね」というように言われたんですね。そのときは「はい」と答えたんですけど(笑)。全然答えになっていないんですが、要するにどんな場合でも新しい解釈を出すと、前の解釈とは違うことになる。その解釈はおかしいのではないかというのは必ずあるので、正しい解釈をあなたは提示しているのかと言われると、大変困るわけです。
その問題に関わって、やはり思想と歴史とか現実とのダイナミクスということがあって、一つは有賀弘先生の『宗教改革とドイツ政治思想』という本、それから斎藤眞先生のアメリカ革命史に関する著作というのは、思想というものと現実というものの関わり方の問題、つまり解釈が正しいかどうかという話でもなくて、その思想がどのように歴史の中で機能してしまうのかという視点を持っていて、非常にすごいと思っています。
いま言った「ルソーが言っているのはこういうことだ」と、読者は著者に成り代わって著者の思想を語ることが許されるかという問題自体が、ルソーにとっての大問題だったわけです。ルソーの自伝はそのために書かれた、それをめぐって書かれたものだろうと思います。あとでちょっと触れる時間はあると思います。

(2)媒介と障害
ルソーはご存じかと思いますが、1712年にジュネーヴで生まれました。当時のジュネーヴは独立都市国家で、フランスでもないし、もちろんスイスでもないのですが、一つの都市国家で、ルソーはそこの市民権を持っている家に生まれた、ある程度上位の職人層の人です。当然フランス語圏です。当時18世紀では、フランス語はある種の国際語としての地位を少なくともヨーロッパでは占めていて、非常に美しくて的確で正確な理性的な言語であると言われていました。
ところが、ルソーはそう考えないのです。『言語起源論』という1755年の『不平等起源論』の注として書き始められたと言われている文章がありますが、その中でフランス語というのは非常に不完全というのか、あるいはやり過ぎの言語というのか、非常に人工的であって、そのために非常に不自由なものだという考えが出てきます。やや大雑把な言い方ですけれども。
言い換えると、ルソーにとってみると、自分が用いている言語、自分が考え、それを表明する言語というのが、非常に不自由なものである。これは言語一般の問題なのかどうか分からないのですが、要するに自分が使っている言語、フランス語は、表現を媒介するものとして非常に不完全なもので、常に障害として意識される。媒介するもの、特にルソーはフランス語の書き言葉に言及するのですが、その記号性というものに対して非常に強い不信感を持っているわけです。
別の言い方をすると、媒介するものということに対してルソーは非常に関心を持ち続けることになります。そんなに難しい本ではなくて、大変おもしろい本ですが、スタロバンスキーという人の『透明と障害』という本があって、ちょうど私が20代だったときに翻訳が出たりして、結構評判になった本です。そのスタロバンスキーがルソーの透明性というものに対し、意識的に透明を求めているというのと、それが障害に出会うという、ある種弁証法的というか、その運動性を書いた本で、おもしろい本です。やはり障害となるものに対する関心が、ルソーは非常に強いのだろうと思います。
そのことは言い換えると、ルソーが、自分はどのように思想というものを表現していくのかということですね。つまり不自由なものを使って自分は自分を表現しなくちゃいけないというわけですから、そこにはやはりある種の戦略というか、方法の問題が生じてくるだろうと思うわけです。というか、その頃、私はそう思ったわけです。
別の言い方をすると、思想というのは、表現されて初めて思想になる。つまり思想というのがまずあって、それが表されるのではなくて、表されるというプロセスないし、その表されたものによって初めて思想ということが、思想と言わなくても文学作品でもいいのですが、そういうものが表れるということです。したがって、ある作品というのがどのように書かれているのか、あるいは別の言い方をすると、それが言語を媒介にするわけで、どのように読まれようとしているのかということをやはり考えなければいけないだろう。そういう観点から作品を読み直してみようというのが、最初のというか、その後ずっと頭の中に引っ掛かっていることです。先ほど[冒頭の紹介で]川崎修さんは映画の話もしてくれましたけど、映画についてもそういうところがあります。同様に、作品がどのように観る者に対して働きかけるかということです。映画のことも映画の専門家が今日来ているので、あまり話したくないのですが、映画に対する関心もその辺で結び付いているだろうと思います。
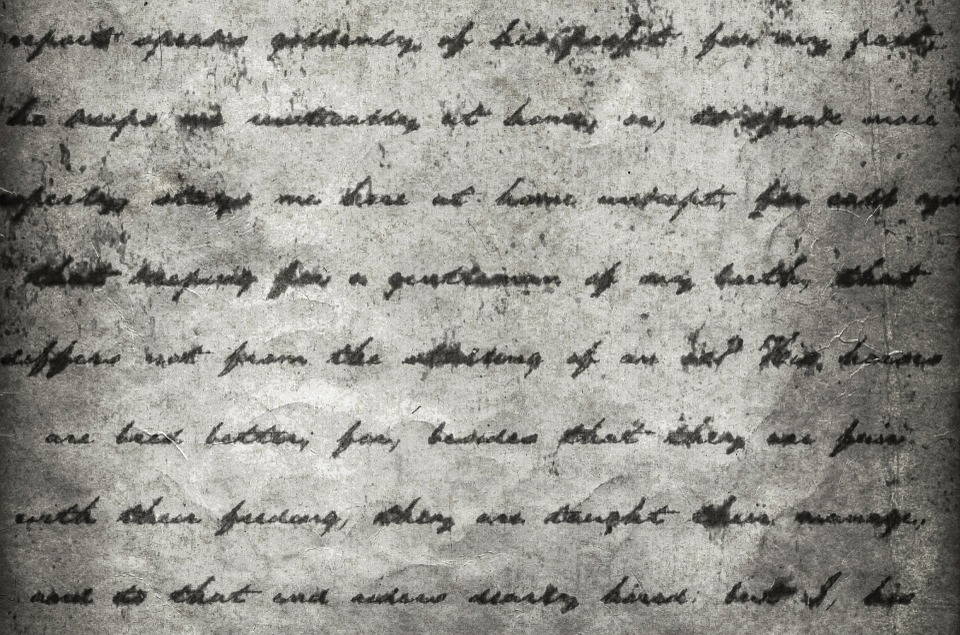
(3)論理と論述
ルソーの作品というのは、そのように思ってみると、非常に凝った仕掛けのある書物ばかりです。講義だと、講義をしたあとに「あのときに話した話」というように戻れるんですけど、8年間、間が空いていて、ここに集まっている方々は学生ではないので、すごく話しにくいのですが、例えばルソーの『不平等起源論』というのは、最初の第1部に自然状態論という自然状態の話が出てくるんですね。そして、第2部に、その自然状態から現在あるいは現在のちょっと先までという感じなんですけど、人類の歴史が書かれるという書物になっています。したがって、そのルソーの自然状態論はホッブズの自然状態とどう違うかとか、ロックの自然状態とどう違うかというのは、いろいろな論争があるわけです。
その自然状態の話と2部の歴史の話というのが総体でテキストができ上がっているのだから、両方まとめてちゃんと読んでみるとどういうことかというと、これは私の読みですけども、要するにいまの私たちが生きているこの状態の人間から、あるいはこの状態から、社会性と考えられるものをどんどん引いていくわけです。人と人との付き合い、例えば商品経済でもいいですし、それから家族関係であるとか、最後は言語まで引いていってしまう。
そうすると、そういう社会的なものが全部なくなった状態が一応想定できるだろう。それを自然状態というようにまず設定して、そこから順番に少しずつ外したものを足していくと、ある種の歴史という形を取った現在に至るまでの物語ができてくる。それが『不平等論』の仕組みになっていて、そうすると読んでいくと、いまいる私たちが結んでいる社会関係というのが一つ一つ検証されていくというのが、『不平等論』の書き方ではないかと思ったわけです。
そのような形で、つまり書物を読んでいくプロセスが、思想に結び付いていく。そういう意味での表現の問題というか、書き方の問題というのと、そのプロセス自体が思想の問題になっているというのが、結構重要ではないかと思ったわけです。ルソーの自然状態論はこうだということを取り出しても、それはそれでいいのですが、ルソーを読むことにはあまりならないかなと思ったのです。
ホッブズの『リヴァイアサン』とロックの『統治二論』と、それからルソーの『社会契約論』の三つは近代社会契約説の三大古典で、実際読んでみると、全く書き方が違う書物です。論理の組立も違いますし、それから論理というものに対する姿勢というのが違っている。
ホッブズは生物としての人間、生物の生存の条件というところから話を始めていくわけですね。ロックはそんなに厳密ではなくて、そもそも政治的なパンフレットとしての性格が強いということがありますけど、どちらかというと説得のレトリックになっていて、基本的には読んでいると、「だって、そうでしょう」という書き方だと僕は思うのですが、読者の既存の観念をうまく利用していく書き方だろうと思います。
それに対してルソーの『社会契約論』は、最初のところで「私はあるがままの姿で人間を捉え、法をあり得る姿に捉えた場合に、社会の秩序の中に正当で確実な統治の何らかの原則があり得るかどうか探究してみたい」と始まります。
いまの人間というものをあるがまま、いまの人間の姿を前提にして、しかしそこに論理的に組み立て得る社会の仕組み、国家論と言ってもいいのですが、国家の仕組みを与えたときに、どういうことが起こって行くのかということを書いているのが『社会契約論』の仕組みで、本人がそのように書いているわけですね。
あるがままの人間というのは、基本的には自分の自意識と欲望に捉えられた人間。一方、あり得る姿の法というのは、まさに社会契約説なのですが、共同的な存在としての国家、国家共同体というものを形成する論理です。基本的にはホッブズを引き継いでいると思いますが、その論理をあるがままの人間に与える。そういう書き方になっているわけです。
ホッブズとかロックはちょっと別の話になってしまうのですが、ルソーの場合は、あるがままの人間というのが、いくつか条件があるんですけど、社会契約を結ぶわけですね。で、共同体をつくる。でも、そこに何が起こってくるかというと、要するに人間は、社会契約をして国家をつくるというのは、共同体を形成するということだという、本当の意味というのは実はあまりよく分かっていないんです。それによって自分の利益が守られるから、あるいは自分の利益が最大化できるからという方向で、実は人間は動く。そうすると、せっかく結んだ社会契約の国家というのは徐々に崩れていくことになります。
『社会契約論』というのは、そういうせっかくつくった国家共同体が崩れていくプロセス、あるがままの人間を前提としたおかげで崩れていくプロセスが書かれている。つまりある論理が提示されて、あるべき社会が書かれているわけではなくて、そのずっと時間的な変化というのが組み込まれているというのが『社会契約論』ではないかと思ったわけです。
で、そのように読むと、『社会契約論』というのはそんなに長い本ではないのですが、最初に社会契約の話が出たあと、いろいろな話が続くのです。前に論じたはずのことがまた出てくるとか、なぜここでこの話が出てくるのかというのがよく分からない。順番がおかしい、章立てがおかしいということは昔から言われていたんですが、それはなぜかというと、現物のテキストの解釈をしないでこんな話をしていると分かりにくいと思いますが、それはその著作の中に時間的な経緯が組み込まれているからだろうと思うわけです。
したがって、『社会契約論』というのはちょっと分かりにくいところがあって、だいたい後半の部分の話はあまり扱われないんですね。つまり全員一致で社会契約を結んで国家をつくる、そこに一般意志というものが生まれて、その一般意志というものを提示できる立法者というのが必要だというところまではだいたい話は出てくるんですが、そこから先の政府が必要になってくる話とか、段々最後に検閲が必要になってくる話というのは、なぜそういう話が出てくるのかが、ちょっと分かりにくいのです。でも、そこに時間的な経緯が組み込まれているというように読むと、なんとか解釈できるのではないかと考えたわけです。
実は『エミール』がそれとよく似ていて、『エミール』というのは、ある種の完全な状況掌握力がある教師、これは「私」で書かれているから、著者と重なるような形で書いているわけですが、教師である「私」のもとでエミールという子どもが生まれたときからずっと育っていくんですね。そのエミールというのは孤児で、親子関係を持っているわけではないんです。それが身体的に成長していくのに対応して、少しずつ社会の中で育っていく。先ほどの『不平等起源論』と少し似ているんですが、その子供が大きくなっていくに従って、社会のいろいろなものに触れてくるときに、何が起こってくるか、そのエミールという子供に何が起こってくるかということが書かれている。そういう仕組みになっています。
テキストもなしにこんな話をしてもよく分からないかもしれないですが、何が言いたいかというと、まず考えたのは、テキストというのは非常に素直に読んでみるものだということに実は尽きるんです。
『社会契約論』の国家というのは、うまくいかないじゃないかという批判が当然あるんですが、それはそのとおりで、ルソーは最初にあるがままの人間というのを前提にして書き始めているわけですね。あるがままの人間と、ある種の完全な形の論理的に構成される法を同じ著作の中に組み込むと、ルソーは最初の最初に書いているんですが、あまりそのことが意識されてこなかったわけです。
できるだけそこに書かれているとおりに読もうというのが大事であろうというのが最初に思ったことで、それ以来一向に進歩していないのですが、そういうことです。

(4)注意深い読者
実際ルソーは著作の中で、注意深い読者であってくれということを、しきりに繰り返しています。注意深くない読者に対して、このことを言ってもきっと分からないということを言います。つまり、注意深い読者と注意深くない読者がいるわけですね。注意深い読者であれば、ルソーの言いたいことは回り道なんだけども、分かってくれるというわけです。
考えてみると、ホッブズは読者に注意深く読んで欲しいとは言わないんですね。言う必要がないわけです。つまりホッブズの論理というのは、非常に優れた論理だと思いますが、確かに注意深く読まないと分からなくなってしまうのです。しかしホッブズが想定している読者、論理的に論理を追える読者はいるわけで、概念の厳密な定義とその展開プロセスを追えば、分かる。論理的な証明になっているわけです。数学の証明に近い。スピノザなんかもそうだと思いますが、そこにあるのは、分かるか、分からないかではあるんだけど、読み間違えるという話は措定されていないのだろうと思うのです。
そういう意味では、ちょっと別のフェーズに話が行ってしまうのですが、要するにホッブズやロックとか、それからスピノザがいた17世紀から18世紀の頭ぐらいの時代とは異なる読者層、つまり書物を読む層が想定されてくるという、歴史的な条件の問題がそこにあるだろうと思うわけです。
18世紀のフランスというのはちょっと特殊なところで、よく分からないところがたくさんあるのですが、一つは大学という制度とは異なる知的な環境が広がっていた時代です。詳しくは桑瀬先生に聞いていただいたほうがいいですが、カフェであるとかサロンであるとか、それからフリーメイソンのような変な秘密結社みたいなものもたくさんあって、それから百科全書派、「派」と言わなくてもいいのですが、『百科全書』というのが編まれて、いろいろな人がそこに関わる、いろいろな人間が、ある意味では好き勝手に書く世界がある。
それから文芸共和国と呼ばれる、ヴォルテール辺りを考えていいと思いますが、やたら手紙を書きながらつながっている知識人のグループがあります。大学はあるのですが、そういう18世紀の時代の中心的な知的な環境からすれば、大学というのはごく一部であるかもしれません。例えば大学で学んだ人たちもいるのですが、そもそも大学の中、あるいはアカデミーの世界とは違う世界というのが、非常に多様に広がっているわけです。その知の制度と規範というものが非常に多様化して多元化している。アカデミズムの文法も壊れてしまっている時代です。それと連動して、読者層もいままでと違う層が成立してくる。
それに対してルソーは、読者が作品をどう読むかということに非常に強い過剰な意識を持って臨んだ人だと思います。
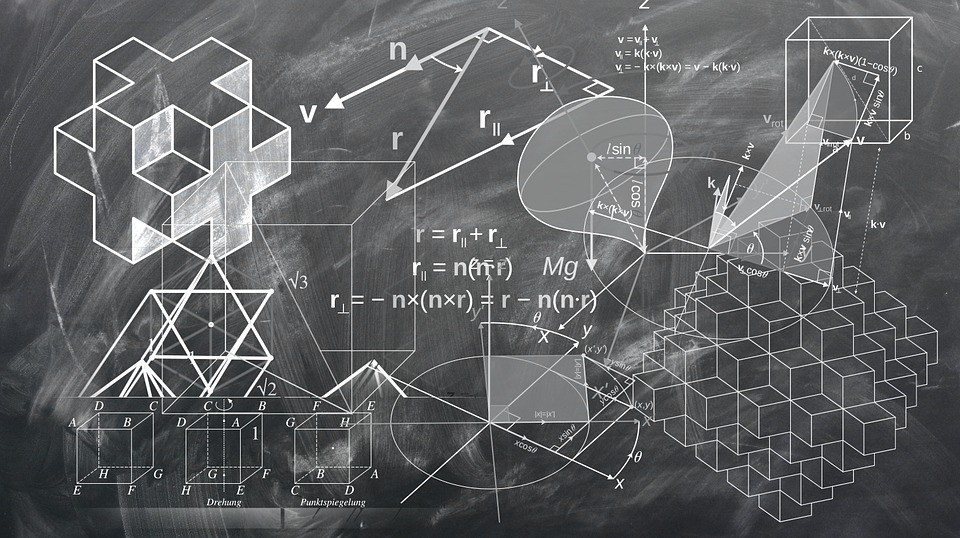
(5)思想における歴史
それで、思想における歴史の問題です。政治思想だけではないのですが、思想というのはちゃんと歴史的なコンテクストの中で読まなければいけない。思想というのは、好き勝手に引用できるものではないというのは、ここ何十年間の間でよく強調されるようになりました。昔の読み方というのは、歴史的な問題あるいは歴史性というのを無視したアナクロニズムだということが言われて、歴史的状況との関連というのが思想史研究の中で非常に強調されるようになりました。
これはヨーロッパの政治思想史の中で大きな動きになるのですが、考えてみると、日本政治思想史というのは元々そういうことがちゃんと考えに入っていたのではないかなと、ちょっと最近思っています。昔から意識されていた。ヨーロッパの政治思想史の研究のレベルの中には、そのことはあまり入っていなかったのですが、日本の政治思想史研究というのは、昔からそういう歴史性ということは強く意識されていたのではないかと思っています。
そういう中で『社会契約論』についても、当時のジュネーヴの社会状況の中で読む、あるいは政治状況の中で読むという読み方が出て来ました。おもしろい見方なのですが、要するに当時ジュネーヴというのは階級闘争がかなり激化していて、一応共和国なんですけど、上部の都市貴族化している層というのが事実上の寡頭政治を敷いていて、それに対する反発というか、階級闘争が起こっているんですね。反対派と言いますか、民主派と言っていいかもしれませんが、そのグループとルソーは実は結構連携を取っていた、連絡をしていたという話があって、ルソーというのは孤独で孤立した人間だというのとは違って、結構ジュネーヴといろいろなつながりがあったということが論証されるようになってきました。
したがって、『社会契約論』というのは、単純化してしまえば、ジュネーヴの民主派の綱領として読むべきだという議論が出て来ました。確かに民主派のほうのマニフェストという側面を持っていると言えなくはないのです。『社会契約論』にジュネーヴ草稿という草稿があります。その草稿を読むと、そういう傾向が非常に強く感じられます。つまり、こういう社会というものが目指されるべき社会である、あるいは国家制度であるということが書かれているのです。ただ、先ほど言ったように、『社会契約論』の決定版と言いますか、出版されるものになると、あるがままの人間にある種の理想的な法の体制を組み込むと何が起こるかという議論なんですね。
つまりテキストというか、作品と外部との関係が、『社会契約論』の中ではその外部が一般化されて作品の中に取り込まれているというように、やや比喩的ですけども、言えるのではないか。ジュネーヴ草稿において作品の外部であったジュネーヴの階級闘争、あるいはそこに起こっている人間の問題みたいなものが、現実の問題の一番根本にある「あるがままの人間」という形で『社会契約論』の中に取り込まれている。
そしてそのことによって、ジュネーヴとの政治的な関係というのがいったんは切れるのではないか。それによって、より一般的な読者に向かう書物になるということが起こっているのではないか、と考えています。もっとも、ジュネーヴ草稿をもう少しちゃんと読まなければいけないなと思っているのですが、ある時期そのように思ったということです。
作品を歴史的コンテクストの中で読むというのはすごく重要なのですが、一種の歴史還元主義にもなりがちで、歴史を要するに外在化していくということになるんですが、そうではなくて、作品の中に内在化された歴史の問題というのを考えることが必要かなと、だいぶ前に思っていたということです。

(6)記号という宿痾
さて、またちょっとルソーの話を続けますけど、先ほど言ったようにルソーは記号といいますか、言葉というものに対して非常に独特の感覚を持っていた。障害として意識しているという側面から始まって、単に障害とは言い切れないのですが、そのことが非常にルソーの一貫した姿勢をつくっているだろうと思うんです。
なぜそういうことを言うかというと、つまり個々の作品についての作品論的な話をいましましたが、それを貫いているルソーの一貫した姿勢の問題みたいなものがあって、その問題というのはやはりちょっとお話ししておくと、おもしろいかなと思うのです。
先ほど言いましたように、ルソーは1750年に『学問芸術論』という書物で論壇にデビューするんですけど、それより少し前には、自分は音楽家であると言って、新しい音符の書き方を発明しているということで、パリで売り出すんですね。楽譜というのはいわゆる五線譜であったり四線譜であったりするわけですが、そのように音符を記号で書くのではなくて数字で表現する。数字化することができるので、数字による音楽表記法というのでルソーはデビューしようとするんですね。たぶんこれは実際にも使いにくかっただろうと思うんですけど、一部では何か評判になったらしいのです。あまり売れなかったのですが、つまりそういう記号というものに対して非常に関心があった人であることは確かだと思います。
で、先ほど少しお話しした自伝の話なのですが、ルソーは『告白』という作品を1765年から70年ぐらいの間に書きます。これは要するに、自分という人間を自然のままに書くという企てをするぞといって書き始めるんですね。最初に、要するに自分は自分が見てきた誰とも同じようにはつくられていないんだ、ということから始まるんです。その自分というのをここで書いて、この書物をもって最後の審判に臨むと書いています。要するに神に読んで欲しいと。神がこれを読んでくれると、神は自分が無垢な無実の人間であることが分かるはずだ、というように書き始めるんです。
このこと自体がおかしいわけですよ。つまり誰とも違う人間である自分を、誰もが使う言語を使って表現するということ自体、ちょっと無理があると誰でも考え付くわけですが、ルソーはそのように考え、それを解読できるのは最後は神様だと、神様を信じていたかどうかは分からないところがあるんですが、そういう言い方をします。
で、この著作は途中で一度中断するんですね。第2部からはほとんど被害妄想みたいな、他の哲学者から迫害を受けたという話が延々と続きます。その第2部の最後のところに出てくる話なのですが、自分が書いたこの原稿の朗読会を開いたと、でも誰も何の反応も示さなかったというんですね。つまり文字で書いて、それを読み上げるわけです。声に変えるわけですね。全然それが誰にも通じなかったというわけです。
その次にルソーはどうするかというと、今度は『ルソー、ジャン=ジャックを裁く―対話』という対話篇を書きます。これも翻訳が出ていますが、『告白』ほど読まれている本ではないです。これはすごく変な本です。ジャン=ジャックという著作家がいる、その著作家についてルソーという人物とフランス人という人物が対話をする、それが『ルソー、ジャン=ジャックを裁く―対話』という、「審判する」と言ったほうがいいかもしれませんが、そういう著作の構造です。
ルソーという登場人物は、そのジャン=ジャックという人の著作を読んで、この作者は悪い人ではないなと思っている人です。一方、フランス人というのは、ジャン=ジャックに会ったことがないし、ジャン=ジャックの作品を読んだことがなくて、でも世間の評判を聞くと、ひどい奴だと思っているという人なんですね。その二人が対談をする。
対談していくと、二人の間が少し近づいて、それではというので、ちょっと正確に覚えていないんですけど、ルソーはジャン=ジャックの著作を読んでいるので、では著作の本人に会ってみようと思うわけです。で、フランス人のほうは、一回ちゃんとジャン=ジャックの著作を読んでみようと思うわけです。読まずに噂話でジャン=ジャックは悪い奴だと思っていたわけですね。
で、ルソーは、自分が考えていた著作の作者、「この人は悪い人ではないな」と思っていた人と実際に会ったジャン=ジャックとが一致して、ジャン=ジャックはいい人だったと、作品を書いている人として自分が想定していた人と重なった人だと結論するわけです。一方、フランス人のほうはジャン=ジャックの作品を読んだら、世間の評判は間違っていたなと気付くわけです。
そこで、二人でジャン=ジャックをなんとかしようみたいな話になるんですが、つまりジャン=ジャックという人の書いた作品を読まずに批判している連中と、ちゃんと読んだらよく分かった人たちという構図がそこにできているわけです。
つまり先ほど話したように、作品を書いた人とその解釈とはどういうことかということ自体が、ルソーの自伝のテーマになってしまっているわけです。しかもルソーは、この『対話』草稿を絶対に誰かに盗まれて悪用されると思って、ノートルダム寺院の祭壇のところに持って行って、そこに置こうとするんですね。それで行ったら、ちょうど鉄柵が閉まっていて駄目だったわけです。その駄目だったという話もまた書いて、さらに「今なお正義と真実とを愛するすべてのフランス人へ」と書いたチラシをつくって、道行く人に配ろうとする。ところが、誰も受け取らないんですね。またその話も書いている。
そういうことをやったあとに、今度は最後に『孤独な散歩者の夢想』という文章を書き始めます。これは最初に「かくて私は地上でたった一人になってしまった。兄弟も隣人も友だちも、自分以外には何の付き合いもない。そういう人間になってしまった」という、非常に悲痛な書き方で始まります。それで「この書いたものがもうどうなろうと、失われることになっても、かまわない」というように書くんですね。これは表現をめぐる変化があって、非常におもしろい。
これは桑瀬さんがまさに繰り返し言っていることですが、つまりルソーの作品というのは、何かについての作品ではなくて、それ自体が何かである。事件としてのと言ってもいいかもしれませんが、そういう作品である。あるいはそういう作品を書いてしまう人間というのが、18世紀に出て来たわけですね。その問題というのは、その後たぶんわれわれまでずっと続いている問題で、ルソーのせいかどうかは分かりませんが、現在にまで至ると思います。
問題は、いま言ったようなお話はルソーだから言えるのであって、ルソー以外の思想家に同じような扱いができるのかということがもう一つ、政治思想史研究の問題としてはあると思います。なんとなくですが、私は、18世紀以降についてはかなり言えるのではないかと思います。やれるのではないかと思います。文学研究なんかだと、そういうことはすごく意識されているので、文学の専門家の方々のほうがお分かりかもしれませんが、18世紀以降はそういう問題ができるようになるのだろうと思います。
やはりある種18世紀のおもしろさというのは、ちょうど境目であるところです。18世紀はユートピア文学がいっぱい出てくるんですね。ユートピアというのは、やはり現実とのある種の緊張関係をつくり出す文学なわけです。現実とは違う世界を描く。それによって、文学が現実と関わる。広い意味の文学ですけど、そのことが持っている政治性みたいなものが18世紀に非常に露わになってくると思います。

3.啓蒙という身振り
そのことはもう少し言っておくと、ここからは簡単な話にしますが、それは思想というのはどのように他者と向き合っているのだろうかということで、一つは啓蒙の問題です。18世紀というのは啓蒙の時代と言われますが、そもそも政治についての言説、あるいは政治でなくてもいいのですが、ある種の思想というのは、現実に関わる場合、啓蒙という身振りから逃れられないのかということです。
ここで言う啓蒙というのは、すごく簡単に言ってしまうと、知的に優れた個人とか集団がその知的な高みから、知識を持たない人とか劣っている集団に対して正しい知識をきちんと注ぎ込むことによって、誤った知識とか遅れた理解とか認識を直して、全体がよくなるということで、そういう考え方から逃れることができないのだろうかということです。これは言うまでもなく、教育一般の問題です。啓蒙でない教育というのがあるのか。常に教師は学生より上なのかと言ってもいいですが、そういう問題だろうと思います。
これはすごく大きな問題なのですが、とりあえず政治の問題としては当然20世以降すごく大きな、まあ、19世紀からと言ってもいいですが、いや、フランス革命もそうだと言えばずっとそうですが、大きな問題だろうと思います。
もちろん20世紀で言えば、社会主義の革命の問題ももちろんそうですが、戦前の日本の近代国家の形成それ自体がそうですし、戦後の民主主義というのは、知識人のあり方の問題あるいは大学の役割の問題と結び付いていることである。別の言い方をすると、民主主義すらも啓蒙という方法から逃れられないのか。常に知的な高みに立って、遅れた大衆であるとか無知な大衆を啓蒙するという知のあり方しかないのかということです。
このことは必然的に権力的な構造を伴うわけで、知と権力の結合ということを意識せざるを得ない。これを克服する方法というのはあるのだろうか。これは全然答えが出ていないのですが、先ほど言ったように、最初からの関心でありました。
ルソーの著作というのは、ある種の複線的な構造を持っていて、理念と現実とのずれを作品自体の中に組み込んでいると先ほど言いましたが、別の言い方をすると、批判というのが内在化されているわけで、そういう論理の組み方というのは可能なのかなと思うわけです。
結論が出ているわけではありません。啓蒙の問題というのはやはりすごく大きな問題だと思います。

4.思想の教義化と政治の宗教化
もう一つ、「思想の教義化と政治の宗教化」というタイトルを付けておきました。これも簡単なことだけで、全然考えが進んでいるわけではないのですが、啓蒙の問題というのはもちろんある種の宗教の問題と結び付いています。宗教の問題をどう考えるかというのは、もちろんヨーロッパの政治思想をやっていればキリスト教の問題として直接関わってくるわけですが、もう少し一般的に宗教と政治とか、宗教と思想、あるいは宗教思想と政治というのがどう関わっているのかという問題です。
繰り返し名前を挙げますけど、有賀先生の『宗教改革とドイツ政治思想』というのは、やはりその問題をもろに扱ったものだろうと思います。あるいはヨーロッパにおける国家と教会の分離の問題も、もう少しきちんと考えなければいけないと昔から思っています。
思想の教義化と政治の宗教化というのは、要するに真理を手にした者、あるいは自分は真理を手にしていると信じた者、その人間あるいは集団がどのように行動するかというと、当然社会をその真理に近付けようとするわけですね。これは当然ある種の啓蒙の身振りを取らざるを得ない。社会をその真理に近付けるために努力する。これは思想の内容の問題なのかどうかよく分かりませんけど、例えば政治集団が宗教集団化する、政治思想が宗教化する、教義化していく、ということが起こる。
私の世代はちょうど1970年代の初頭に大学に入学したわけで、私は一浪しているのですが、一浪した受験の直前が連合赤軍事件なんです。大学に入ったあとも内ゲバの時代なんですけど、ある種の集団が宗教化するというと宗教に申し訳ないんですが、どんどん閉鎖化していくのをある意味では目の当たりに見ている。要するに党派というものと宗派というのはどのように違うのかというのは、かなりリアルな問題でした。
これはたぶんいまでもかなり大きな問題だろうと思っています。昔のような形での学生運動がなくなってしまったので、そのように出て来ませんが、でも思想というのはどこで宗教とか教義に変わっていくのか、あるいは逆に宗教というのはどこで思想的なものとなるのか。思想と宗教って、言葉の違いに過ぎないのかどうかもよく分からないんです。ただ、宗教というのは、やはり考えを突き詰めていくところで、どこかで思考にバイパスを置くんだろうと思うんですね。それは神であってもいいし、聖典の言葉であってもいいし、奇跡でもいいんですけど、思考の過程で何かを飛ばす。その飛ばしたことに意識的であるかどうか。意識的だけれども飛ばしたままにしておくという場合も含めて、やはり何かを飛ばすんだろうと思うんですね。
こういうことはどんな思想でも、どんな研究でもあり得るだろう。何が飛んでいるのか。それを検証する力というのが思想自体の中にうまく組み込まれているかというのが、一つ非常に大きな問題であるということと、研究でもいくらでも起こり得るということを考えると、やはり研究というのは、教育も含めたほうがいいと思いますが、本質的に共同的な作業で、一人で考えていても知恵は及ばないので、批判に開かれているということがとても重要なことだろう。それはやはり大学であるとか、あるいは学会というものが持っているすごく大きな機能ではないかと思うわけです。
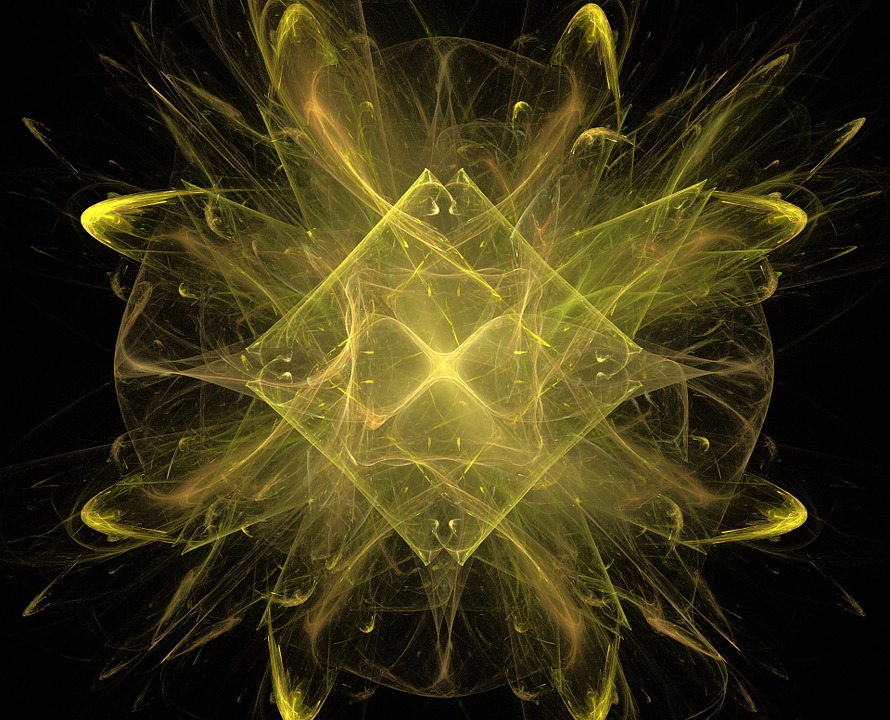
5.代表すること
さて、そろそろ終わりにします。最後は「代表すること」というので、これはちょっとしたエピソードです。1995年に海外研究でパリにいたんですけど、冬にパリで大ストライキがありました。よく覚えていないのですが、トラックの運転手の最低賃金の保障か何かではなかったかと思いますけど、パリに至る道を全部トラックが封鎖するんですね。それに同調する形で、SNCFという鉄道、それからパリのバス、メトロが全部止まります。要するに公共交通機関が全部止まる。それに同調するというか、同じように多くの会社もストライキに入っていきます。
いまのフランスは知らないのですが、その当時は少なくともフランスはストライキがものすごく強くて、ストライキは労働者の権利、圧倒的な権利だったんですね。一種のゼネストに入ってしまいます。でもおもしろいのは、労働組合の力が強いのかと思ったら、そうではなくて、フランスは必ずしもそのとき労働組合の組織率は高くない。誰でも権利としてストライキを主張することができる、宣言することができるということであったらしいです。
で、パリの交通というのは、完全にマヒしてしまいます。真冬のすごく寒いときです。でもすごく印象的だったのは、移動することを除くと日常生活はあまり困らないんです。食べ物はちゃんと新鮮な食べ物が届けられるわけです。その間もちろん、12月でしたが、政府、政党それから組合の指導者たちの交渉が続くわけですが、ストライキは一向に解けないんです。で、どうなるかなと思っていたら、12月の25日か20日過ぎに、ある日突然何か妥結して一気に正常に戻ったんですね。
そのとき思ったことなんですが、選挙というのは、自分たちの代表を選ぶと言われていますけど、要するに自分たちのリーダーを選ぶということだと。で、ふだんはリーダーに基本的に任せて、一方自分たちは自分たちの日常があるわけで、労働者は労働をするわけです。リーダーは自分たちのために働いて、必要に応じて自分たちに指示を出していく。通常は基本的にリーダーの指示に従う。
だけど、リーダーに任せているといっても、日常はあるわけで、その日常において問題が起こった場合には、自分たちで行動する権利を全く放棄しているわけではない。要求を掲げてストライキに入ってしまう。そしてその調整をするのはリーダーの役割である。
その感覚ですね。つまりリーダーたちを選んだんだから、リーダーたちがちゃんとやるのは彼らの仕事であって、自分たちはそれによって拘束されることはないわけです。別の言い方をすると、ある種の代表制とか代議制というのは、政治の直接性を制限したり排除することはないということです。
これはすごく当たり前のことであると私も思います。自分たちが自分たちの代表を選出していることと、自分たちが権利を行使していることは矛盾しないわけです。これはフランスのエリート社会の組み方の問題、あるいはエリートの社会的機能の問題とかと少し絡んでいるところもあって、一概に一般化はできないと思いますが、そのときすごくそのことを思ったというのが一つです。
もう一つ、8年前に総長になったわけですが、そのときに総長として挨拶をする。総長の仕事は挨拶をすることが大部分なんですけど(笑)、総長として挨拶するときは、立教大学を代表してというようにしゃべるわけですね。そのとき、これは本当に直観的にそう思ったのですが、代表するというのは表現するということであると。要するに、ここで私が「立教大学を代表してお祝いを申し上げます」と言ったときに、その言葉を通じて、立教大学という観念の共同体がそこに現前するんだという感覚を持ったんですね。つまり、リプレゼントというのはそういうことなんだと。
別の言い方をすると、その代表する、リプレゼントする行為がないと、立教大学という共同体はそこに現れないわけです。その都度私が総長として立教大学を代表すると言い、その行為をすることによって、立教大学が常に繰り返しそこに現れてくるということであって、別の言い方をすると、立教大学があらかじめ存在するわけではないのではないかと、ある種の実感を持ちました。
ただ考えてみると、これも相変わらず有賀先生と斎藤先生の名前を挙げますけれど、阿部斉先生と3人で書いた『政治:個人と統合』の中で代議制について、統合の問題としてこの問題を扱っているのです。代表というものが持っている機能というのは、そういう表現することによって、そこにある共同体をつくり出すわけです。
もちろんそのつくり出され方は、それぞれの例えば代議士によって違うわけで、そこに政治の空間がもう一度できてくるわけですが、そういうこともまた実感として感じたというのを最後にお話ししておきます。別の言い方をすると、要するに総長の仕事というのは代表することだ、表現することだということを実感したということで、あとひと月弱で立教大学を代表することも終わるんだなということを、いまつくづく感じているわけです。
おわりに
ということで、本当に今日はありがとうございました。講義と言えるような話ができたわけではないし、なんとなく昔から40年、何も変わらないじゃないかというように(笑)、ちょっと振り返ると、段々暗くなってくるんですけど、とりあえず退職前に教壇に立つことができた、もう思い残すことはないということです。ただあと1カ月弱総長の仕事が残っているので、注意深い総長でありたいと思っております。どうもありがとうございます。(拍手)