たいせつなことはすべてあなたが教えてくれた、プリンス! (Phase Two)
プリンス、HITnRUN、2015年.
Prince, HITnRUN Phase One, NPG, 2015.
Prince, HITnRUN Phase Two, NPG, 2015(2016).
桑瀬章二郎(立教大学)
2 N.O. and N.K.
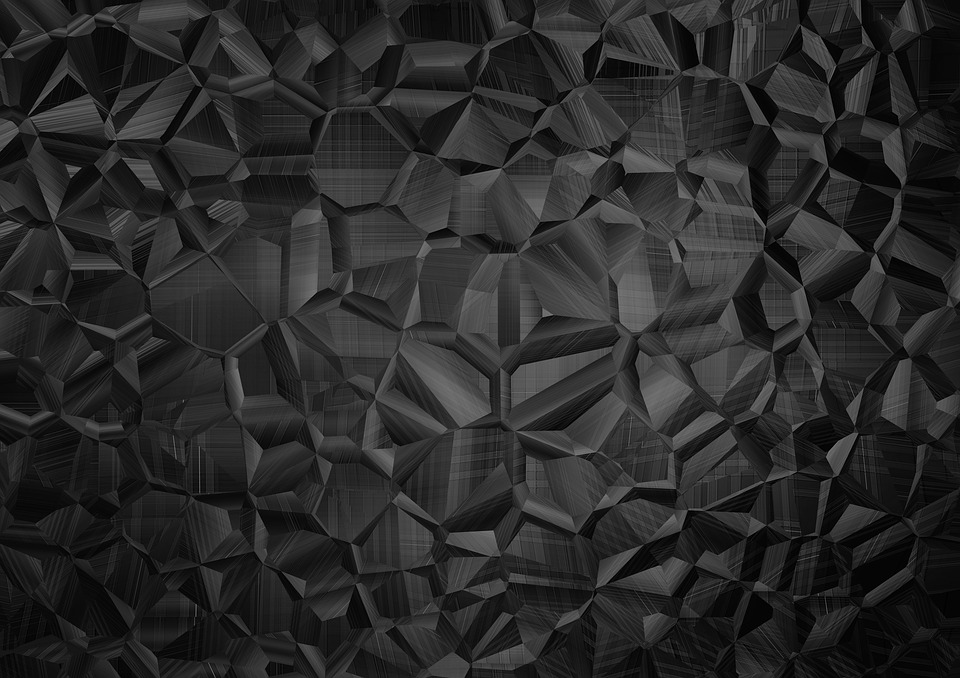
しかし、Love Symbol Album (1992)以降、やはり、狂信的かつ身勝手な熱情は徐々に冷めていったように思う。どこまでも挑発的で、押し殺したような怒りが通底するCome (1994)はまちがいなく傑作だった。自分が勝手にプリンスの全盛期とみなしていた1987年にリリースされるはずだった(発売を当時どれほど待ち望んだことか)The Black Album (1994)は、Sheila E.の圧巻のパーカションで閉じられる"2 Nigs United 4 West Compton"が象徴するように、ファンキー音楽(単なるファンクではない)の極北であろう。時代の流行などいっさい無視したあらゆる意味でシンプルなThe Gold Experience (1995)は、先行シングル"The Most Beautiful Girl in the World"まで買って待ちに待って届いたアルバムだったはずだ。余計な前戯など不要だといわんばかりにいきなりサビを挿入してみせる奇抜でありながらキャッチーでもある"My Computer"のような名曲に随所で出会う3枚組の「自伝的」アルバムEmancipation (1996)もずいぶん聞き込んだ。だが、それにもかかわらず、久しぶりに聴きなおしてみると、ほとんど初めて聴くような曲もあることに気づかされ、心底驚かされた。Chaos and Disorder (1996)にいたっては、まるで新作を聴いているようだった("Into the Light"から "I Will", "Dig U Better Dead"へと続く後半部に当時、本当に何も感じなかったのだろうか)。The Vault: Old Friends 4 Sale (1999)についても同様だ。自称「信者」の私はまともにプリンスを聴いていなかったのかもしれない…。
このように、音楽家プリンスについてでさえ自分に都合のよい解釈を続けてきた者、さらにそのパフォーマンスを一度も見に行く勇気のなかった小心者の言が何ら信憑性も持たぬことは承知のうえで、あえて付け加えておくなら、私は若き日の彼を最も優れたダンサーのひとりであると固く信じていたし、今なお信じている。音楽同様、いや音楽に応じて進化し続けてきたそのダンスは、まさしく彼のみが駆使することのできる特異な身体言語であるというほかない。あれは「パープル・レイン・ツアー」の映像だっただろうか、あらゆる細やかな「動き」が(ジェイムス・ブラウンのように)反射的・自発的でありながら同時に計算しつくされてもいる、つまりは制御不能のようでありながら完全な制約の美でもある"I Would Die 4 U"のたった数分間の完成されたストリップショー。あるいは"Diamonds and Pearls"のPVでの高貴かつ猥褻な「舞」…。ハイカルチャーとマスカルチャーという二項対立などプリンスを前に意味を成さないと信じていた過去の自分を今なお肯定しようとは思わないが、振付家やダンサーの数々の「動き」がすぐさま形式化・定型化されていくのに対し、プリンスの「動き」は誰にも模倣できない。
もう一点、PVについてもひと言触れておくなら、高い評価を得た"Black Sweat" (2006)を挙げるまでもなく、アニメーションが曲調にぴったり合った"Raspberry Beret" (1985)、歌詞の単語のみが流れ、浮き出ていく演出がいかにもこの実験曲にふさわしい"Sign o' the Times" (1987)は、近年映像作品の収集・所蔵に余念がない、いまだハイカルチャーなるものが存在すると信じているどこかの近代美術館がしっかり保存しておくべきだろう。
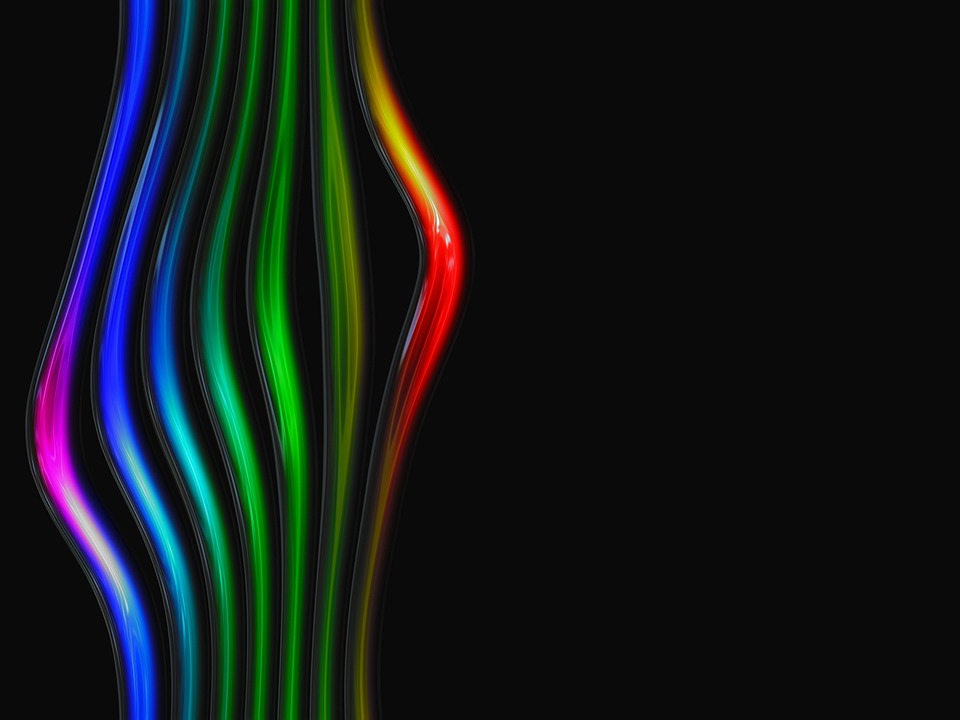
ところが、世紀とともにすべてが一変してしまった…。マスマーケットを意識した、それでありながらかつての名作のような多様性と強固な統一性を備えた、もっとも好きなアルバムのひとつRave Un2 the Joy Fantastic (1999)のあとに、問題作The Rainbow Children (2001) が届いたのだった。このアルバムもかなり聴き込んだはずだし、主要曲のすばらしいライブ演奏もOne Nite Alone... Live! (2002)で何度も何度も聴いた。けれどもあの劇的な変貌を理解していたとはとうてい思えないし、今でもやはりまったく理解できていない。そもそもひとりの人間の生に起こった大転換・回転・改革・(とりわけ宗教的)転回など、アウグスティヌス(『告白』)からロラン・バルト(とりわけ『小説の準備』、『喪の日記』)にいたるまでの無数の例を挙げるまでもなく、その時期や起源など特定しようがないし、他人がこれを推測・記述しようとする試みほど傲慢なものはない(Raveにいっさいその痕跡がないと誰が断定できよう)。いずれにせよ、この時期を境に私は、プリンスの「歩み」を辿ることさえ放棄してしまい、私の曲解は必然的にさらに戦略的な誤読となっていったように思う。私は彼からますます遠ざかっていったのだった。
その後の「歩み」も、今から考えれば記念碑的なものだ。"Cinnamon Girl"から"What Do U Want Me 2 Do ?"への転調が、プリンスの作品世界の無限の広がりを思い出させてくれるMusicology (2004)。
"Te Amo Corazón", "Black Sweat", "Beautiful, Loved and Blessed"といった名曲が象徴するように、プリンスにとって侮蔑的表現ともなりうる洗練(というのも、彼の場合、洗練の洗練は後退ともとれるのだから)という語を用いたくなるような、抑制の効いた完成度の高い3121 (2006)(だが、クレジット最後にはやはり「All praise and glory 2 the Most High-Jehovah」とある…)。
ミュート・トランペット(共同録音が噂されたマイルス・デイヴィスのDoo-Bop (1992)ではプリンスの演奏が聴けず落胆したものだ)とピアノに歌声が絶妙に絡み合う"Somewhere Here on Earth"や、最初のメロディーで心鷲掴みにされる"Future Baby Mama"といった優れた曲の並ぶ Planet Earth (2007)。
二枚のプリンスのアルバムと当時の恋人Bria Valente のデビュー・アルバムから成る三枚を全編通して聴けば壮大な建造物を眼前に見るような気がするLotusflower (2009)(プリンスは楽曲提供者・プロデューサーとしても卓越した存在だったとするのが定説だが、私はそれならジャム&ルイスのほうがはるかに好きで、 Bria Valente のElixer は、ほとんどプリンス自身の曲といえるそのタイトル曲があるからこそ輝いているとしか思えない)。
もちろんがっかりさせられたアルバムもある。20Ten (2010)はタブロイド紙に(その一部あるいは付録として)発表されたもので、当時パリにいた私は『クーリエ・アンテルナショナル』をキオスクに買いに走ったものだが、これはいったいいつ録音されたものなのだろうと首を傾げたものだ。Plectrumelectrum (2014)は私が大の苦手とする完全なロック、楽曲名を借りるならファンクンロール・アルバムで、"TicTacToe"のような音韻、抑揚、「リズム」、言葉遊びから生み出されたのではないかと思わせるようなユーモラスな曲に感心しはしたものの、やはり好きにはなれなかった。
Art Official Age (2014)は久しぶりにあきれるほど繰り返し聴いた傑作で、実に難解な歌詞の"Way Back Home"から"FunknRoll (Remix)", "Time"へと流れるアルバム後半は見事というほかなく、囁くようなコーラスとピアノで閉じられる、すべてが終焉を迎えるかのような"affirmation III"には文句のつけようがない。だが、それでも私は相変わらず彼から遠く離れたところにいたように思う。
そして、HITnRUN Phase One (2015)が発表され、HITnRUN Phase Two (2015, 2016)が最後のスタジオ録音アルバムとなった。
これら最後のアルバムによって再びプリンスに回帰したというなら話は実にわかりやすいし、この駄文も追悼のことばとなりえたのかもしれない。けれども、(恥ずかしながら)私とプリンスの距離はいっこうに縮まらなかった。
底抜けに陽気かつ晴朗に、いわゆるマイケル・ブラウン射殺事件とフレディ・グレイ事件の被害者の実名を組み込みながら、「平和」を優しく歌いあげる"Baltimore"の曲調はアルバム全体を見事なまでに支配しており、プリンスにしか作れない傑作であることはまちがいない。けれども私はこの二枚のアルバムに決して夢中になったわけではなかったのだ(プリンスにおける「政治」を狭義でとらえるのには賛成できず、「No Time 4 Politics」と歌う彼の「政治性」にいまだ強く惹かれる)。
理由はいたって単純で、私は常にプリンスに「前衛」でいること、「前衛」であり続けることを一方的に求めていたのだ。「前衛」なる概念それ自体の正当性にさまざまなかたちで疑義が差し挟まれ、「後衛」といった概念が持ち出されもしたのははるか数十年前のことで、そうした議論を知らなくはなかったというのに、私はどういうわけかプリンスにだけは、どうしても、「前衛」、それも言葉の最も単純な(さらに最も身勝手な)意味での「前衛」、先駆的で先鋭的で「体制」に揺さぶりをかけうるような「前衛」であり続けることを望んでいたのだ。あらゆる知と芸術の「終焉」が語られはじめていたにもかかわらず、である。プリンスにとって「前衛」であることなどほとんど意味を成さなかったかもしれないのに、である。
いや、もっと卑俗な理由からだろうか。世の中には「選ばれし者」と「選ばれなかった者」しかいないという、小学生にでさえ笑われるであろう世界観に立って、「選ばれなかった者」としてどう生きていけばよいのかと、友人とろくでもない議論をしながら「犬の様にうろついていた」あのころのプリンスを特権化することによって、何ひとつ変われぬ自分、まったく成長できぬ自分を肯定しようとしていたのかもしれない。そして、その友人たちもプリンスも、転回と成熟を経て、移動していった…。