ローラン・プティが織りなすバレエと「神話」の幻想 ―『若者と死』を巡って― [1]
森絵磨(立教大学文学部4年)
序
何が起ころうとも、あの舞台の美しさはフットライトを飛び越える。あの全体の雰囲気は、そのままわたし(moi)の、わたしの寓話(ma fable)の、わたしの神話(mes mythes)のフィギュールであり、『詩人の血』の無意識のパラフレーズとなっていた[2]。
フランスの詩人ジャン・コクトーは、舞台上で自身の爪弾く「寓話[3]」、そして「神話」が花開く瞬間をこのように認めている。時空間を超越する軽やかさ、そしてスペクタクルを永遠と化す美しさ。コクトーは図らずとも生まれた神秘を自ら台本を手掛けた『若者と死』に見た。20世紀を代表する傑作と称され、今なお上演され続けている「ミモドラム[4]」、それが『若者と死』である。パリ・オペラ座出身で後に世界的な活躍を見せる、若き日のローラン・プティが振付を担当し、舞踊にまで拡張する非言語コミュニケーションが可視化されている。コクトーが頻繁に用いた神話は、プティのもとで舞踊とも調和を果たしたのである。だが、一括りに神話と言えど、オルフェウスにオイディプス等、様々なモチーフを作品に取り込んできたコクトーは、『若者と死』に対して如何なる意味を付与したのか幾分不明確だ。その上、コクトーが作品の中から見出したのは、フットライトを飛び越え、未来へと通ずるような神話であろう。この神話が歴史に埋没せずにスターによって受け継がれているのは、おそらく、後世のダンサーにも伝授を続けたプティの功績にほかならない。そのため、彼の神話を表出させ、世代が変わりゆく中でも伝承されるように導いたプティこそ、『若者と死』における真の立役者なのではないだろうか。
そこで本稿では、『若者と死』において、プティが果たした(あるいは果たしたかもしれぬ)役割を再検討することを目的とし、「神話」というキーワードを手掛かりにしながら、議論を進めていく。そして、プティの登用によって、間接的に作品に「作用」することになった「部分」に注目し、それを集中的に分析を進めることで、作品に新たな可能性を与えてみたい。そもそも、何度もオルフェウスに身を重ね、詩人としての歩みを続けるようなコクトーゆえに、彼と神話は永遠に切り離し難いテーマである。したがって、神話に関するコクトーの先行研究は膨大に存在し、われわれは凡庸な帰結に陥りかねない危うさを抱えることになるだろう。しかしながら、彼の神話とバレエの関係性に着眼した研究は意外にも少ない[5]。『若者と死』における「神話」を物語る術、すなわち身体表現を担当したのがプティのために、研究の範疇がコクトーとの間で分散していることも原因だろう。さらに「ミモドラム」というジャンルが、舞踊と演劇の狭間で作品を宙吊りにさせ、解釈を困難にさせている。舞台芸術の一つに包摂されることで、バレエと「神話」の直接的な結びつきの遅延という由々しき現状が浮かび上がってしまったのである。延期を余儀なくされた舞踊詩的な「神話」を認めるためにも、バレエの振付に触れなければならないのだ。
それゆえ本稿では、プティが成し遂げた役割を見極めるべく、第一部では、あえてコクトーの描き出したプロットを忠実に読み直す。その後、第二部でプティの振付を中心に、作品内の舞台装置や音楽にまで分析の対象を広げ、「神話」となる過程を考察する。とりわけ第二部では、プティのあらゆる作品との比較も行うが、これは、あくまで『若者と死』という萌芽が開かれる様子を確認する方法にすぎない。もちろん、『若者と死』はコクトーが台本を手掛けた上に、音楽の差し替えもあり、プティにとっては例外的な作品に該当する。他作品との比較に際し、『若者と死』を主軸に置くことはリスクを伴うだろう。その危険性を顧みず、豊穣な作品世界の深みを探るのは、洒脱、軽快といった言葉で形容されがちなプティのイメージを再考するためでもある。コクトーとプティ、両者ともに多岐に渡る活躍を見せ、バラエティに富んだレパートリーが高く評価される一方、広く浅い印象を与えてしまうのも事実で、上演回数は減少の一途をたどっている[6]。こうした短絡的な固定観念を払拭すべく、コクトーにとって「寓話(fable)の非現実は真実になる[7]」ように、「神話」が時代の枠組みを超越してくれると信じ、一見無鉄砲かもしれないが、プティの振付をメインとした『若者と死』の考察を試みる[8]。
第1部 『若者と死』のプロットに関する考察
第1節 概説
1946年6月25日、パリ・シャンゼリゼ劇場で『若者と死』は初演を迎えた。プティがディアギレフの秘書を務めたボリス・コフノと手を組み創設したバレエ・デ・シャンゼリゼ(シャンゼリゼ・バレエ団)のお膝元での幕開けであった。第二次世界大戦の影響が色濃く残る中、舞台を埋め尽くしたのは、パリ解放直後の現実[9]。コクトーは、ロマンチックでもエキゾチックでもない、都会的な儚さに美を見出したのである。そのため、『若者と死』には歴史的な背景が透けて見えるが、この「時代性」の鍵は、コクトー以上に、実はコフノが握っていると言っても過言ではない。なぜなら、詩人や振付家の顔を併せ持つコフノは、自らも頻繁に台本を手掛けるほど、バレエ団の運営に奔走しており、コクトーへの声かけもその一環であったからだ。コフノは、コクトーに対して、当団のダンサーで「大いにヴァーツラフ・ニジンスキーのエネルギーが認められる[10]」ジャン・バビレをもとにした新作を依頼した。そのうえ、人々の心を揺さぶり、「時代を完全に一新した『薔薇の精』のような作品[11]」を探しているのだとコクトーに相談を続けた。名作への挑戦とは言え、ロシア・バレエ団の公演に衝撃を覚えて以来、ディアギレフからバレエの洗礼を受け続けてきたコクトーにとっては、申し入れを断る理由が見つからなかったかもしれない。ある意味、コフノの熱心な要請は、ディアギレフの死後、バレエと疎遠になっていたコクトーの舞踊への情熱を呼び覚ましたと言える[12]。目覚めた詩人の行動はすばやく、早速コクトーは、視覚効果に長けたカリンスカを衣装、彼の映画装置も担っていたヴァケヴィッチを舞台装置、新進気鋭のローラン・プティを振付家に抜擢した。あっという間に盤石の布陣が整ったのである。
さて、依頼されたコクトーのリブレットだが、内容自体はいたってシンプルである。屋根裏部屋で一人鬱屈としている若者のもとに、彼の愛する美しい娘が現れる。必死に娘を惹きつけようと試みる若者だが、彼女に散々翻弄された後、逃げ去られる。苦悩のあまり、首を吊る若者。すると天井が開いて、エッフェル塔が浮かび上がり、再び現れた「死の女神」=娘とともに、若者はパリの夜を歩み続ける。終わりの見えない旅路に踏み出した若者は、「いま、ここ」に焦点が当たっていた舞台を無限の時間へと切り開くかのようだ。こうして現代的な『薔薇の精』は、ディアギレフやニジンスキーの精神を秘めつつ、コクトー独自のタッチで生死を彷徨う若者に変身を遂げたのである。
しかしながら、コクトーの特異性は物語の筋に収まらず、むしろ音楽の使用方法にて際立っている。大胆にも、コクトーはリハーサルで扱っていた音楽を本番では別の曲に変更することを提案したのである。エッセイでは当時の心境が以下のように語られている。
私は役者がジャズのリズムにのって稽古し、このリズムが単なる練習道具とみなされ、後にモーツァルトやシューベルトあるいはバッハの偉大な作品にその座を譲るような舞踊劇が可能か考えた[13]。
それゆえ、初演キャストのバビレとナタリー・フィリッパールは、ジャズの「フランキー&ジョニー」でリハーサルを行っていたものの、本番では音楽の長さを決め手に見繕われた、バッハの「パッサカリアとフーガ」に乗って、即興で踊ることを余儀なくされた。最後まで曲が足りるのか、ダンサーを見守るコフノやコクトーにも緊張感が漂っていたが、心配をよそに音楽は舞踊と一致し、幕を閉じた。コクトーは映画でも、この手の差し替えを行っており、全ては「音楽と舞踊とが、ある瞬間に偶然に合致して、思いがけない神秘的効果を生む〈偶発的同時性〉[14]」の探求に集約される。このように、『若者と死』は、実験の失敗を度外視した冒険心によって、コクトーの肥沃な世界観に更なる実りをもたらしていくのである。

第2節 二項対立を孕むテーマ
『若者と死』。この題名を耳にするだけで、若者の死とせめぎ合う光景が脳裏に思い浮かぶのではないだろうか。単純明快なタイトルゆえ覚えやすく、端的に表された内容が、観る者の理解を促してくれる。題名一つで、バッハの音楽と同等のシンクロニシティを示しているとも言えよう。ところが、どちらかといえば、物語自体は「若者の死(La mort d’un jeune homme)」として進行している。コクトーの「死は一瞬一瞬わたしたちの中にあり、また、甘受しなければならない[15]」との考えを踏まえても、死は本来、われわれと分離することがないため、若者「の」中に位置付けるものだ。たしかに、死を恐れるあまり、「寓話(fable)[16]」を作り出し、外側から判断してしまう人間は後を絶たない。コクトーがそんな人間を訝しみ、彼自身は、死が内部に存在する現実を受け止めるスタンスを貫いているのも事実である。だからこそ、直視しないことで享受できる幸せにもコクトーは切り込んで行く。最終的には、死を「わたしたちの若さ[17]」と言い切るように、内なる死との拮抗が、若者を若者たらしめていることは明らかだろう。両者の相互作用は、若者「の」死を以ってして、始めて強調されるのである。だが、表面的には正当性を認められた「若者の死」も、そのタイトルを語る際、実は一つの盲点を生じさせている。なぜなら発話者が知らぬ間に生者の観点に立ってしまうからだ。「若者の死」の場合、ある種、謎に覆われた死が見えているという幻想が先走り、死を受け止める責任を割愛することで安堵感に至れるのだと考えられる。つまり、「若者の死」と名付けられることは、逆説的ではあるが、生に囚われることを促してしまうのである。
実は、人間が包括する死を綴る一方で、コクトーは、人の命が尽きる時、死はようやく外に出られるのだと結論づけている。自ら命をたって完結するリブレットが提示するのは、見かけ倒しではない死者の、もしくはこの世を生きるにあたり手放さざるを得なかった眼差しであったのだ。よって、若者一人の内省が、死により外の世界へと広がっていくように、この二項対立は、あらゆる対象への還元を可能にしている。観る者の主観に応じて、「男と女」、「若さと老い」、「生と死」など、変容のバリエーションは無限大となり、自ずと『若者と死』は「不可避的に人間の想像力を二項対立の網にとらえてしまう[18]」ような「神話」の形態を取る。そのため、無限に分離する『若者と死』という題は、死と向き合わず、己と切り離すことで幸せを汲みする者には、外側からの判断をあて擦り、警鐘を鳴らす「寓話(fable)」としてしか映らないだろう。はたまた、死を直視するものには、「神話(mythes)」の様相で、不滅の希望の光を感じさせるのである[19]。
第3節 逃げ去る女
『若者と死』を多面的に論じるにあたり、まずは作品の中核となる登場人物の描き方を出発点に置くことにしよう。すると、コクトー並びにプティが人物像に用いる典型的なパターンとして、蠱惑的な美女と翻弄される男の構図が浮かび上がる。大抵、彼らは悲劇的な末路を辿りながら、死に接近していく過程が描かれ、『若者と死』のように、物語は弄ばれる男の眼差しで展開することが多い。男は、愛する存在との別れや運命づけられた死に抗えず、観客も彼の目線と一体化するために、女の捉え難さを追体験せざるを得ない。それゆえ、幕が降りたとしても、男の行先の彼岸となる女の存在が、一つの疑問として残る。バビレにインスパイアされていた若者に対して、抽象的で曖昧な「女」。コクトーやプティが描写する「女」とは一体何なのか、「神話」を形成する要素を抽出すべく比較分析を行う。
第一に『若者と死』における「女」とは、まさしく「死」である。命を絶った若者の前に髑髏の仮面をつけた美女が現れるが、その正体が若い娘であったように、「女」が「死」であることに疑いの余地はない。しかしながら、内にある死から目を背け、若さを汲み尽くしてこそ「若者」となり得るコクトーの観点を踏まえると、死に魅了される主人公には矛盾が生じている。元より、死と向かい合うことに恐怖や嫌悪を抱くのが人間の特性であり、命を喪失する危機感ゆえに身体を苛む脅威を回避できるため、若者が恐れるのも無理はないはずだ。むしろ当然の反応である[20]。実際に若者も、挑発を繰り返す娘に反発し、抵抗するそぶりは見せており、何よりも恐れから娘の前では萎縮し、猫背気味で不安な面持ちを浮かべている。若者はダイナミックな跳躍、アクロバティックな回転技を行って、持ち前の活気を振り撒くが、かえって若さをも飲み込む死の強さが引き立っている。圧倒的な死は、若者や彼の舞台たる部屋を一瞬のうちに席巻してしまうのだ。とは言え、コクトーは、あまりにも耐え難い時間を過ごしているにつれて、死に心地よい感情を覚えていることもある[21]。耐え忍び、克服にかける時間が蓄積されると、逆説的だが、恐怖は甘美を助長するようになる。紛れもなく、「死」が欲望をそそっているのだ。若者は結局、女の抗い難き引力へ逆らうも、同時に貪るかの如く望みつつ、命を投げ出したのである。われわれは命を危険にさらすことに時として快感を覚えるがゆえに[22]、若者も欲望に忠実に従った結果、死をも嗜んでしまう。その結末が、図らずともオルフェウスのような古典悲劇と重なり合うとは知るよしもない[23]。コクトーは、若者に古代ギリシャより脈打つ煩悶の精神を宿らせ、他方で「女」には、「死」そして「運命[24]」を司るよう描いたのである。
ようするに、「死」は「女」という外観を携えて、若者に接近し、欲望を刺激する。若者に対置される娘が若く美しいのも、死を隠すためであり、美化された仮初めの姿をわれわれは眺めているに過ぎない。娘が若者を蹴散らす足先にさえ美は及び、その消失点はポワントにて紡がれている。先端にかけて幅が狭まるポワントは、脚の長さを引き伸ばすがゆえに、持って生まれた肉体の拡張、人間離れした浮遊間を演出することが可能だからだ。ミモドラムであっても、バレエのスタイルを踏襲する以上、マリー・タリオーニがシルフィードの荘厳な美しさをポワントにて遺憾なく表現し、観客を魅了したように、歴史的な所産たるトゥシューズの美学が、娘の神聖化を加速させるのだ[25]。
だが、妖精の爪先は、魔法にかけられているも同然で、かつてポワントの中には「生肉[26]」が秘められていたとも言われている。バレエ・ブラン〔白い衣装を身に着けて踊る作品またはシーン〕を支えるポワントの白さは、まるで腐敗を隠すべく研ぎ澄まされているかのようだ。審美的な漂白により、野蛮と思しき要素が排除され、えてして優位思想と結びつきかねない畏怖が足先から漂う[27]。爪の先まで文化的な思考が介在していると言っても過言ではないが、だからこそ、自然を否定し、構築されてきた人工的な美を侵犯することに憧憬が投じられるのだろう。プティの『ノートルダム・ド・パリ[28]』においても、舞台上で唯一ポワントを履き、白い衣装を身にまとって登場するエスメラルダが、フロロやファビュス、カジモドを惹きつけて離さないのは、当然の成り行きと言える。とくに、カジモドに水を与えるエスメラルダは、ジェームズと戯れる最中、彼の元へ小川の流水を運んでいくシルフィードと響き合い、ロマンティック・バレエから始まるとも言える処女性を明らかに受け継いでいる。次第にフロロやファビュスの色情に巻き込まれるのと並行して、彼女の衣装も赤、黒と変化していくが、その白さゆえに、我が色に染めてしまいたいという彼らの欲望を煽るのだ。処女ならしめるポワントは、『若者と死』における「女」の泡沫の若さに拍車をかけているに等しい。
このように、パリ解放後を描く『若者と死』の世界であっても、ロマンに満ちた理想美が、そこはかとなく香り続けていることが窺える。けれども精霊とは異なり、娘は現実的な側面も兼ね備えている。ポワントを我がものとなし、自らの一部となす筋肉質な脚は、その一つである。娘は黄色いミニスカート身につけているため、脚が一段と露わになっているが、晒さられた「筋肉[29]」は、妖精らしさ、いわば重力や隷属とは無縁の軽さを剥奪してしまう。プティが頻繁に用いた短くタイトなスカートは、足先だけを覗かせるロマンティック・チュチュとは異なり、「筋肉」を包み隠してはくれない。したがって、娘の脚は重さゆえに、物質的隷属を喚起し、ほどなくして彫刻となる[30]。この肉体による彫像は、腐敗や排他的な要素に引きずられてきたように、「死」から[31]常に姿を現す。それゆえ、「死」をも秘めたる肉体を前に、観客が目撃してきたのは、まさしくエドガー・ドガも刻み込み、ボードレールも詠った、「軽やかに上品に、彫刻の脚を進めて行った[32]」女である。現代に降り立った彫像は、見る者の目を眩ませ、その隙に通りすぎ、逃げ去ってしまうが、同時に、所有できないもどかしさという、愛の持続の残像を生じさせていく。つまり、娘のミニスカートはモード、彫刻と転ずる脚は「現代性[33]」を彷彿とさせる。瞬く間に消え去るため、二度と「女」は捉えられないが、かえって、美そのものは永遠となり、かつ真空された状態で保持される。若者にとって「才能[34]」とも表現される「女」だが、「現代性」を伴っているのかもしれない。何せ、コクトー自身が『若者と死』の屋根裏部屋を「きらびやかなもの、汚らしいもの、気品のあるもの、卑しいもの、すべてが、鈍い照明を浴びてさまざまな陰影を帯び、ボードレールの世界のようなたたずまいをみせているはずだ[35]」と語っている。退廃的な空気や倦怠感にも美が滑り込んでいるのだ。
さて、あぶくのように儚く、「理想」、「才能」、「死」を表す「女」は、畢竟、若者の「ネガ[36]」である。自分自身をやむを得ず投影してしまうがゆえに、女を直視することは不可能で、追い続けるほか道はない。皮肉なことに、絶対に満たされることがない確証が、所有欲を半永久的に存続させ、更なる呼び水となり、盲目的に女を求めてしまう[37]。仮に恋愛の不可能性に気がついたとしても、解決策は引き出されず、自分自身すら見えない現実によって、若者の葛藤は深まる一方である。若者と娘の境界線は、ほどなくして曖昧になり、線引きできないような関係性に陥る[38]。身体が秒単位で死に行く反面、肉体が彫像として刻み込まれていることに対するわれわれの忘却を踏まえると、なおさら内にあっても「他者」である「死」、そして「女」を理解することはあり得ない。映画『オルフェ』のラストは、一番大切なものが愛だと悟ることで締めくくられるが、愛を追求すれば、必然的に作品は悲劇的な色彩を帯びる。愛する対象への認識の不可能性に直面することは、若者を「女」に紐づけられる運命へと突き動かしたのである。あたかも、娘に手玉を取られ、受動的になった若者は、主体性を欠き、〈他者〉の欲望を体現するかのようだ[39]。若者は「他自我(alter ego)」の狭間を行き交い、自己にも他者にも愛を蕩尽しながら、生を食いつぶす愉悦に浸っているにほかならない。「女」とは、「死」や「ネガ」を映し出し、「寓話(fable)」を目覚めさせる「わたし(moi)」のフィギュール、まさに「神話(mythes)」の引き金なのだ。
第4節 死による再生と昇華
「わたし(moi)」のフィギュールである「女」を始め、『若者と死』には、至るところでコクトーの面影が見て取れる。『詩人の血』や『オルフェ』をも自在に行き来する「女」によって、観客は若者の世界におけるコクトーの再認を促されているからであろう。しかしながら、様々な作品を貫くコクトー独自の死生観を共有したとは言え、「わたし」を捉えられるとは限らない。コクトーは作品に自身を溶け込ませ、命そのものを脈打たせている[40]。「わたし」の理解には、コクトーの精神以上に、作品を流れる血、いわば彼の鼓動との共鳴が不可欠なのだ。それゆえ、古びた短絡的な手法に陥る危険を承知で、あえてコクトーの伝記的事実と比較分析し、「わたし」を多面的に探ることも、「脈動」を感じるためには、無益ではあるまい。
『若者と死』とコクトーの人生の交錯を見るには、少なからず彼の幼少期まで遡らなければならないだろう。若者は元より、コクトーが頻繁に用いる自死のテーマは、一般的に彼の父親ジョルジュのピストル自殺に由来すると考えられている。現に、絵を描くことが趣味であったジョルジュは、画家という若者の設定とも一致している。ジョルジュが命を絶ったのは、妻ウージェニーの不義によるショックという仮説もあるために、若者のみならず、劇中で逃げ去っていく女にも、両親の残像が見え隠れするのである。なお、コクトーが自分とジョルジュが非常によく似ていると感じ、自身も沢山のイラストを残した点を考慮に入れると、若者には、父から「わたし」へと流れる血が明らかに通っている[41]。それゆえ、『若者と死』という二項対立は、「父と母」、「息子と母」に転ずることが可能なのだ。若者をコクトーに置き換えることで、彼が自死を度々描く根源には、エディプス的な葛藤があったとも考えられよう。
実際に、芝居に出かけるため美しく着飾るウージェニーは、幼いコクトーの心をくすぐり、魅了してやまなかった。鏡と対峙しながら化粧に専念する時、ウージェニーは彼の知らない「他者」へと変貌していたために、母が母ではなくなる衝撃をコクトーは幼少期に早くも体験していたのである。母が手袋をはめる瞬間に至っては、「あの手袋のボタンを掛ける愛すべき儀式[42]」と捉え、身支度を壮大かつ印象的に形式化している。映画『オルフェ』においても鏡の向こう側に行く「通行手形[43]」であるように、手袋は死へと誘う特権的なモチーフ、さらには母のアトリビュートなのだ。娘が手袋をはめた指先で、若者の首筋を伝うシーンは、母の不実への疑い、「女」としての魅惑など、コクトーをよぎるウージェニーの影が窺える。つまり『若者と死』には、コクトーの生きてきた時間が、「わたし」の拍動となり、刻み込まれている。「わたし」は、精神的な価値観よりも常に肉体に根ざし、身を挺してでも生きた証を告白してくるのだ。待ち受ける先にあるのは死以外の何ものでもないが、コクトーは心血を注ぎ、独白を通して身をやつすことをも厭わない。それは詩人コクトーの創作の糧、もっぱらポエジーに迫るためであろう。
基本的にコクトーは、ポエジーを死や無意識に求める傾向がある。映画『オルフェ』でも、詩の才能に行き詰まったオルフェが魅せられるのは、愛する妻ユリディスではなく、死を操る女王だ。オルフェはラジオから聴こえる言葉の虜にもなるが、発信元は女王に殺された詩人のセジュストゆえに、死とポエジーは分かち難い。若く有望なセジュストの詩に夢中になるあまり、ユリディスには目も暮れず、虚ろな状態に陥ってしまうオルフェ。まるで、己の恋煩いに気が付かない若者のようだが、盲目になる相手が死である以上、成就されることはない。ポエジーを掴み所のないものとしてコクトーが捉えるのも、生きるか死ぬかという二者択一を迫られる、われわれ人間の限界と結びついていると言えよう。だが、容易に届き得ないからこそ、死は詩情を響かせ、凡庸な生を乗り越える場所となり、皮肉にも輝くのである。コクトー自身、『オルフェ』の序文で「詩人が生まれるには幾度となく死ななければならないのだ」と宣言し、このテーマが20年前の『詩人の血』ですでに展開されたことを明記しているとおり、死に沸き立つポエジーは重要な主題として反復している[44]。そして、先述のように自らを退行せしめ、幼少期や無意識的な領域に潜り込むこともあるが、これもまた詩の源泉を探り当てる手立てだ。ただし、精神分析学的発想は,幼児期の生育体験による呪縛が否めず,無意識的な領野が自己にとっては変更し難く、拘束してしまう可能性を踏まえると[45]、フロイト的な葛藤、コンプレックスに対する追求は、コクトーの想像力の足枷となりかねない。安易に近寄ってしまうと、固定観念に自らを縛り付ける結末を招くことはコクトーも理解していたはずだ。それどころか、コクトーはレッテルを張られる危うさを理解しすぎていたのではないだろうか。実はコクトー自身、フロイトに懐疑的なスタンスを取っており、『知られざる者の日記』で次のような言葉を残している。
フロイトに近づくのはやさしい。フロイトの地獄(もしくは煉獄)は、最大多数者の能力につりあっている。わたしたちの探求とは反対に、フロイトは目に見えるものしか求めない。
わたしが考えている闇は、それとは違う。その闇は、宝物を秘めた洞窟である[46]。
この記述を見る限り、『若者と死』に対する精神分析学的な考察は、若者を最大多数者として画一化しているに等しく、コクトーの本意ではないことが読み取れる。するとコクトーは、意識下に置けない混沌とした世界、すなわち無意識にポエジーを見出そうと試みたとしても、神話の主題に関しては、図らずともフロイトに接近してしまったのかもしれない。フロイトも、愛する人を選ぶ「愛の条件」について何千年もの間に詩人たちが語り、「人々を楽しませてきた同じ素材を、科学がもっとずんぐりした手で取り上げ、さほどの快も得られないままこれに取り組むことが避けられなくなる[47]」と言及しているように、両者のテーマが重複することは必然的でもある。フロイトが、詩人たちはこのような課題を解決するのに相応しい特性をいくつか身につけているのであり、「とりわけ、他人の心の隠された蠢き(うごめき)を察知する繊細な感性や、自分自身の無意識的なものを声に出す勇気がそれに当たる[48]」と考えていることを踏襲すると、コクトーは語ることの勇気に死力を注いだのであって、神話のテーマはその表現手段にほかならない。ポエジーは、神話が塗り替えられてこそ、沸き立つと想定される。ちなみにコクトーのエッセイの中でも、一般論による若者の均質化に否定的な彼の態度が見受けられる。例えばコクトーは、彼のもとに若者たちが助言なり活力を求めて、訪問してくる瞬間を「自己を模索する虚無の一部をさいた一夜[49]」だと語るのだが、アンビバレントな存在として彼らを受け止め、悩みを聞いてあげる理由を次のように書き綴っている。
若者たちを神話(myhte)の形式でひとまとめにして考察するのは、滑稽である。それに対して、彼らを恐れたり、彼らとわたしたちの間にテーブルを置いたり、鼻先で扉をぴしゃりと閉めてしまったり、近づいてくるなり逃げ出してしまったりするのも滑稽なのだ[50]。
ネガティヴに描かれるこの神話は、フロイトが意味づけした諸概念を指している可能性が高い。フロイトがヒステリー患者を中心に、人間をひとまとまりに区分したことに対するコクトーの批判的な眼差しが見られるかのようだ。『若者と死』はフロイトに沿って解釈しやすい反面、滑稽さを逆手にとったコクトーなりのアンチテーゼと考えられる。テーブルの記述以降は、『若者と死』の一場面を言語化したも同然である。したがって、『若者と死』は悲劇的な結末としてカタルシスを味わせつつも、観客には風刺やカリカチュアを通し、神話で簡略化せしめることへの滑稽さに気が付かせる狙いもあるのではないだろうか。コクトーの見地からすると、神話が生み出す真実は、嘘にまみれた歴史や社会の趨勢とは根本的に相容れない。フロイトを批判する目的も、神話の理解しやすい上澄みや、われわれの間で簡易的に流布している言説を斬ることにある。青木研二は、コクトーが『詩人の血』にて、本人が吹き込んだナレーションを挿入し、自己批評的な介入行為を繰り返すことで〈否定的とらえ返し〉を行なっていると考えているが[51]、この観点は「『詩人の血』の無意識のパラフレーズ」である『若者と死』にも置き換えられるだろう。精神分析と照らし合わされることは予期していたのだと考えられる。
それでは、フロイトやシュールレアリスムと混同されるリスクを冒してまで、コクトーが「わたし」を描くのは何故だろうか。実を言えば、コクトーは『詩人の血』を制作した当時、シュールレアリスムは存在しておらず、関係性もないと語っているため、本来の彼の関心事は以下の点にあった。
『詩人の血』の時代に、私は無意識を意図的に表現するようなことは避け、むしろ半覚半睡状態に身を置いて、みずからその迷路をさまよっていた。人間の肉体という大きな夜からたちあらわれるイメージの起伏や細部―私はそういうものにしか目を向けていなかった[52]。
コクトーは、明らかに精神分析学的な解釈や価値観とは決別しており、読み取れるのは、身体表現の持ちうる可能性への一途な集中である。その上、『詩人の血』において、夢のメカニズムをコクトーは応用しているがゆえに、「精神をある程度弛緩させ、眠りに似た状態に置くことによって、思い出が結び合わされ、動きまわり、好きなように常軌を逸するがままにまかせる[53]」と綴っている。夢を扱うことで、精神分析学と近づかざるをえないが、それは通俗的なものではなく、むしろラカンが語るような「無意識の領野こそが主体の本拠地[54]」としたフロイト観なのかもしれない。すると、「わたし(moi)」のフィギュールでありうるのは、半覚半睡という夢と目覚めの合間に位置付けることで、「出会い損なわれた現実、いつになっても決して到達されることのない目覚めの中で果てしなく繰り返されるほかない現実へと捧げられたオマージュ[55]」に接近しようと試みた功徳と言えよう。コクトーが「象徴についていえばこれを嫌悪しており[56]」と語る点を考慮に入れても、いわゆる現実を表象する夢を指している訳ではない。詩人が幾度となく死ななければならないのは、夢に包括される現実界の反復であり、定められた「運命」なのだ。
いずれにせよ、コクトーは、夢のメカニスムの研究は「しばしば詩人に、わたしたちの限界を凌駕し、良識を強いられるのとは違う遣り方で世界に適応する手段を与え、さらに理性が命ずる諸要素の秩序を混乱させる方法、つまり、詩をもっと軽やかでもっとすばやくもっと新しい媒体に変える方法を授けた[57]」と明言している。『詩人の血』のパラフレーズの『若者と死』にも夢のメカニスムが使われているとなると、フットライトを飛び越える軽やかさは、夢にあると言っても過言ではない。『若者と死』は、父との「出会い損ない」について思考する「夢」のかたちをとることによって、現実的な領域に回帰するような狙いがあるのだ。『詩人の血』や『オルフェ』を始め、自死がテーマとして繰り返されるのも、一般には巷に流布しているエディプス・コンプレックスとして回収されがちだが、抗い難き「出会い損ない」を反復する宿命に突き動かされたとなれば、フロイトと十把一絡げにされるリスクなど取るに足るまい。
おまけにコクトーにとって、「書くことは、植物や樹々のメカニスムに従うこと、ぼくらの周囲の遠くに精液をまき散らすことである[58]」。すなわち「愛の行為[59]」だ。コクトーの生き様が注ぎ込まれた作品は、読者や観客のもとで受精できる瞬間を今かと待ち侘びているのである。コクトーは、死による再生の主題をあらゆる作品内で語ってきたが、どんなに多作な彼でも蘇生するには、受容者がいなければ元も子もない。もしも、作品に流れ、脈打つ魂に触れた者がいたとしたら、おそらく次のような体験をしたはずだ。
そして、あなたがもうわたしの書いたもの以外何ものにも気を取られなくなるまでになると、あなたは、内部に少しずつわたしが宿り、あなたがわたしを生き返らせているのを感じとるようになるだろう[60]。
コクトーは、差し出した「わたし」を吸収してもらうことで、芸術を自分自身の観点でしか捉えられない制約を越えてほしいと望んでいるに違いない[61]。そのため、読者がコクトーの想像力に誘われるのを期待していようといなかろうと、彼は言葉への受肉を続けるだろう。むしろ「わたし」が提供するものを拒むように要求しているのかもしれない。おそらくコクトーの愛の営みは、彼の死後も『若者と死』を継承して行ったプティのもとで、一つ実を結んでいる。ディアギレフから託された灯火をコクトーは再燃させ、プティの中に息づかせた瞬間が何よりの証拠である。
われわれには、セルジュ・ド・ディアギレフの忘れ得ない不死鳥(フェニックス)の灰しか残されていなかった。しかし人は神話と神話の真実を知っている。不死鳥は生き返るために死んだのだ。(中略)ローラン・プティのまわりに、飛び散った水銀がまた集まり、ふるえ、そしてきらめくひとつの魂を形づくる。
不死鳥は己の本質を見極め、偉大な魂と色とりどりの羽を神秘の炎の中で再生した[62]。
ディアギレフも「わたしの神話」もプティのまわりで再生し、昇華しているのだ。とは言え、コクトーの愛は、プティに更なる愛を要求することだろう[63]。そのため、プティが「わたしの神話」をどのように開き、新たな魂を生み出していくのか、第2部で考えていきたい。

第2部 ローラン・プティの振付を巡って
第1節 エスプリを転がす振付
第一部では、コクトーのプロットを中心に『若者と死』を読み解いてきたが、第二部ではローラン・プティの振付を巡って考察を進めることにする。パラフレーズとなっている『詩人の血』が夢のメカニズムを参考にしていたように、人間の肉体から現れる「イメージの起伏や細部」を捉える方法は、振付に対するアプローチに違いない。コクトーは「『詩人の血』にあって特徴的なのは、なによりもまず、世間が《詩的なもの》と思い込んでいるものへの完全な無関心であり、逆に(詩がそれを使うにせよ使わないにせよ)詩の媒体を作るさいに込められた入念さ[64]」にあると語っているが、『若者と死』の特徴もまた、制作のプロセス、舞台を構成するディテールに収斂するだろう。よって、プティがダンサーの肉体から引き出したイメージを筋書きに乗せて追っていこう。
舞台は、若者の目覚めとともに始まる。タバコをくゆらせ、まどろみながら横たわる若者は、ふと物思いに襲われ、起き上がる。腕時計を見た後、眠っていた身体を起動させるかのように、腰を据え、床を踏みしめる。図らずとも若者の動作はバレエのスタイルを取ることになり、二番ポジション〔膝とつま先を真横に向けた両脚を一足ほど広げて立った状態[65]〕のプリエ〔膝を屈曲させる動き〕の姿勢に入っている。その際、ターン・アウト〔外旋〕とターン・イン〔内旋〕を繰り返すのだが、やがて両足はパラレルな状態の六番ポジションに収まる。ターン・アウトというクラシックバレエの基本的なポジションに準拠しつつ、ターンインする瞬間が垣間見える若者。そんな若者が掻い潜っていくのは、ルイ14世、すなわち王が確立したアカデミーの規範とも言えよう。古典的な脚の外旋に対し、ターン・インが内包する一種の「現代性」との狭間を行き来することで、若者はバレエのスタイルになる以前の「イメージの起伏」を呼び起こすのである。さらにターン・インのモダンな要素が醸し出す「現代性」は、「女」とも引き合うように、若者と娘には、身体的な語彙の呼応が窺える。ドアから高圧的に入り込んできた娘も、まず若者に向き合って行うのは、二番ポジションのプリエだ。同じポジションにて、肉体を動かし始める娘は、案の定若者の「ネガ」である。そして、娘は踊りの節々で脚をターン・インさせ、しなやかなラインを強調するため、プティならではの「ずらし[66]」の洒脱さを身にまとう。ターン・アウトやエポールマン〔腰の位置は変えることなく、上体を捻り、立体的に見せること〕の基本を重んじながら生み出される「ずらし」によって、娘の存在そのものが、「歴史的なものの裡に含み得る詩的なものを、流行の中から取り出す[67]」かのようだ。こうした「現代性」は、ターン・インがターン・アウトの美を逆説的に呼び覚ます暗喩となることをも是認し、『若者と死』において根源にある「バレエ」の価値や枠組みを永遠なものにしてしまう。
また、古典的な技法に沿っているにせよ、二番ポジションも実のところ、あまりクラシカルな作品では使われないパ〔バレエにおける動きの総称〕である。だが、プティは『ノートルダム・ド・パリ』や『ピンク・フロイド・バレエ[68]』といった後期作でも、アン・ファス〔正面〕に向いて二番を行うほど、積極的かつ効果的に活用しており、彼にとって象徴的とも言うべき「ずらし」のポジションだ。本来エポールマンを重んじるバレエにおいて、五番ポジション〔両足を真横に開いた上で、前足の踵が後ろ足のつま先に触れるように重ねたもの〕の方が多用されるのも、左右に交差された身体が、奥行きを自然と生むからだろう。大抵、真正面に身体を使うのは、『ロミオとジュリエット[69]』のジュリエットが睡眠薬を飲んだり、ロミオの死を嘆く時のように、非常に強いエモーションを提示する場合に限る。ある種、エーポルマンに収まっている時が、一般的に綺麗な自分を見せている、社交的な姿だとすると、正面に身体を向けるのは、抑圧された状態を抜け、感情が先立つ内面的な姿だと考えられる。二番ポジションのスクエアな体勢は、感情の強さを全身で表現するのに有効的であり、貴族とは違う大衆的なグルーブへの寄与を促す。このような古典とモダンの相互作用が、プティの萌芽とも言うべき『若者と死』において、半ば先取りする形で現れているため、等身大の若者としての葛藤を観客は目の当たりにできるのである。
こうして「古典とモダン」を往来する、その刹那、若者は過去から現在へさすらうオルフェと重なり合う。娘が逃げ去った後、扉の前で一人たたずむ若者、王女が消え失せた鏡に対して立ち尽くすオルフェ、両者を切り離すことはいまや不可能に等しい。どうしようもなく身悶える若者は、オルフェと同様に「死」に焦がれつつも、生の次元に位置づけている。だからこそ、若者は左という、半身不随のような死の世界とは一定の距離がある[70]。タバコを吸えど、回転するにせよ、多くが右向きに行われるのである。一挙手一投足を抜かりなくコントロールすることで、若者は能動的に生を行使しているとも考えられる。その上、時代が下るにつれ、若者を演ずるダンサーの回転量も多くなるために、生のエネルギーも増大する一方だ。ただ、四番ポジション〔五番ポジションから前足を一足分前方に出したもの〕から始まるピルエット〔両脚で踏みきり、片脚立ちで回転する動き〕の際、ターンアウトされた軸足の摩擦力は、回転と逆向きに働いており、左にこそ原動力があることは忘れてはなるまい。右が優位の世界においても、回転を裏で支えているのがハンデを抱えた左ゆえに、「死」の求心力抜きには、生はおぼつかず、成り立ち得ないと言えよう。よって、若者の取る動作の一つ一つが、何気ない日常に潜む生と死の揺らぎを表象しているのである。「ミモドラム」と称され、習慣化した動作でも舞踊に派生する可能性が生まれた結果、私たちが肉体に向ける視座も変化し行く。バレエが持つような言語の障壁を取り除く特権はそのままに[71]、舞踊という枠組みをも越えられる「ミモドラム」は、私たちの身体から無限のイメージを放出させる。それゆえ『若者と死』は、パの連鎖である「アンシェヌマン」によっては語り尽くせない。むしろ、バレエの規則性から「女」の如く逃れ、若者のように自らを崩壊しにかかる。まさに「破壊という奔出[72]」であるが、これは再生へのしるしにほかならないのだ。
第2節 舞台を彩るメタファー
振付が語るものを媒介として、われわれは肉体に向ける視座の変化を確認してきた。無造作な身振りを眼前に表す「ミモドラム」を通し、日常生活を巣食い、また舞踊へと繋がり得る、ある種の演技を認めることになったはずだ。こうして振付を中心に、われわれの見えている世界が変わり行く過程を捉えてきたわけだが、その変容は、ダンサーのみに集約されるのだろうか。舞台は、なにも若者と娘だけではなく、装置や小道具あってこそ彩られるとも言える。したがって観客が目を留めるのは、「イメージの起伏」によって生み出された「メタファー[73]」なのではないだろうか。するとメタファーには、ダンサーの肉体を経て紡がれるもの、舞台装置をもって成り立つもの、2パターンがあると考えられる。そのため、両者を探ることで、どのようなメタファーが舞台上に現れているのか追求していこう。われわれの眼差しが、いかに誘われるのかメタファーが導いてくれるに違いないからだ。
まず前提として、ダンサーの身体から生まれるメタファーを考察するにあたり、先述の振付と不可分であることは否めない。しかしながら、ここまでは若者と娘が対話の一要素として振付を扱い、相互に作用しあう感情の機微を表現していたのに対し、メタファーたる身体表現は、二者の中には閉じ込められず、外へと向けられている。それゆえ、娘の手のひらで踊らされる若者が踏みにじられ、身を焦がしている時、この「煙草(cigarette )[74]」と化したポーズは観客に差し出されているのだ。本来、娘に蹴り飛ばされ、のけぞる若者の体勢は、日常的な動作、反応と照らし合わせてみても、不自然かつ過剰と言える。重力に逆らい、脚を天井へと突き上げているのも、立ち昇る煙のイメージを模倣したかのようだ。若者は若者でしかないのだが、その存在はやはり擬態化された身体を提示していると考えられる。結果的に観客は、眼前に立ち現れた若者の新たな見かけを傍観してしまうのだ。もちろん、それはプティやコクトーが仕掛けた「罠(piège)[75]」にほかならない。観客はあらかじめ舞台において、若者に夢なかば嗜まれる煙草―若者が「女」と口唇的なコミュニケーションを交わした煙草―を見つめていたではないか。観客は若者の仮相に騙されるべくして騙されているのである。この振付は、コクトーの思惑どおり三度繰り返されることで理解に至るため[76]、知覚のプロセスを追っているに等しい。目に入るだけでなく、見ることで認知が進み、かえって誤解せざるをえないからこそ、コクトーやプティは恣意的に、煙草さながら若者を舞台に放り出すのだ。「メトニミー[77]」とも思しき煙草というメタファーは、こうして若者の世界に溶け込み、観客の目を欺くのである。
なお、若者と娘が向き合い、ぐっと詰め寄るシーンでは、互いに「威嚇[78]」しあい、一対一の攻防が繰り広げられているかのようだ。それゆえ、若者と娘による接近戦に、プティがパ・ド・ドゥに重ね合わがちなテーマの一つ、「闘牛」を見い出せるだろう。『カルメン[79]』ではラストシーンにて、ホセの胸に闘牛のように飛び込むカルメンが描かれているため、若者と「女」との交戦も、一種の見せ物として機能しているに違いない。さらに『スペードの女王[80]』でも、主人公ゲルマンとカードの謎を知る伯爵夫人のパ・ド・ドゥに闘牛のイメージが投じられていることを踏まえれば、闘牛は精神的なゲームの延長戦を見せるのである。堅気で実直なホセ、ゲルマンと、蠱惑的でどこか人間離れしたカルメンと夫人。そもそも「闘牛」は、コクトーやプティのみならず、ピカソ、バタイユ、そしてレリス等の知識人にも愛された主題ゆえ、生に溢れる右、死が匂い立つ左という両極的な相貌を介し眺めることもできるだろう[81]。よって、闘牛のメタファーは、内なる若者の情動の揺らぎをも儀式化し、観客の眼差しに呈することを可能にしてしまうのである。
若者の肉体に新たな様相が垣間見えることで、パリの一角にスペインの空気が吹き抜けているが、その風を呼び覚ます要因たるメタファーは、意外にも身近で換喩的と言えるだろう。何の気無しに手に取るような煙草を見ても、メタファーは日常生活を支える事物と地続きな側面がある。だからこそ、小道具や装置にもメタファーが掛け合わされ、ダンサーと寸分違わず舞台に彩りを添えているのである。その中でも、ダンサーと密接に関わり、振付の一部として組み込まれる「椅子」は、見るものを惹きつけてやまない。なぜなら、若者が娘を待ち望みつつ、たった一人の空間で手に取り、孤独な時間をカバーする椅子は、見せ物の一部として祭り上げられているからだ。椅子を片手にアラベスク〔片脚立ちの状態で、もう片方の脚を後方に伸ばすポーズ〕し、プロムナード〔一定のポーズを保持しながら、軸脚の爪先を支点に、足を床につけたまま回転すること〕する時、額面どおり、若者は「女」と脚を絡ませ、ともに散歩しているのであろう。ふと思い立ち、蹴り飛ばす瞬間には、受動的な若者に備わる、能動的かつ暴力的とも思しきサディズムが見受けられ、両義性のあるアンビバレントな姿が前景化しているのかもしれない。
ちなみに、余白を埋め合わせるような椅子の使い方は、特段プティに限定されてはいない。時代を下れば、ピナ・バウシュが『カフェ・ミュラー』にて何十脚もの椅子の中でのダンスを繰り広げている。もちろん、こうした傾向は同時代に活躍した振付家モーリス・ベジャールの作品にもすでに認められている。それは不条理演劇の妙手イヨネスコの戯曲に振付した、『椅子』である。内容としては長年寄り添ってきた老夫婦が、夢想し、踊り、やっとの思いを口にする、いわば演劇要素の強い舞台なのだが、題名そのままに、二人だけの世界の背後に立ち並ぶ、膨大な椅子が何にも増して特徴的だ。誰も老夫婦のもとを訪れないにもかかわらず、彼らはただひたすら椅子を動かし回り、舞台に独特の喧騒感を生み出している。プティの『カルメン』にせよ、酒屋の鬱蒼とした雰囲気は、やはり数多くの椅子が生じさせる人混みの錯覚にあると言っても過言ではない。加えて、『カルメン』の場合、ミュージカル『キャバレー』や『シカゴ』における印象的な椅子のダンスをも先取りできるがゆえに、放たれる猥雑さや世俗性の中に、生暖かい体温すら感じられよう。『スペードの女王』では、賭博場に来る者の緊迫感を伝え、足枷になる振付も散見されることから、その座からこき下ろす敵にも変化している。このように多義的なメタファーたる椅子は、実はプティ自身も「演技者[82]」に相当すると太鼓判を押すほど、特別視されているものである。ダンサーと同等に、もしくはそれ以上に存在感を出すのは、当然の成り行きであったのだ。いまや椅子に、誰かがしばらく腰を休めていた気配、もしくは新たに座るものを待望する期待感すら感じられるのではないだろうか。われわれが椅子に見るのは、人間の残像、痕跡、ほかならぬ不在なのだ。
そして、もう一つ不自然ながら、若者の部屋に溶け込んでいるものがある。若者のベッドにかけて天井から垂れ下がる赤い布である。コクトーの『恐るべき子供たち』の観点からすると、赤い布は、浮世離れした子供たちの舞台の幕に相当し、知性介入以前の世界の幕開けを意味していると考えられる[83]。子供たちとは知性が関与せず、布切れを「直視[84]」できるため、この世に囚われることを知らない存在だ。そのような子供たちの世界を覗き見することを許された観客は、「異化」を促される。ボードレールもダニエル・アラスも語るとおり、幼年期の眼差しは、言語以前に位置付け、想像によって支えられており、断絶も切断もない、流動的なものである[85]。このまなざしに観客も突き動かされるとなれば、『若者と死』も多分に漏れず「傑作」になり得るだろう。
さらに次のように―見るように促されるあまり、傑作から溢れる赤い布という共通点から、フラゴナールの《閂》を見るように誘惑されていると―解釈することも可能であろう。そのため、赤い布地をアラスと同じく男根のメタファーとして見てしまうことはやむを得ないだろう。とは言え、メタファーを見るも見ないも観者の勝手であり、赤い布は実際「何でもないもの[86]」だ。逆説的になるが、布は舞台の端にずっと潜んでいるも、名付け難く、われわれから常に逃れ去る「名付けられないもの[87]」だからこそ、欲望の対象であり続けているとも言える。すなわち、絵画のように、『若者と死』の舞台も「名付けられないもの」に属し、言葉にできるものの向こう側で、機能しているに違いない。たとえ、赤い布地の、ある種のヴェールの向こうに隠されたもの見ようとしても、おそらく何もないだろう。ゼウキシスと同じく騙されたことが明らかになるだけだ。まさに神話や寓話に閉じ込められていた逸話を開くかのように、彼らの反復を行ってしまうのである。しかしながら、「見かけ[88]」に騙されていることに気がついた時、それは、われわれが改めて見ることの欲望を知る時でもある。画家の若者が生じさせ、「わたし(moi)」とも語られる傑作は、観客をイリュージョンへと誘っていたのだ。『若者と死』とは、『ノートルダム・ド・パリ』や『プルースト[89]』に先駆けた、絵(タブロー)なのではないだろうか。

第3節 偶然性の戯れ
若者の人生のワンシーンを切り取った、屋根裏部屋という舞台は、「何でもないもの」に満ち、換喩的に働くメタファーをわれわれの眼前に広げていた。観客は、目の前に溢れるものを見るようにそそのかされ、舞台と対峙せざるを得なかっただろう。密室での男女の駆け引き、転がる椅子、そしてベッドに覆い被さる赤い布。フラゴナールの魅惑にも突き動かされる舞台は、まさに絵と化していた。だが、それは『若者と死』の一面にすぎない。舞台は上演時のみ立ち現れ、絵画のように、物理的に同一の状態が保持されることはないため、両者の性質には相違がある。与えられた振付に変更点がなかろうと、昨日と今日の公演が寸分違わず同じになることはありえない。どんなに綿密な計画、準備が行われたとしても、舞台には偶然の産物が付きものなのだ。元より、『若者と死』は「偶発的な同時性の神秘(le mystère du synchronisme accidentel)[90]」としてコクトーによる使用する音楽の実験が繰り広げられたことを忘れてはなるまい。バビレやフィリッパールは、半ば即興で踊ることを余儀なくされていた。それゆえ、偶然性に導かれながら到達できる作品の境地を見届けることこそ、『若者と死』の根幹と言えるだろう。コクトーの独自性が光るバッハへのアプローチを中心に、偶然性が作品にもたらした神秘を探ってみよう。
『若者と死』の偶然性の特殊な点は、前述どおり、ジャズからクラシックへの差し替え、いわば音楽の置換にある。レアケースなだけに、やはりダンサーには混乱を生じさせたようだ。リハーサルも進んでいた分、ダンサーはジャズのリズムを染み込ませ、習慣化された身体を作り上げていたと考えられる。見かねたプティは音楽を一種のBGMとして捉えることを助言したのだが、これは困惑の大きさを物語る提案と言えよう。こうして前代未聞な実験は幕を開けたものの、皆の心配をよそに、本番では振付と音楽が見事に一つにまとまり、成功を収める。緊張感と張り詰めた空気に包まれたことで、若者の感情の機微、「イメージの起伏」を包含する振付が、音楽と急速に接近し、一体化したのだろう。そもそも音楽は、次々と音が流れ去るような流動的な性格を有するがゆえに、振付と照らし合わせ、いまここを掴み取ろうとすればするほど、われわれの現存性に語りかけてくる。「自我への親近性[91]」を持ち、心の動きや感情に照応する音楽は、バビレと若者の脈動が重なり合うよう促したのではないだろうか。バビレが、「若者は私自身であった[92]」と語っていることを踏まえると、差し迫る状況、重厚な音楽が、彼の直観に働きかけ、若者の内部に滑り込む「罠」を作り出したと考えられる。バッハの荘厳なリズムは、夢にうつつを抜かす若者と、バビレを繋ぎ止める。つまり、リズムに乗ることは、言葉や知性に絡め取られた身体を解き放ち、幼少期の世界への退行を可能にするのである。それは、子供たち特有の「遊戯[93]」にも似ているかもしれない。「遊戯」が神聖さを帯びていたように、詩人のもとで舞踊と音楽が結びつくとなれば、『若者と死』にも古代ギリシャより流れる神秘や霊感を見出せる。「偶発的な同時性の神秘」は、ジャズからクラシックへ移り行くリズムを介し、ダンサーや観客を芸術の根源的な次元にも引き合わせてしまうのだ。
ちなみにジャズと言えば、特徴の一つに即興の演奏が挙げられ、偶然性の要素を多分に含んだジャンルの音楽である。クラシックは演奏家と作曲家が離れ始めたロマン主義以降、本家に追従することも多く、バッハならばバッハらしい演奏が求められる傾向にあり、その歴史性や宗教性を鑑みた上での表現が重要視されやすい。もちろん、バッハ本人は即興で演奏を行なっていたり、ジャック・ルーシェのようにバッハをジャズにアレンジする音楽家もいるだけに、例外もある。ゆえに一概には語り得ないが、音楽の置換によって、言ってみれば卑近なジャズのリズムに潜む崇高性、バッハの音楽に隠れる世俗性が引き出され、相互作用が生じたと考えられる。なおかつ、バッハは、メンデルスゾーンの功績にて再び日の目を見たため、コクトーが語るような死と再生の観念にも呼応している。プティ以降もバッハは、ジョン・ノイマイヤー、ウィリアム・フォーサイス、ハインツ・シュペルリを筆頭に作品の核を担う音楽として、名だたる振付家に重宝されているが、時代を超越し得るだけあって、コンテンポラリーとも相性が良い[94]。モダンな色にも染まれ、色褪せることを知らないバッハだからこそ、ノイマイヤーは彼の特異性を語るために、以下の時代錯誤的な表現をも厭わなかったようだ。
たとえば、美術館で十七世紀の絵を見て、とても好ましく思い、その時代を感じる。しかし、バッハはそうした時代に属するものとは思えません。私にとって、バッハは常に「いま」なのです。こうした作曲家はほかに考えられません[95]。
バッハの音楽が、時代に囚われないアナクロニックな作用を持つとなれば、取り替えられた一音一音に耳をすます度に、バビレは「いま」を感じていた可能性がある。バビレが若者自身と見まごうような感覚に陥ったのも、バッハを介して「いま」を生きた結果かもしれない。
少なからず振付と結びつき、絵とも引き合うバッハの音楽は、『若者と死』の世界に一同に会する諸芸術を繋ぎ止める絆となっているのである。あらゆる芸術を陰ながら操作していても痕跡を残さない音楽は、ミシェル・セールからすると、神話の様相すら帯びてくるようだ。
エウリディケがオルペウスのはるか後ろからついてくるように、あるいはまた像に変えられた女の背後のロトの家族のように、あるいは振り向いたオルペウスや、塩の柱の後で爆発する地獄や、火をかけられたソドムのように、音楽はすべての[芸術の]背後にあり、すべてのなかに実際にありながら、すべてからは知られず、それらに運動と生命を、精神と火をあたえていながら、だれも音楽には近づけないのです[96]。
オルフェとも共鳴する音楽は、コクトーに向けて、「わたしの神話」を見るよう密かに誘っていたに違いない。おまけに、ひとえに音楽と言えど、選ばれたのはバッハの「パッサカリアとフーガ」である。「バッハの時代に形をととのえたフーガ形式は、ある種の神話、つまり二人の人物ないし二群の人物が登場するような神話の進み方に驚くほどそっくりそのまま[97]」なため、一連の運動に見事に火をつけているのだ。厳密には「フーガ」を抜いた「パッサカリア」のみの構成だが、変奏曲の事実は変わらず、主題は繰り返し、逃げ去り、追いかけられる。それゆえ、物語の展開も「遁走曲」と溶け合い、若者がどんなに欲しようと、永遠に近づくことができない「女」が浮かび上がるのである。
さて「女」が逃げて行った先に、実は「音楽」固有の偶然性とは異なるもう一つの偶然性がわれわれを待ち受けていることを付言しておかなければならない。それはむしろ第2節で、すでに触れた舞台装置や小道具の主題系に連なるものなのだが、偶発的な神秘を見届けるためには―若者の背後を照らしだすエッフェル塔を―振り返らなければならないのだ。このエッフェル塔、当初から予定されていた舞台装置ではなく、マレーネ・ディートリッヒの映画撮影の終了に応じて、たまたまプティらに引き渡され、急遽取り入れられることになった僥倖の証なのだ。エッフェル塔という特権的なオブジェ抜きには、屋根裏部屋という閉ざされた夢想空間から、パリの夜へと観客が誘いだされることもないだろう。コクトーと同じ年に誕生したエッフェル塔は、「いま」や「現代性」を作品に送り込むエッセンスとして働いているのである。そして、あまりに象徴的で、幾つもの移ろいやすいメタファーを作るエッフェル塔は、バルト曰く「パリを見守る女性、足下に身をよせるパリをいたわる女性[98]」にほかならない。さらに、塔が自殺の名所でもあることに関して、バルトは「エッフェル塔が、純粋な見世物であり、絶対的な象徴であり、無限の隠喩であるからこそ、人々はここで死ぬ[99]」のだと結論づけている。「現代性」、「女」、「死」という数々の象徴は、エッフェル塔に向かって統合され行くように、「人々はエッフェル塔というつきることのない象徴をとおして、人間の限界とたわむれはじめたのである[100]」。偶然性の戯れは、われわれを限りある世の中から解放してくれる。そのかわり観客は「わたし(moi)」や「神話(mythes)」の生き証人になることを余儀なくされるのである。「わたし(moi)」を媒介に幼少期に立ち返れるも、曖昧な「女」に近づくにつれ、エディプス的な空想なり根源的な問題提起を繰り返すように迫られるのは、われわれにとって止むをえないのである[101]。

第4節 若者の中に、若者以上のものを
眼差しを貫く振付、その目を癒すメタファー、全ての背後に潜みながら心を打ち震わせる音楽。いまやわれわれは、『若者と死』の世界における諸芸術の戯れの目撃者になろうとしている。コクトーと同じく、舞台に現れる神話を認めつつあるのだ。そのため、音楽に誘われ、揃い始めたピースも、残り一つとなった。最後の中心部分を埋めるのは、舞台を燦然と輝くダンサーである。そもそも、「第二のニジンスキー」と名高いバビレの初演から、決して精彩を失うことなく『若者と死』が踊り継がれてきたのは、先駆者を乗り越えるようなスターが誕生し続ける、奇跡に支えられていると言っても過言ではない。踏襲と刷新が繰り返され、生き抜いてきた若者は、バレエの変遷に何度も立ち会い、ルドルフ・ヌレエフやミハイル・バリシニコフといったスターを神話の語り部に所望してきたほどだ。このようにバレエ史に君臨する若者だが、一体われわれにとって、またダンサーにとって、いかなる存在なのだろうか。プティにおいても革新的な作品ゆえ、観客、ダンサー、振付師のあらゆる視点に着眼しながら、若者の姿を見つめ直したい。
沢山のスターが己の持ち味を生かしたことで、築き上げられてきた数多の若者像。バラエティに富んだ若者について語るには、前提としてプティの振付の特色を踏まえておく必要がある。たとえば、プティにとって極めて例外的な『若者と死』を除けば、本来、彼が目指しているは「動きと音楽の一致[102]」である。音楽と身体が連動しあうことに重きを置く以上、プティは、ダンサーに自身が織りなす振付への忠実さを求めて止まない。実際に、彼のミューズの一人、アレッサンドラ・フェリは、プティの作品に関して、感情は本物であっても、常に完璧なスタイルを介して踊り、振付の中から自由を見出さなければならないと証言している[103]。フェリの言葉を借りるなら、プティのバレエには、情熱的に踊るための感情の豊かさ、やりすぎを未然に防ぐような精確さ、両者のバランスの保持に難しさがあるのだ。ちなみに、フェリがこの際、プティと対照的なコリオグラファーとして掲げるのが、ケネス・マクミランである。マクミランの振付は、フェリ曰くダンサーに向けてあえて余白を残す特徴があるようだ。東京バレエ団を設立した佐々木忠次にせよ、マクミランの凄さは「ダンサーが解釈できる余地を最大限に残していること[104]」だと綴っている。ゆえに、同じジュリエットを演じても、シルヴィ・ギエムとフェリとでは全く異なって見え、観客を常に楽しませることができるのだと佐々木は続ける。佐々木が「上演されつづけるバレエはダンサーを重視したバレエだ[105]」と結論づけていることを鑑みると、マクミランに比べてプティ作品の上演が伸び悩む理由は、需要と供給の食い違いにあるのだろう。ニコラ・ル・リッシュが、「ダンスの父のような存在(comme un parrain de la danse)[106]」と称しているとおり、一種の権威となっていたかもしれない。その点、『若者と死』は、プティのスタイルに則るも、特殊な音楽使用を始め、ダンサーを重んじる傾向が強い作品である。確固たるロジックを加味しながら、個性的な表現を可能にする『若者と死』は、ダンスを止揚の方向へと駆り立てていると言える。奔出による破壊と統合を促す作品ゆえに、他作品が追いつけぬほどのスター性を若者は生み出し得るのである。
だからこそ、ダンサーの存在感、独自性を光らせる若者は、スターから大切に守られてきたのだろう。止まることを知らない回転、重力を感じさせない跳躍、あまりにアクロバティックな振付は、ニジンスキーの伝説を引き継ぐかのようにバビレより受け渡される。流動的な舞台芸術であれど、その伝説ばかりは、消え去ることを知らない。事実、スペインの振付家オルガ・デ・ソトは、初演に立ち会った観客へのインタビューを通し、記憶を追求するプロジェクト『歴史[107]』(histoire(s), 2004)を行っているが、バビレのダイナミックなダンスについて言及する者が多かった。作品を飾る随所のディテールは、個々に記憶が分散されており、娘の黄色いドレスを赤もしくは黒だったと誤認している観客もいたが、若者の技術面への思い出の集中は疑う余地がない。何十年も経ち、個人の解釈や思い入れが介在する中で、鮮烈に記憶に残っている技巧的なバビレは、ともすればヴィルトゥオーゾのようでもある。他の追随を許さないパフォーマンスならびに自己アピール力は、作品内の諸芸術の要素を凌駕するも、結果的には作品を豊かにする方向へと働く。コクトーの思い描く神話を実現するためにも、ダンサーの個性が尊重されてしかるべき作品なのだ。
このような若者の特異な煌めきを最も生かしたのは、恐らくミハイル・バリシニコフだろう。彼は主演を務める映画『ホワイトナイツ』の冒頭を『若者と死』で飾っている。その上『ホワイトナイツ』は、ソ連から亡命する世界的なダンサーを主人公に、表現の自由、愛する者と生きる権利を求めて戦う映画ゆえ、幕開けを担う『若者と死』に込められたメッセージ性の強さが窺える。社会や組織が優先され、個人的な表現を統制していたソ連では、モダンダンスさえ禁止の対象にあったことを念頭に置くと、相反する『若者と死』は、民主主義的な自由を香らせているとも考えられる。また、バリシニコフ本人が主人公同様、亡命していたため、「わたし(moi)」を表象する若者は、作品を越えて個人の尊厳を主張するダンサーの声を轟かせているはずだ。なお『ホワイトナイツ』には、バレエだけでなく、準主役のグレゴリー・ハインズのお家芸たるタップが何度も挿入されており、後にハリウッド進出し、ジャズやタップも愛したプティと80年代アメリカは、根本的に波長が合うのかもしれない。「フランキー&ジョニー」で踊られていた時点で、『若者と死』には、アメリカの気風が流れるよう運命づけられていたとも見込まれる。やはり、『若者と死』は、プロパガンダとは一線を画する、ダンサーのための作品なのだ。
しかしながら、『ホワイトナイツ』にも、映画、いわば「マス・メディア[108]」としての多大な影響力、ある種の幻想を引き起こす可能性が潜んではいないだろうか。アメリカン・ドリーム、そして何よりもスターの憧憬を脳裏に刻み込むよう促されていると考えてしかるべきではないのか。たしかに、われわれは、バリシニコフの若者を見つめる時、明らかに眼差しを誘導されている。あらゆるカメラを駆使しつつ、時に脚元や顔の表情のみを切り取る撮影は、見ることのできる範囲を予め操作し、われわれを恣意的な視座に立たせているに等しい。舞台を眺めるような引きでのショットを減らし、映画の一場面の如く機能しているのは、ダンスのために演技が中断されることを拒む監督の意図によるものである。それゆえ、この『若者と死』においては、映画の流れを汲むべく短縮化され、カットされる振付も存在しているが、作為的な修正はかえって、バリシニコフの躍動感溢れるダンスの濃度が増すように上手く機能したと思われる。代表的な娘に3回蹴られる場面にしても、尺の関係で1回に減少しているが、バリシニコフは、映像に残るダンサーの誰よりも掲げた脚をゆっくりと降ろしており、桁外れの身体能力を見せつけている。そして短い時間に詰め込まれる分、俊敏なジャンプ、スピードが充溢した回転も目立っており、バリシニコフが若者の伝説に更なる弾みをつけたことは間違いない。熊川哲也の『若者と死』を見ても、クローズアップを積極的に行う撮影や、切れ味鋭いダンスの端々に『ホワイトナイツ』のバリシニコフが想起される。
ちなみに、次世代のダンサーを飲み込むほどの影響力は、熊川哲也のように視覚的に確認できないパターンもある。バンジャマン・ペッシュが好例で、彼の場合、『ホワイトナイツ』がダンサーを志すきっかけとなっている。だからこそ、『アルルの女[109]』、『ノートルダム・ド・パリ』といった名だたる作品を演じてきたペッシュだが、プティに踊るべきだと告げられても、『若者と死』だけは八歳当時の記憶と感動が変わってしまうことを恐れ、踊らない決断を下している[110]。そんなペッシュに対して、他方ではステファン・ビュリオンのように、背の高さが原因で、若者を踊ることをすぐには許されなかったケースもある[111]。彼は交渉し、練習の成果を見事示したことで、役を掴み取るが、いかに若者に対する欲望が三者三様なものか読み取れるだろう。とは言え、若者を欲望するビュリオンも、欲望することを欲しない、すなわち「欲望しないことを欲する[112]」ペッシュも、結局は根本の部分が変わらない。つまり、プティは、この両者が出会うところで待ち受けているのである。ニコラ・ル・リッシュが、プティと「真の共犯関係(une vraie complicité)[113]」にあったと語っていることを考慮しても、ダンサーが常に主体的でいられるよう導いていると推測される。プティはダンサーに応じて、若者の振付を適宜調節していたが、彼らを自分自身と向き合わせるための策略だったとすら考えられる。それだけに、ダンサーからも、観客からも若者は愛され続けるのだ。つまるところ、われわれが若者の中に愛しているのは、若者以上のものなのかもしれない[114]。
結
観客と作品とが触れ合った瞬間は、束の間とは言え、わたしたちと他人とを隔てる空間を消滅させることも言い添えておこう[115]。
ここまでわれわれは、プロットや振付を介し、『若者と死』から立ち上がる「神話(mythes)」を多面的に追い続けてきた。第一部では、まず二項対立で語られる題名を通し、パ・ド・ドゥによって綴られる『若者と死』の世界が、プティおよびコクトーの共通テーマ—翻弄される男と魅惑的な美女の構図―を皮切りとした、あらゆる二元論に置換できることを確認した。その次には、エヴリディケの如く逃げ去る「女」に処女性や現代性、そして「死」を認めることで「神話」への引き金を捉えたのだった。だが、若者に接近する死の影が、むしろ再生の兆しとなることも見てきただろう。われわれは、入念にプロットを読み解きながら、表面的では無い、内面的な「神話」への接近を試みてきたのである。
第二部では、紐解いた筋書きを踏まえつつ、振付、装飾、音楽、ダンサーにスポットを幾度となく切り替え、舞台上で具現化され行く「神話」に、様々な角度から光を照らしてきたのであった。たとえば、クラシック・バレエの伝統を重んじるも、現代性に繋がるモダンなエッセンスを多分に含み、やがては逸脱していくプティの振付は、オルフェのような境界線の突破を可能にしていたはずだ。時には、屋根裏部屋に潜むメタファーをも体現するダンサーの肉体は、観客の眼差しを突き動かしつつ、幼少期へと誘う「罠」として機能していた。また、美術や舞踊といった数々の芸術が集まる舞台の背後で、鳴り響くバッハの音色は、立ち会う者の感情に照応し、ついには、われわれの現存性にまで訴えかけてきただろう。バビレに至っては若者と一体化する感覚を抱くほど、動きと音楽が見事な絆で結ばれていた。それゆえ、ミハイル・バリシニコフやニコラ・ル・リッシュなど数多のスターにも愛されることになった若者は、風化せず、後世へと引き継がれ、時代を超越していくのである。このように複数の要素が交錯し、無限に広がることで、四方から知覚に働きかける「神話」は、ある意味では、観る主体の想像力を掻き立てる「寓話(fable)」に収斂するとも言える。最終的には、イマジネーションの起源であり、ミュトスたる「寓話」は、「わたし(moi)」へと導き、結果的にコクトーの面影をも浮かび上がらせるのだった。
こうして「わたし」へと回帰する時、それは、あの「愛の行為」に至る瞬間でもある。コクトーの息遣いをそばで感じ、彼がゆっくりと、観客の内部に宿り始めるがゆえに、前述の引用の如く、他人とを隔てる障壁は崩れ去るのだ。あまりに奇跡的な一時に、コクトーはさらなる言葉をこぼす。
こうした現象は、最も反発しあう電気を一つの尖端に集め、慇懃なしきたりだけが、吐き気を催させるような人間の孤独を誤魔化してくれるこの現実世界で、わたしたちが生きてゆくのを可能にしてくれる[116]。
つまり、その営みは、孤独な深淵に生きるわれわれを救い出してくれる頼みの綱でもあったのだ。そもそも本稿ではあまり触れてこなかったが、『若者と死』は、実存に関する問題提起と密接に関連していることは疑い得ない[117]。『若者と死』の題名が孕む「生と死」のテーマは、他者との対峙、自殺の意義など、一つの時代性を反映しているのである。
おまけに、タイトルに「男と女」を見出すならば、ジェンダーに関する問いかけも生じてくる。若者を弄ぶ娘にはスポーティーで、媚びない強さがあったように、プティは時代に先駆けて、常に解放的で自立した女性をヒロインに設定している。ファム・ファタルの代名詞である『カルメン』にせよ、プティは「髪を短く切り、様子を一変し、男でも女でもない無セックスなもの、鬼のようなもの、新しい存在になることを提案[118]」し、神話より通ずる典型的なイメージの刷新に挑んでいる。まるで「女」など存在しないかのようだが、固定観念から抜け出でることにこそ、プティの趣があっただろう。要するに、そんなプティの世界に誘われることで、われわれは、自らの実存やセクシュアリティを再考するよう促されるのである。
したがって、「わたし」と一括りに言っても、コクトー本人やプティの精神を指すばかりでなく、やがてはわれわれ自身に辿り着き、己の欲望と向き合うことにも通じて行く。大戦後の殺伐とした世界だからこそ、観客と作品がともに脈打ち、われわれが一つになれることが、より一層甘美に描かれる。もちろん、それは束の間の蜃気楼、幻想かもしれない[119]。だがたとえ、うたかたの愛であろうとも、われわれはその刹那を求め、アンコールし続けるだろう。
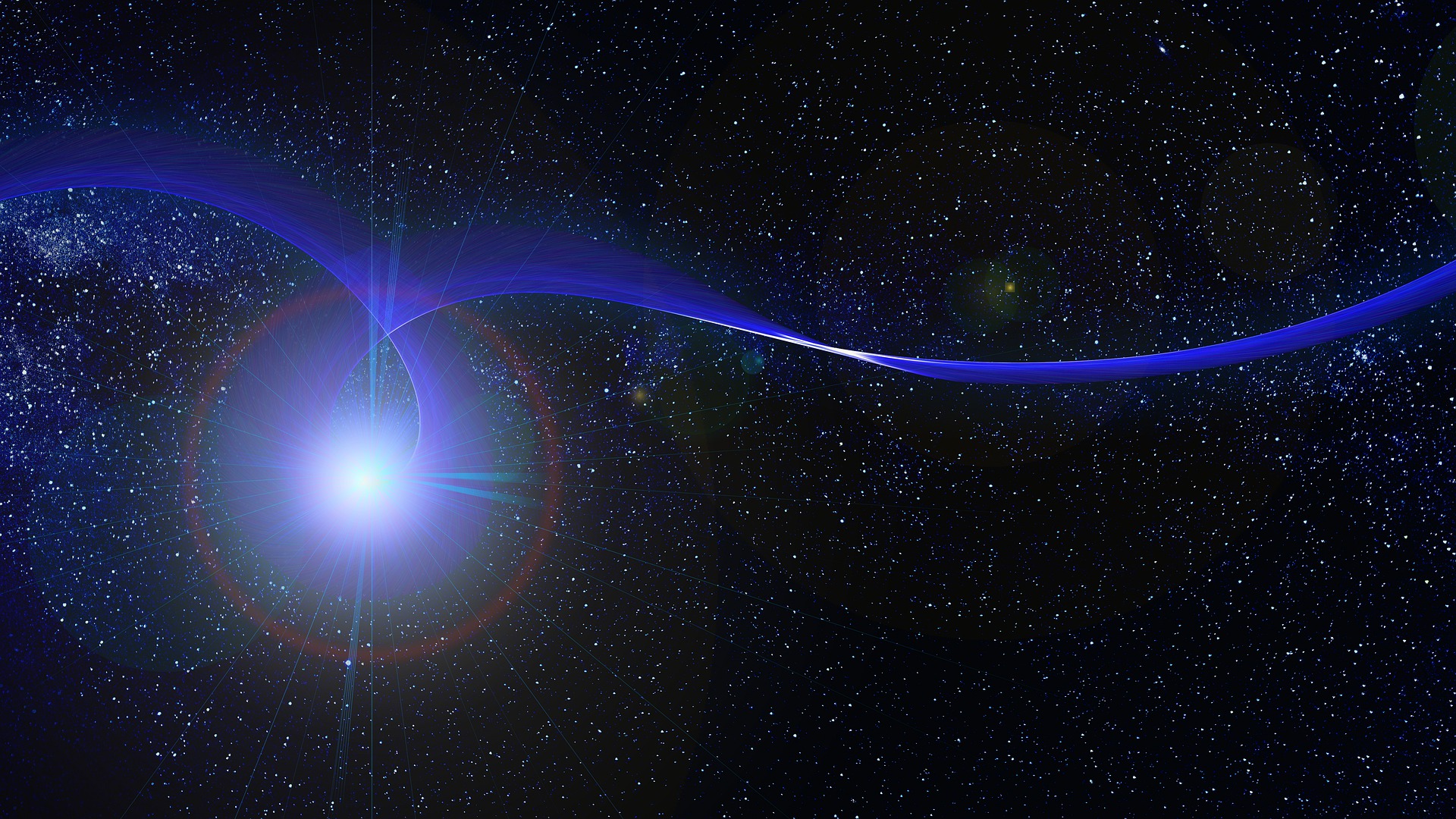
***********************
注
[1] 本稿は2021年12月15日に立教大学文学部に提出され、2022年1月28日に審査を受けた卒業論文に加筆修正を施したものである。
[2] Jean Cocteau, La difficulté d'être, Paris, Union Generale d'Editions, 1957, p. 168. « Du reste, la beauté du spectacle saute la rampe, quoi qu'il advienne, et l'atmosphère générale est une figure de moi, de ma fable, de mes mythes, une paraphrase involontaire du Sang d'un poète. »本稿では日本語訳は既訳(ジャン・コクトー、『ぼく自身あるいは困難な存在』、秋山和夫訳、筑摩書房、1991)をベースに、適宜参照し、改変を行う。
[3] 本稿では「寓話(fable)」を次のような意味で用いる。« Récit, le plus souvent symbolique, dans lequel l'imagination intervient pour une grande part. »( https://www.cnrtl.fr/definition/fableより引用 )
[4] 本稿では「ミモドラム(mimodrame)」を次のような意味で用いる。« Pièce représentée sous forme de pantomime, dans laquelle les moyens d'expression sont les gestes, la mimique, la danse et l'accompagnement musical à l'exclusion de toute parole. »(https://www.cnrtl.fr/definition/mimodrameを参考)。それゆえ『若者と死』は単なるバレエではない。コクトー曰く、「ミモドラム」なのだ。Ibid., p. 169. « C'est un mimodrame où la pantomime exagère son style jusqu'à celui de la danse. »
[5] 『若者と死』は当初、観客にはバレエとして発表されており、コクトーが「ミモドラム」と断定するのは、後のエッセイにて回想するまで待たなければならなかった。この曖昧さが議論を引き起こし、時に「論争のバレエ(ballet litigieux)」と表現されるほどであるために、バレエそのものには焦点を当て難い。Franco, Susanne. « Imaginaires dansés à partir de Jean Cocteau. Le Jeune homme et la Mort entre histoire, mémoire et loi, in Pas de Mots. » De la littérature à la danse, Paris, Hermann, sous la direction de Laura Colombo et Stefano Genetti, Paris, Hermann, 2010, pp. 217-237.
[6] Sulcas, Roslyn, “Roland Petit: A French Choreographer, Most Savored in France.” 2021, The New York Times 17.
https://www.nytimes.com/2021/05/26/arts/dance/roland-petit-paris-opera-ballet.html
[7] コクトーは、神話に包含される嘘に現実は混ざっていないが、歴史には現実と嘘が混同していると考えており、「『歴史』の現実は噓になるが、作り話の非現実は真実になる」と語っている。それゆえ、神話に嘘はありえないのだと結論付けている。コクトー、『ジャン・コクトー全集Ⅵ』(堀口大學・佐藤朔監修)、東京創元社、1985、332頁。(翻訳は文意に合わせ修正した)。なお、フランス語原文は以下の通り。
Jean Cocteau, JOURNAL D’UN INCONNU, Bernard Grasset, Paris, 1953, p. 143. « Le réel de l’Histoire devient un mensonge. L’irréel de la fable devient vérité. » Nous soulignons.
[8] 本稿では、振付をメインに論じるに伴い、『若者と死』の映像資料のベースとしては、劇場で実際に収録されているという理由から、ローラン・プティ振付、『カルメン/若者と死』(2005年収録)、ニコラ・ル・リッシュ、マリ=アニエス・ジロー出演、パリ・オペラ座バレエ団、(ディアゴスティーニ・ジャパン発行、隔週刊バレエDVDコレクション第19号)を参考にした。
[9] 舞踊学を専門とする深澤南土実は、バレエ・デ・シャンゼリゼの活動に対して、「パリ解放直後の街の現実や雰囲気をそのまま作品=舞台に表象させた《旅芸人》,《ランデヴー》,《若者と死》などは,戦後直後の時代の空気を観客とともに共有し,バレエに新たな精神を吹き込み,新しいバレエの里程標となった」と考察している。深澤南土実、「バレエ・デ・シャンゼリゼの軌跡」、『舞踊學』、2014、第37号。
[10] Cocteau, op.cit., p. 162. « M. Babilée, chez lequel je retrouve bien des ressorts de Waslav Nijinsky. »
[11] 高橋洋一、『ジャン・コクトー—幻視芸術の魔術師―』、講談社、1995、169頁。
[12] 同上、169-173頁を参考。
[13] Cocteau, op.cit., pp. 161-162. « j’envisageai comme possible une scène de danse où les artistes étudieraient sur des rythmes de jazz, où ces rythmes seraient considérés comme de simples instruments de travail et céderaient ensuite la place à quelque grande œuvre de Mozart, de Schubert ou de Bach. »
[14] 高橋、前掲書、1995、176頁。
[15] コクトーはエッセイ『ぼく自身あるいは困難な存在』の「死について」という章で、多くの人が死をつらく考えていることに驚きを覚えている。Cocteau, op.cit., p. 90. « Sur le chapitre de la mort, il me reste beaucoup à dire, et je m’étonne que tant de gens s’en affectent puisqu’elle est nous chaque seconde et qu’ils devraient la prendre en résignation. »
[16] Ibid., p. 90. « On s’est habitué à en faire une fable et à la juger du dehors. […]Chacun loge sa mort et se rassure par ce qu’il en invente, à savoir qu’elle est une figure allégorique n’apparaissant qu’au dernier acte. » Nous soulignons.
[17] Ibid., p. 91. « Elle〔la mort〕est notre jeunesse. »
[18] 『神話と意味』の序論で、ウェンディ・ドニジャーは「神話はすべて、自然が与える混沌たる事実に知的意味を与えようとする弁証法の試みであるとし、またこの試みは、不可避的に人間の想像力を二項対立の網にとらえてしまう[] 」ものだと説明している。クロード・レヴィ=ストロース、『神話と意味』(大橋保夫訳)、みすず書房、1996、2-3頁。
[19] ちなみにコクトーは「映画における驚異について」という章で、モンテーニュの『エセー』内にある次のような言葉を肯定的に引用している。Cocteau, op.cit., p. 53. « La plupart des fables d'Esope ont plusieurs sens et intelligences. Ceux qui les mythologisent en choisissent quelque visage qui cadre bien à la fable ; mais, pour la plupart, ce n'est que le premier visage et superficiel, et il y en a d'autres, plus vifs, plus essentiels et internes, auxquels ils n'ont su pénétrer. » Nous soulignons.
[20] 数多の思想家がこの問題を論じているが、例えばジョルジュ・バタイユは、このような激しい嫌悪を覚える本質的な意味として次のように述べている。「何ものにも従属しない意志、肉体が生れ出た局部の忌避、死ぬという事実への根源的な反抗、肉体に対する、言いかえれば、われわれにあって偶然に生来備わりいずれは滅びゆくべきものに対する一般的な警戒心―こうしたものこそ、汚物や性的機能や死とは無関係なものとして人間を描くようわれわれを仕向ける衝動が、われわれ各人にとって担っている意味であろうと思われる」(バタイユ自身による強調)。ちなみに、本稿でバタイユを参考にし、引用するのは、数ある議論から、「死」や「性」の暴力性をタブー視してきた問題に注目するためである。ジョルジュ・バタイユ、『エロティシズムの歴史 呪われた部分―普遍経済学論の試み:第二巻』(湯浅博雄・中地義和訳)、筑摩書房、2011、125頁。
[21] Cocteau, op.cit., p88. « J’ai traversé des périodes tellement insupportables que la mort me semblait quelque chose de délicieux. »
[22] バタイユからすれば、欲望と嫌悪は結びついており、死に向かう時でさえも、募る不安が欲望の対象の魅力を高める可能性がある。そのため、「われわれが欲するのは、われわれの力と諸資源とを汲み尽くすもの、そして必要となれば、われわれの命をも危険にさらすもの」である。同上、141-143頁。
[23] 死を正面から見据えることへの憧れを文学によって満たし得る読者がいるように、「主人公の性格がおのずから彼を破滅に導くとき、魅力は一番高まる」とバタイユは考えている。同上、147。
[24] コクトーは小説『恐るべき子供たち』の中で、恋に目覚めたポールを踏まえ、「運命の働きの途方もなさ」に対して、次のように表現している。「運命はレースを編む女のように、私たちをクッション代わりに膝の上に置き、女たちの針の動きをゆっくりと真似て、私たちを針で穴だらけにするのだ」。コクトー、『恐るべき子供たち』(中条省平・中条志穂訳)、光文社、2020、173頁。
[25] マリー・タリオーニは、ロマンティック・バレエ時代の最も天上的なダンサーと評されるほど、はかない精神性と超自然的な優雅さの体現に長けていたバレリーナである。それゆえ、彼女が「爪先で立って踊る技法を、単なる見世物的な技術から詩的舞踊の崇高な表現に変えた」と言われている。デブラ・クレイン、ジュディス・マックレル、『オックスフォード バレエダンス辞典』(赤尾雄人・海野敏・鈴木昌・長野由紀訳)、平凡社、2010、283頁。
[26] 舞踊研究家の芳賀直子曰く、諸説はあるが、「ダンサーたちはそれぞれ工夫を凝らし、指先を布で巻いたり、生肉を入れたなどという話も伝わっている」そうだ。芳賀直子、『ビジュアル版 バレエ・ヒストリー バレエ誕生からバレエ・リュスまで』、世界文化社、2014、p.82。
[27] 例えばトウシューズメーカーのFREEDは、2018年より肌の色に応じたブラウン系のポワントを制作しているが、それ以前は白い肌に合う色味しか存在しなかったがゆえに、選択肢の少なさが自ずと白人至上主義を招いていたと考えられる。(https://balletblack.co.uk/freed-pointe-shoe-collaboration/を参考。)
[28] 『ノートルダム・ド・パリ』とは、ハリウッドにも活躍の幅を広げていったプティが、20年ぶりにホームのパリ・オペラ座に復帰して振付を行った意欲作である。イヴ・サン=ローランが衣装、ルネ・アリオが装置を担当したことで、華やかな色彩と荘厳なセットが目を引き、物語の時代性を越えて現代に置換されたスタイリッシュさが舞台を埋めつくしている。振付にはモダンなステップや奇怪な動きを多用し、クラシックの枠に収まらないダンスは、群衆の膨らみ、感情のうねりを鋭く描いている。それゆえ、カジモドの背中の湾曲をも巧みに再現し、19世紀の身体表象を20世紀の手法を持って具現化してしまう。プティのダイナミックな解釈の結晶とも言える作品だ。
[29] バタイユの観点を踏まえれば、「踊り子の浮き出た筋肉は、たとえダンスが労働と反対に至高の活動であり、その意味するところがひとえに美であるとしても、最も強い魅力の価値を下落させてしまう」ことも否めない。バタイユ、前掲書、200頁。
[30] 重さのある筋肉は、ミッシェル・セールが語るところの「あたかも彫刻の、空間的な、服喪の状態の、客観的で凍りついた、動かない単独性」を具現化するものだろう。反対に、流動的な音楽の目には見えない普遍性を体現するものこそ妖精と考えられる。ついでながら、本稿でセールを引用するのは、あくまでコクトーの両性具有に対する関心を分析するためにすぎない。ミッシェル・セール、『両性具有 バルザック『サラジーヌ』をめぐって』(及川馥訳)、法政大学出版局、1996、149頁。
[31] 彫像は、「死から、死にもとづいて、墓地から、そこに隠れているものから」やってくるとの見解をセールは示している。同上、115頁。
[32] シャルル・ボードレール、『悪の華』(安藤元雄訳)、集英社文庫、2017、248-249頁。
[33] 周知のようにボードレールは「現代性とは、一時的なもの、うつろい易いもの、偶発的なもので、これが芸術の半分をなし、他の半分が、永遠なもの、不易なものである」と定義づけている。シャルル・ボードレール、『ボードレール批評2』(阿部良雄訳)、筑摩書房、1999、169頁。
[34] 熊川哲也は『若者と死』に関するインタビューにて、「黄色い女っていうのは、若者の運命、はたまた彼の才能、彼の分身」、「芸術的なインスピレーション」だと語っている。ローラン・プティ振付、『若者と死』(2006年収録)、熊川哲也、ダーシー・バッセル出演、特典映像を参考。
[35] Cocteau, op.cit., p. 163. « Le tout, par l’éclairage dur, les ombles portées, le splendide, le sordide, le noble, l’ignoble, aura l’allure du monde de Baudelaire. »
[36] プティも『プルースト』を制作するほど思い入れがあり、コクトーとも親しい間柄にあったマルセル・プルーストは、愛する女性に関してこのようなことを述べている。「というのもこの気質が愛する女性を選ぶにあたり、われわれを補完してくれると同時にわれわれと対立するような女性、言いかえるとわれわれの官能を満足させると同時に心を苦しませるような女性ばかりを選んで、そうでない女性をすべて排除するからである。こうして選ばれた女性は、われわれの気質の産物であり、われわれの感受性の投影された倒立像であり、「ネガ」なのである」。プルースト、『失われた時を求めて4 花咲く乙女たちのかげにⅡ』(吉川一義訳)、岩波書店、2020、537頁。
[37] バタイユは、愛される対象である存在について、「満足よりも、不充足のほうがもっと深い意味を持つということ、われわれがそれを所有していたときよりも、それが逃れ去るときこそずっと大きな強度とともにそれが開示される」と語っている。バタイユ、前掲書、221頁。
[38] 訳者の湯浅博雄は、バタイユの上記の点を踏まえて、「〈愛の関係〉における私は、この相手(他者)を「私の対象」として区切り、言い表す他者とみなすことはできなくなる」ように、この他者は、私の主体的能力が及ぶ範囲から溢れ出してしまい、つねに〈逃げ去る存在〉なるため、「ちょうど『失われた時を求めて』の語り手である〈私〉にとって、アルベルチーヌがそうであるのと同様」だと自身の考察を交えつつまとめている。バタイユ、前掲書、319頁。
[39] ジャック・ラカンによる、「人の欲望は〈他者〉の欲望である」との定式を考慮すると、若者の欲望が満たされずに存続し続けているとも考えられる。なお、本稿でラカンを取り上げるのは、コクトーやプティがテーマにしてきた「愛」や「死」について掘り下げるためである。ジャック・ラカン、『精神分析の四基本概念(上)ジャック=アラン・ミレール編』(小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳)、岩波書店、2020、87頁。
[40] Cocteau, op.cit., p. 173. « Sans vous quitter, cela va de soi, puisque je me suis mêlé à mon encre assez étroitement pour que le pouls y batte. »
[41] ジョルジュの死には、ウージェニーの裏切りを筆頭に、破産、日曜画家としか見られないことへの憂慮など、幾つか仮説が存在している。その中で、コクトーは父親が男色家だったのではないかと疑っている。コクトーは、自らの性向を理解していたので、ユダヤ人がユダヤ人を見抜くように、「彼は、仮面を被っている男色家を識別する……私はつねづね、自分と父がとてもよく似ているので、こうした重要な点で異なっているとは思えなかった」と小説『白書』にて語っている。ドミニク・マルニィ、『コクトーが愛した美女たち』(高橋洋一訳)、講談社、1998、29-32頁。
[42] コクトーは手袋をつける仕草を「今まで死んでいた手袋の皮が生きて来て、ぴったりと貼りつき、形を具え、それぞれの指が順々に動き出し、最後に、あの手袋のボタンを掛ける愛すべき儀式が行われるのだった」と「わが青春記」にて回想している。コクトー、『ジャン・コクトー全集Ⅴ』(堀口大學・佐藤朔監修)、東京創元社、1981、17-18頁。
[43] 三木英治は、コクトーにおける手袋について、母を劇場へ、オルフェを鏡の中へと導く、一種の「通行手形」として表現している。三木英治、『21世紀のオルフェ—ジャン・コクトオ物語―』、編集工房ノア、2009、31頁。
[44] コクトー、『ジャン・コクトー全集Ⅷ』(堀口大學・佐藤朔監修)、東京創元社、1987、294-295頁。
[45] 青木研二は、「精神分析学的発想によれば,無意識レベルにあるものの存在形態は幼児期の生育体験に強く規定されているわけで,自己にとっては変更が難しいためにむしろ拘束的なものとして働く可能性がある」と考え、芸術創造にあたり、コクトーと性的コンプレックスのテーマを安易に結びつけることに対し、疑問を抱いている。青木研二、「コクトーの『詩人の血』」、『茨城大学教養部紀要』、1995、第28号、132頁。
[46] コクトー、前掲書、1985、235頁。
[47] フロイト、「男性における対象選択のある特殊な型について」、『フロイト全集11』(高田珠樹・甲田純生・新宮一成・渡辺哲夫訳)、岩波書店、2009、245頁。
[48] 同上、245頁。
[49] Cocteau, op.cit., p. 139. « Bref, c’est une soirée prise sur le vide où ils se cherchent. »(既訳168頁引用)。
[50] Ibid., p. 137. « Il est ridicule d’envisager la jeunesse sous forme de mythe et en bloc. Par contre, il est ridicule de la craindre, de mettre une table entre elle et nous, de lui claquer la porte au nez, de prendre la fuite à son approche. » Nous soulignons.(既訳166頁参考)。
[51] 青木、前掲書、141頁。
[52] コクトー、前掲書、1987、2頁。
[53] 同上、3頁。
[54] ラカン、前掲書、2020、82頁。
[55] 同上、130頁。
[56] コクトーは『詩人の血』に関して、夢に頼るわけでも、象徴を援用するわけでもないと断言し、「象徴についていえばこれを嫌悪しており、そのかわりに行為あるいは行為のアレゴリーを盛り込んでいる」と説明している。コクトー、前掲書、1987、3頁。
[57] Cocteau, op.cit., p. 60. « Depuis Nerval, Ducasse, Rimbaud, l’étude de son mécanisme a souvent donné au poète le moyen de les vaincre, d’accommoder notre monde autrement que le bon sens ne nous y oblige, de brouiller l’ordre des facteurs auquel la raison nous condamne, bref de faire à la poésie un véhicule plus léger, plus rapide et plus neuf. »(既訳70頁参考)。
[58] Cocteau, op.cit., p. 151. « Il consiste à obéir au mécanisme des plantes et des arbres et à projeter du sperme loin autour de nous. »(既訳183頁参考)。
[59] Ibid., p. 151. « Ecrire est un acte d’amour. »
[60] Cocteau, op.cit., p. 173. « Et si vous parvenez à le lire sans que plus rien ne puisse vous distraire de mon écriture, peu à peu vous sentirez que je vous habite et vous me ressusciterez. »(既訳210頁)。
[61] たとえばコクトー曰く、人間は自分にとって都合の良い部分を選択して読み、用途に合わせて考えているため、読書とは思い込みでもある。それゆえ、芸術に接していても自分自身を読み、見ているに過ぎない。Ibid., p. 145. « De même que l’homme ne lit pas, mais se lit, il ne regarde pas, il se regarde. »
[62] ジェラ―ル・マノニ他、『ローラン・プティ ダンスの魔術師』(前田允訳)、新書館、1987、112頁。
[63] 例えば、ここでラカンがまったく異なるコンテクストで述べたことを想起したいという誘惑に駆られることになる。ラカンは、愛はいつでも相互的だとみなし、「愛は愛を要求する……もっと〔encore〕」と要求することをやめないものとして語っている。ジャック・ラカン、『アンコール』(藤田博史・片山文保訳)、講談社、2019、12頁。
[64] コクトー、前掲書、1987、4頁。
[65] 本稿で扱うバレエ用語には、簡易的な説明文を記載しているが、主に、小山久美監修、『バレエ用語集』、新書館、2009を参考にしている。
[66] 舞踊評論家の海野敏は、「プティの作品は、古典技法を尊重しながらも、それに”ずらし”を加えておしゃれに見せる振付に特徴がある」と語っている。海野曰く、パリオペラ座出身のプティは、ターン・アウトの美学を大事にしつつも、古典ではありえない、肘をはったり、肩をすくめたり、ターン・インを加えることで、バレエの枠組みを少しずらし、華やかで楽しいダンスへと発展させているそうだ。海野敏、2006、「ローラン・プティの美学―20世紀バレエ界に革新をもたらした振付家の“粋”―」、熊川哲也出演『若者と死』のDVD内の付属パンフレットより参考。
[67] ボードレール、前掲書、168頁。
[68] プティがイギリスのロックバンド「ピンク・フロイド」の楽曲に合わせて、振り付けを行ったバレエである。音楽はさることながら、身体のラインを生かすべく極めてシンプルに作り上げられた衣装や、レーザー光やスモークを導入した演出も特徴的で、クラシック・バレエ界に新規軸を打ち出したとも言える前提的な作品である。抽象バレエのような構成ゆえ、ロックをバレエ・ダンサーの肉体をもって描く斬新さが光る。
[69] 何十人もの振付家の創作意欲を掻き立ててきた今作は、シェイクスピアの有名な戯曲をベースとしつつも、あらゆる解釈が存在しており、バレエ史に幾度となく彩りを添えてきた名作である。とりわけ、プロコフィエフが作曲を担当したプソタ版以来、ドラマティックな演出に拍車がかかり、現在最も有名な演出であるマクミランやクランコのバージョンをも生み出すことになった。ちなみに、マクミランの演出に至っては、「頑なで情熱的なジュリエットを物語の中心に置いており、彼女は暴力や自分を脅かす慣習的制約に対して抵抗する」ように描かれているため、家父長的な呪縛からの解放や自由を求める強さに独自性が窺える。デブラ・クレイン、ジュディス・マックレル、前掲書、612-613頁。
[70] ミッシェル・セールは、人間は左利きか右利きか決まっているため、誰しもが半身不随であり、「対象の側、黒い、死者の、凍り付いた側に、自分を反映して」生きていると語っている。本論文で左を半身不随としたのは、若者の、右(生)の世界に重きを置いた結果である。ミッシェル・セール、前掲書、p.138。
[71] Cocteau, op.cit., p. 168. « Un ballet possède, en outre, ce privilège, de parler toutes les langues et de supprimer la barrière entre nous et ceux qui parlent celles que nous ne parlons pas. »
[72] バタイユは、「そういうマテリアルな生の運動は、人間の内的な生を、キリスト教が表しているような連鎖的束縛(アンシエヌマン)のうちに引きずっていくというよりも、むしろある種の絶え間ない破壊という奔出(デシエヌマン)のうちへともたらす」と語っている。バタイユ、前掲書、283頁。
[73] 「メタファー(métaphore)」は一般に次のような意味で用いられる。
« Figure d'expression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme qui, en langue, en signifie une autre en vertu d'une analogie entre les deux entités rapprochées et finalement fondues. » (https://www.cnrtl.fr/definition/metaphoreより引用)。ただし本論ではこれを広義に捉えたい。
[74] Cocteau, op.cit., p. 168. « La scène monte jusqu’à la danse, c’est-à-dire jusqu’au déroulement des corps qui s’accrochent et se décrochent, d’une cigarette qu’on crache et qu’on écrase, d’une fille qui, du talon, frappe trois fois de suite un pauvre type agenouillé qui tombe[…]. »
[75] コクトーは作品内によく「罠」という言葉を散りばめるのだが、美を成り立たせるもの、また芸術を永遠化させる巧妙な策略として扱う傾向にある。Ibid. , p. 146. « De siècle en siècle, la Joconde attire la ruche des regards à des pièges que Léonard croyait tendre à la seule beauté de son modèle. »Nous soulignons.
[76] Franco, op.cit., p.230. « Cocteau : il avait insisté afin que les détails des mouvements soient répétés trois fois chacun, fort du fait que« la première fois le public ne voit pas mouvement. La deuxième fois le remarque. La troisième fois il existe pour lui ». »
[77] 「メトニミー(métonymie)」は一般に次のような意味で用いられる。« Figure d'expression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme qui, en langue, en signifie une autre, celle-ci étant, au départ, associée à la première par un rapport de contiguïté. »(https://www.cnrtl.fr/definition/metonymieより引用)ただし本論ではこれを広義に捉えたい。
[78] ラカンは「威嚇」に関して、「主体が、やはりその見かけによって達しようとする過剰価値」だと説明している。ラカン、前掲書、2020、216頁。
[79] 『カルメン』は、『若者と死』の3年後に発表された、プティの初期作の一つである。オペラにインスピレーションを受けた後、原作を下敷きにした今作は、闘牛のイマージュが香る一方で、レビュー的な要素も散見され、プティのオリジナリティに溢れている。その上、ミカエラやホセの母親が登場しないため、ひたすらカルメンとホセの激しい愛に収斂しているのも特徴的だ。二人の寝室でのパ・ド・ドゥに至っては、バレエ史上初めてベッドシーンを盛り込んだ振り付けである。古典バレエに多いプラトニックな恋愛とは異なり、陶酔や恍惚といった、世俗性と神聖さが交錯するような愛のかたちをプティは描きだしたと言えよう。ちなみに、椅子やタバコを使って表現する場面も多く、小道具や衣装を介して空間を鮮やかに彩るのも『若者と死』などの他作品とも通じるところである。
[80] プーシキンの『スペードの女王』をもとに、チャイコフスキーの『交響曲第六番悲愴』にのせて、描き出されるバレエ。フランス文学が多いプティの中で、異色とも言うべきロシア文学が題材の作品であるが、バリシニコフより頼まれて作り上げた初演、後にボリショイ劇場のために作り直した再演と、プティにとって長年連れそうことになる、濃密な舞台の一つだ。なお、このゲルマンと夫人のパ・ド・ドゥは原作の意図に反するため、バリシニコフは拒否していたが、ゲルマンの「情人(いろ)になってもいい」と語る意気込みをプティは舞踊で表現すべく、反対を押し切って制作を続けたそうだ。クラシック・バレエを基調にしつつ、軽快なステップ、多種多様な身振りが盛り込まれ、プティの独特なアレンジが舞台に響き渡っている。守山実花監修、「名作の世界―『スペードの女王』―」、『隔週刊バレエDVDコレクション25』、デアゴスティーニ・ジャパン、2012、8-9頁参考。
[81] 谷昌親曰く、闘牛のテーマを頻繁に用いたレリスは、右と左の持つ象徴的な役割を踏まえ、右に対する左の侵犯が聖なるものを導き出すと考えている側面がある。そのため、「牡牛や身のかわしに描かれる軌跡のせいで課される逸脱」が必然的に生じてくる闘牛にも美的価値を見出している。谷昌親、「闘牛と「聖なるもの」―ミシェル・レリスにおける不器用さの民族学」、『人文論集』、2019、第57巻、31-35頁。
[82] プティはインタビューにて、早くから『若者と死』の中で椅子を使い始めていたことに言及しており、「これは素晴らしい演技者なのだ」と語っている。ジェラール・マノニ、前掲書、130頁。
[83] 「じっさい、この子供たちが創りだすものは傑作だったし、それは彼らそのものという傑作であり、そこには知性がまったく関与せず、その驚異はなんの自負も目的もないことから生まれていた」。コクトー、前掲書(中条訳)、2020、90-92頁。(作者による強調)。
[84] ロシア・フォルマリズムの理論家であるシクロフスキーは「芸術の目的は、再認=それと認めることのレベルではなく、直視=見ることのレベルで事物を感じとらせること」だと語っており、習慣化されゆく知覚を突き抜ける手法として、「異化」の概念を打ち出している。ヴィクトル・シクロフスキイ、「手法としての芸術」(松原明訳)、『ロシア・アヴァンギャルド6 フォルマリズム―詩的言語論―』、国書刊行会、1988、25頁。
[85] ダニエル・アラス、『モナリザの秘密 絵画をめぐる25章』(吉田典子訳)、白水社、2007、261-262頁。
[86] 同上、260頁。
[87] ダニエル・アラスは研究対象として絵画について書いたり話したりすることを選んだが、こうした枠組みを掻い潜るものとして絵画を捉えている。ゆえに彼は、そのような「絵画におけるこの『名付けられないもの』―フラゴナールのタブローはその完璧な例だと思うのですが―からわかることは、絵画はつねに、欲望の対象の地位にあるということ」だとまとめている。同上、261頁。
[88] 『ラカン『精神分析の四基本概念』解説』では、「絵を描くという行為は、鑑賞者を『見かけ』によって『騙す』ことで、当の『見かけ』に気づかせ、そのことでかえって『対象a』をあらわにすることである」と解釈されている。それゆえ鑑賞者には「眼差し」への「欲望」が備わっているのだと語られている。荒谷大輔・小長野航太・桑田光平・池松辰男、『ラカン『精神分析の四基本概念』解説』、せりか書房、2018、87-88頁。
[89] 『プルースト』は、『失われた時を求めて』を全2幕のバレエに仕立てた作品である。前半は天国、後半は地獄のイマージュに分けて展開される。語り手こと「私」は若き日のプルーストと一体化しており、全体を通して作家になるために必要不可欠な出来事が、13のタブローとなって紡がれる。タブローの形式は『ノートルダム・ド・パリ』と同じプティのパターンで、物語に依拠しつつも、抽象バレエと似ているがゆえに、ダンスそのものも堪能できる仕掛けだ。13の情景に絞られただけあって、アルベルチーヌとプルーストの『囚われの女』のパ・ド・ドゥように軽やかでドラマティックなシーンから、後の『こうもり』のウルリッヒを彷彿とさせるシャルリュスのコメディタッチな演技まで、バラエティに富んだ踊りが見られる。そんなプティの登場人物に応じた変幻自在な振付は、「言語標本」として人々を描きがちなプルーストの視点を絶妙に反映させている。
[90] Cocteau, op.cit., p. 160. « De longue date, je cherchais à employer, autrement que par le cinématographe, le mystère du synchronisme accidentel. »
[91] 国安洋は、音楽を内的な自己の運動の表出にあると考えたヘーゲルを始めとする知識人を踏まえ、「音楽は自我への親近性をもつが故に、音楽における音の流れはただちに心の動き、つまり感情に照応するのである」と述べている。国安洋、『音楽美学入門』、春秋社、1981、80頁。
[92] 深澤南土実、「ローラン・プティ≪若者と死≫―「生」の象徴としての「若者」―」、『人間文化創成科学論叢』、2011、第14巻、122頁。
[93] 「遊戯というのはひどく不正確な用語だが、ポールは、子供たちが潜りこむ半意識の状態をそう呼んでいるのであった」。コクトー、前掲書(中条訳)、46頁。
[94] バッハを扱った作品として各振付家の代表的な作品には、ノイマイヤー『マタイ受難曲』、フォーサイス『ステップテクスト』、シュペルリ『バッハ無伴奏チェロ組曲』、『マニフィカト』が挙げられるだろう。
[95] 三浦雅士、『コリオグラファーは語る ダンスマガジン編』、新書館、1998、61頁。
[96] セール、前掲書、168-169頁。
[97] レヴィ=ストロース、前掲書、69-70頁。
[98] ロラン・バルト、『エッフェル塔』、(宗左近・諸田和治訳)、筑摩書房、2007、100頁。
[99] 同上、104頁。
[100] 同上、102頁。
[101] ラカンを踏まえるなら、このように叫ばれ続ける問題、一種「多くの騒音も、発達の竪琴に合わせて次のような質問を吟じさせてくれるなら、実際にはむだになるまい」と考えられる。「なぜなら、そこには音楽があるから」だ。ジャック・ラカン、『エクリⅢ』(佐々木孝次・海老原英彦・芦原眷共訳)、弘文堂、1981、210頁。
[102] プティは「最も大切なことは何かを強く感じることであり、それをダンサーを介して動きと音楽の一致を具現しながら伝達することである」と語っている。マノニ、前掲書、131頁。
[103] 「追悼ローラン・プティ—アレッサンドラ・フェリ 美とは何かを知る人―」、『月刊ダンスマガジン10月号』、新潮社、2011、56頁。
[104] 佐々木忠次、『闘うバレエ 素顔のスターとカンパニーの物語』、文藝春秋、2009、195頁。
[105] 同上、195頁。
[106] 「追悼ローラン・プティ—ニコラ・ル・リッシュ プティからの結婚プレゼント—」、前掲書、48頁。
[107] « Cinquante-sept ans plus tard, la chorégraphe Olga de Soto mène l’enquête sur ce ballet devenu mythique et part à la recherche des spectateurs présents ce soir-là pour donner la parole à leurs souvenirs et à leurs trous de mémoire. » https://www.olgadesoto.com/fr/histoires (2021年11月28日アクセス)
[108] ラカンは、「声」と「眼差し」を特性として持つような「マス・メディア」が繰り出す「かくも多くのショーや幻想においては、我われの視覚が喚起されているというよりも、むしろ我われの眼差しが呼び出されている」と考えている。ジャック・ラカン、『精神分析の四基本概念(下)ジャック=アラン・ミレール編』(小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳)、岩波書店、2020、337頁。
[109] アルフォンス・ドーテの戯曲に基づきながら、ビゼーの壮大な音楽に乗せて送るバレエ作品である。許嫁がいるにもかかわらず、主人公フレデリが闘牛場で出会った「女」に心を奪われ、狂気に陥り、自死してしまう結末は、『若者と死』にも通ずるプティならではのテーマを彷彿とさせる。死に直進していくフレデリのソロ「ファランドール」は、激しくも躍動感あふれるラストシーンで、ダンサーの見せ場としても有名な場面である。
[110] 「ダンスマガジン・インタビュー バンジャマン・ペッシュ×三浦雅士」、『月刊ダンスマガジン4月号』、新潮社、2012、66-70頁。
[111] 「追悼ローラン・プティ—ステファン・ビュリオン 可能性の扉を開いてくれた人―」、前掲書、50頁。
[112] ラカンは、「分析経験全体―それはここにいらっしゃるみなさんそれぞれの経験の根っこに横たわっているものの別名にすぎないのですが―が証言しているように、欲望することを欲しないことと、欲望すること、この二つは同じこと」だと語っている。ラカン、前掲書(下)、253-254頁。
[113] 「追悼ローラン・プティ」、前掲書、48頁。
[114] ダンサーと振付家の関係性に着眼するに際し、改めてラカンを想起したい欲望が駆り立てられることになった。「私は君(テュ)を愛している、しかし、不可解なことに私が君の中に愛しているのは君以上のもの―対象a―なので、私は君を切り裂く」。ラカン、前掲書(下)、325頁。
[115] Cocteau, op.cit., p. 167. « Ajouterai-je qu’une minute de contact entre une salle et une œuvre supprime momentanément l’espace qui nous sépare d’autrui. »(既訳202頁参考)。
[116] Ibid., p. 167. « Ce phénomène, qui groupe les électricités les plus contradictoires au bout de quelque pointe, nous permet de vivre dans un monde où le cérémonial de la politesse arrive seul à nous donner le change sur l’écœurante solitude de l’être humain. »(同上)。
[117] 三浦雅士は、プティがコクトーを介してディアギレフに繋がり、そしてサルトルやカミュの実存主義にも繋がることを言及しており、その上で「プティだけが実存主義に潜む永遠の領域を舞台化したのだ」と断言している。「追悼ローラン・プティ」、前掲書、45頁。
[118] ジェラール・マノニ、前掲書、129頁。
[119] ラカンは、「わたしたちがただひとつである〔Nous ne sommes qu’un〕」ことから愛の観念が始まったとし、「誰もが引き合いに出すこの〈一〉は、まず、人が自らにあると信じている〈一〉の、あの蜃気楼の性質を持っています」と語っている。ラカン、『アンコール』、2019、84-85頁。