作家とは誰か? 公衆と対峙するルソーと文体の変遷
Christine Hammann, Déplaire au public: le cas Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 2012, 491p.
クリスティーヌ・アマン、『公衆から嫌われること 事例ルソー』、パリ、クラシック・ガルニエ、2012年、491頁
富田圭(慶應義塾大学文学研究科修士課程)
本書の著者クリスティーヌ・アマンは、17・18世紀フランス文学を専門とする研究者であり、現在上アルザス大学准教授として教鞭を取っている。彼女の研究の主要な関心は、ルソーを軸としながらも、より一般的に、レトリックを通じた作者と「公衆=読者(public)」の関係の問題にある。しかし他方で、ルソーにおける間テクスト性についての業績も多数あり、特にルソーとトルクァート・タッソとの間テクスト的読解に関心を向けている。

本書はアマンがパリ第三大学に提出した博士論文〔原題 :『18世紀のある作家における読者から嫌われること ルソーの場合 (Déplaire à son public pour un auteur du XVIIIe siècle : le cas de Rousseau)』、審査:ジャン=ポール・セルマン(主査)、ジャック・ベルシュトルド、アラン・グロリシャール、ジャン=フランソワ・ペラン、ヤニック・セイテ、2009年〕に加筆、修正を施し、ガルニエ社から出版されたものである。前述したアマンの広範な関心に沿って、400ページを超える四部構成で書かれているが、同時に、本書全体を通してルソーの文体の変遷を包括的に描くという野心的な試みともなっている。
まずは各部の展開に沿って本書を概観したい。
本書において、一貫して著者がルソーの仮想敵に選ぶのは、17世紀を代表する三人の作家、コルネイユ、モリエール、ラ・フォンテーヌである。彼らは、「気に入られる=喜ばす技術 (l'art de plaire)」を駆使し「良き趣味(le bon goût)」に準じることで、17世紀の「公衆(public)=宮廷(人)」の政治的秩序を支える絶対王政の共犯者たちだとされる。それだけではない。公衆に好かれようとすること、それは作家個人の感受性、天才を従属させる、抑圧的制度の一端を担うことにもなる。以上のようにアマンは、ルソーの「気に入られること(plaire)」への批判の賭け金が、政治・美学・倫理という広範な領域にまたがっていると考える。こうした射程のもと、『学問藝術論』、『ナルシス』序文、『ダランベールへの手紙』が書かれることになった、というのである。
しかし、同時に著者は、ルソーの「気に入られること」への批判が、先行者・同時代の作家たちの文学的実践と連動していることにも注意を促す。モンテスキューはすでに『法の精神』において17世紀的理想(洗練された「オネットム」)が特権階層と共犯の関係にあることを指摘していたし、マリヴォーは彼自身の発行する定期刊行物において読者から「気に入られること」のみを志向する作家たちと距離を置き、「嫌われること」を厭わずに自己の試みに忠実であろうとしていた。何よりディドロは、ルソー自身が「告白」するように、彼の「気に入られること」を拒否する「荒々しい」文体に多大な影響を及ぼしていたのである。いずれにせよ、この「気に入られること(plaire)」の体制からの離脱の試みが、「嫌われること=不快にさせること(déplaire)」として定義されることになる。ここまでが第一部・第二部の大まかな論点である。

ところが、18世紀に起こった公衆の民主化、多様化、いわば「公衆の誕生」は、17世紀の宮廷社会をモデルとする密室的な公衆像を劇的に変容させた。今や公衆は、王権に代わる新たなる至高の「法廷」(マルゼルブ)となった。アマンによれば、このように変貌した公衆と対峙することになったルソーは、「読者公衆への無配慮=嫌われること」という態度を変更し、「気に入られること」の再定義を経て、新たなる「気に入られる=喜ばす技術(l'art de plaire)」、つまり別様な作家と読者との関わりを『エミール』『新エロイーズ』において模索することになったというのである。これが第三部・第四部で扱われる本書の第二の論点である。
著者はまず、『エミール』にルソーの「人間学(anthropologie)」の重大な転回点があることを示す。初期の著作である『学問藝術論』『人間不平等起源論』の中で社会と「同時に」発生するとされた「気に入られたい欲望(le désir de plaire)」が、青年の情念のめざめを主題とする『エミール』四巻の「第二の誕生」において「自然化」され、自然な情念の一種として分類されるのである。
次に、ルソーが『新エロイーズ』において実践した新たなる「気に入られる技術」が検討される。著者はジャン=フランソワ・ペランによる「理性による説得(convaincre)/情念による説得(persuader)」という区分を援用しながら、後者の方法である「情念による説得」が、経験論から感覚論へと連なる哲学の系譜(ロック、コンディヤック)に根ざす一方で、ペランが強調するようにキリスト教のレトリックの伝統(パスカル、マルブランシュ、ピエール・ニコル)とも接続することを示す。アマンによれば、ルソーは以上のような先行者たちの理論を取り込みつつ、自らの「気に入られること」、すなわち「詩」=フィクションの「快楽(plaisir)」による説得という方法を確立させたというのである。
以上の議論を踏まえた上で、本書第三部においては、積極的に捉え直された「気に入られること=快を与えること(plaire)」による読者公衆の説得=道徳的教化こそがルソーの新たな目的であった、とされるのだ。
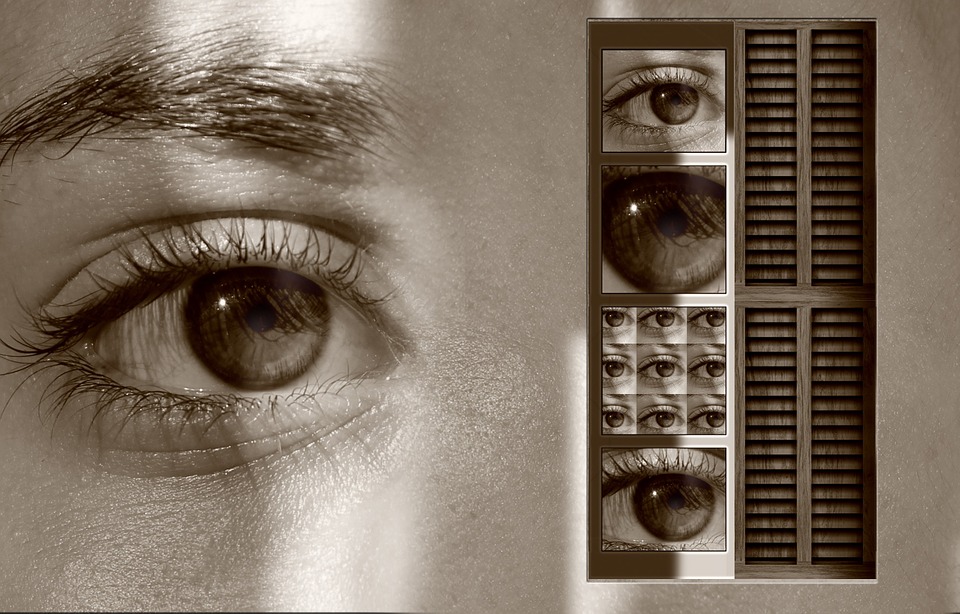
しかし、このように「公衆」への態度を変更するならば、ルソーは、(潜在的に)悪であったはずの「気に入られること」を通じて道徳的教化という「善」を実現しなければならない、という困難に直面することになる。本書第四部ではこの問題が集中的に扱われる。アマンはまず、「大都市には演劇が必要であり、堕落した都市には小説が必要である」という『新エロイーズ』「第一の序文」冒頭の一節の分析から始める。彼女の読解によれば、この逆説的表現には、「病のうちなる治療薬(le remède dans le mal)」という、かつてスタロバンスキーによって緻密に分析された、ルソー(そして啓蒙という時代全体)における特権的なモチーフが機能しているのである。この読解を皮切りに、著者は本書第四部を通して、このモチーフがさまざまに形を変えながら、作家と公衆の関係の形象としてルソーの数多くの作品に見いだされることを明らかにしていく。「気に入られる技術」を駆使するものとしての「詩人」=フィクションの作り手は、時に「病の中の治療薬」を駆使する医者であり、共同体のスケープゴートにされるファルマコンであり、放火によって不滅の名声を得ようとするヘロストラトスである。このように、多岐にわたる作家(と「公衆」との関係)のイメージの分析を通して、ルソーにおけるフィクションの快楽(plaisir)と有用(utilité)との鋭い対立と、「気に入られる=快を与えること(plaire)」によって有用であることを目指す『新エロイーズ』の特異性が浮き彫りにされるのである。
以上が本書の大まかな内容であるが、いくつかの注意すべき点、問題点を挙げたい。
本書の眼目は、「気に入られること(plaire)」と「公衆(public)」という概念を軸として、ルソーの文体の変遷に統一的なパースペクティヴを与えることにあるだろう。 文体の変遷と二度にわたる「自己改革(les réformes)」の連動という図式は極めて明快であり、説得的であるものの(まさにそれは『告白』におけるルソーの自己解釈なのだから)、いくつかの重大な理論的問題を残す。
実際に、著者はこの図式化による弊害、たとえば、フィクションを糾弾する『ダランベールへの手紙』と、フィクションによる道徳的教化を試みた書簡体小説『新エロイーズ』というあまりにも矛盾した二つの著作が、ほとんど同時期に書かれている、という難問の分析に第四部全体を費やすことになる(しかし、この二作品の同時性だけでなく、奇妙なことに同質性すら、ルソー自身によって『告白』に書き込まれているのだが、この点について著者は立ち入っていない)。また、本書第三部では、ペランの議論に依拠した「理性による説得/ 情念による説得」という二項図式がいささか安易に『エミール』と『新エロイーズ』に当て嵌められる。そして、教育論の概説書である前者において用いられた方法は専ら「理性による説得」であったとされるのである。しかし、そのような単純化は、まさにロレンス・モールの仕事が明らかにしたような『エミール』におけるフィクションの機能、たとえば語りの重層性といった要素を、ほとんど完全に切り捨ててしまっていることになるのではないか。この点は本書の射程を狭めてしまうことになったと言えよう。

さらに、本書の扱う領域の広さと、それによって引き起こされる問題も指摘できるだろう。
本書の鍵語となる「気に入られること(plaire)」と「公衆(public)」は、互いに連動しながら歴史的に変容し続ける、極めて動的な概念である。本書第一部冒頭で修辞学の伝統における文を彩る「飾り(ornement)」に過ぎなかった「気に入られること」が、17世紀の宮廷社会においては「適切であること(aptum)」を意味する文士の成功に不可欠の要素となり、18世紀のリベルタンにとっては「誘惑(séduction)」することと等価となる。これに応じて「公衆」もまた、アゴラの聴衆から宮廷社会の女性たち、そして『新エロイーズ』を読む「読者」へと様々に変貌するのだ。
本書の研究にとってこれらの鍵概念の射程の広さは、さまざまなジャンルに跨るルソーのほとんど全作品を扱う事を可能にしているのだが、著者はそれによって複雑化した論点を整理し切れていないようにも見える。具体的に指摘するならば、第一部・第二部では美学の問題が政治・倫理といかに交錯するのかが繊細に扱われていたのに対し、第三部以降で文学作品の本格的読解に入ると、ルソーの著作にたびたび現れる作家(と「公衆」との関係)を表す内的形象の連鎖を追うことが優先され、三つの領域がいかに交錯しているのかが曖昧になっている。その結果、特に政治的な問題系が美学と倫理の問題に比べて主題として扱われることが少なくなり、本書前半部が強調していたような、ルソーにおける文体(=公衆への態度)の選択の政治性についての議論を十分に展開できていないのではないか。この点、政治的な問題系に関心を持っている読者にとって本書後半部は、前半部に比してやや不満の残る内容になっているだろう。
以上のように、幾つかの問題点を提起したが、最後に本書を貫く二つのアプローチについて手短に言及したい。
本書は前半部と後半部では用いられる方法が大きく異なっている。ルソーの著作を歴史的な文脈に置き直し、先行者や同時代人との影響関係を検証するとともに、その独自性を際立たせる手法は、本書前半部の基本的な姿勢である。以上のようなアプローチを外在的なネットワークを(再)構築する作業だとするならば、主に後半部において用いられる、ルソーのテクストに反復的に現れる(時に神話的な)形象を読解し、それらの連鎖を丹念に追う手法は、内在的なネットワークを描くアプローチだと言えるだろう。著者が特にこの手法を集中的に用いるのは本書第四部の、ルソーの著作(と書簡)に見出される作家と「公衆」の関わりを表す形象の緻密な読解においてである。そして、その部分こそ、アマンのテクスト分析の力量が冴え渡る箇所なのではないだろうか。いずれにせよ、これら二つの方法を巧みに組み合わせて、初めてルソーを読解することが可能となるように思われる。そしてクリスティーヌ・アマンは本書において、二つのアプローチをどちらも妥協なく押し進め、それらの総合を果敢に試みていると言えるだろう。