サドを読む
Michel Onfray, La passion de la méchanceté : sur un prétendu divin marquis, Editions Autrement, Collection Universités populaires & Cie, 2014.
ミシェル・オンフレ『悪意への情熱 いわゆる神のごとき侯爵について』、2014年
Annie Le Brun, Sade: attaquer le soleil, Musée d’Orsay-Gallimard, 2014.
アニー・ル・ブラン『太陽を攻撃したい』、2014年
Michel Delon, avec la coolaboration de Sophie Bogaert, Les vies de Sade, 2 vol., I, Sade en son temps, Sade après Sade ; II, Sade au travail, Textuel, 2007.
ミシェル・ドゥロン 『サドのいくつもの生:I 彼が生きた時代のサド、サドの後のサド;II 仕事中のサド』,2007年
宮本陽子(広島女学院大学教授)
サド没後200年の2014年にはサドに関する多くの書物が刊行された。その一冊がここで最初に取り上げる、「反文学史」の執筆を標榜するオンフレの『悪意への情熱』(以下『悪意』とする)である。また、書籍の出版のみならず、展覧会が企画され、それが書籍となったものもある。その一冊が、オルセー美術館における展覧会の豪華な図録、アニー・ル・ブランの『太陽を攻撃したい』(以下『太陽』とする)である。もう一冊は、サドの没後記念出版とは関係ないが、先に挙げた二冊の対極にあるものとして、プレイヤード版サドの監修者ミシェル・ドゥロンの『サドのいくつもの生』(以下『サド』とする)を紹介する。
1 ミシェル・オンフレ『悪意への情熱 いわゆる神のごとき侯爵について』
オンフレは文学史がすでに評価を定めた文学者、哲学者を槍玉に挙げる。文学史が築き上げた「伝説」を粉砕するのが彼の務めだ。ここでも当然、サドを評価した文学者、哲学者が袋叩きになる。二部構成の前半は詩人が対象なので主にアポリネール、哲学者が対象の後半はバタイユに連なる文学者、哲学者が弾劾される。なぜ文学がサドを認めてはいけないのか。それはサドが「性犯罪者(délinquant sexuel)」だからである。健全な市民道徳を守る家庭人の代表オンフレにとってサドは、貧しいローズ・ケレルをアルクイユの妾宅に連れ込み、暴行を加えたサディスト、マルセイユで売春婦に催淫剤を飲ませ、下男と交わった変態、貴族の特権を利用する性犯罪者に他ならない。
ナチスの女看守の醜行を本書の序文とするオンフレは、サドの放蕩を18世紀の放蕩としてではなく、今日のメディアで報道される性犯罪に対するかのように義憤とともに記述する。サドを断罪せずに、「これまで存在したうちでもっとも自由な精神」と讃えたアポリネールが最大の戦犯だ。アポリネールが1909年に初めて、アンソロジーを『サド侯爵作品』として合法的に出版した意味は無視し、詩人がサドを「愛の巨匠たち」コレクションに入れたことにオンフレは激怒する。オンフレ自身はルヴェールの伝記も読み、サドの作品と書簡も読み、多くの情報に通じた上で、民衆の正義を武器に善男善女の共感に訴える。コレクションの名称の「愛」とサドの「非人道的な」放蕩の矛盾を何度も繰り返し強調し、誰にでも分かるように書く。これがオンフレの書き方だ。
歴史家を自称するオンフレは、恐怖政治下のサドがピック地区書記長として書いた文書も攻撃する。暗殺されたマラーを称える文書と『閨房哲学』に挿入されたパンフレット「フランス人よ、共和主義者たらんとすればあと一息だ」における「死刑反対論」が矛盾すると言うのだ。しかし、このパンフレット内で展開される殺人擁護論には言及しない。法による「死刑」は反対、個人の情欲による殺人は賛成、というのがサドの終生変わることのない持論であるのに、オンフレは、1794年に反革命の容疑で監禁されていたサドが部屋の窓からギロチンの犠牲者たちの山積みの死体を見た結果、死刑反対論者に宗旨替えし、『閨房哲学』のパンフレットを書いたのだと推定する。しかし、革命初期においてのみ死刑反対論者であったロベスピエールとは違い、サドの死刑反対論は無神論同様、死ぬまで変わらない。サドが革命勃発の1年前にバスチーユ牢獄で書き終えていた『アリーヌとヴァルクール』に登場する啓蒙的君主ザメの「死刑反対論」をオンフレは知らないのだろうか。
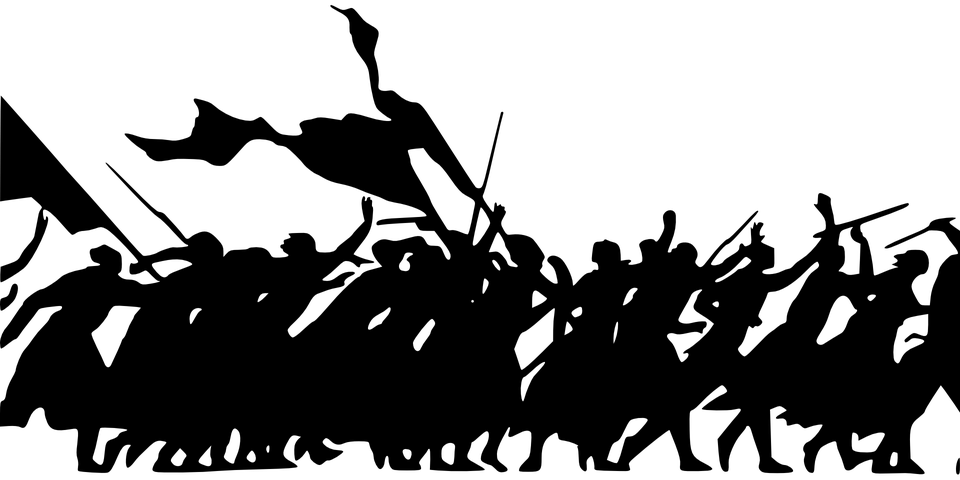
サドの政治活動は保身のためだけではない。1793年8月3日付のゴーフリディ宛の手紙において、1日にピック地区の議長となったサドが翌2日の議会で二度に亘って発言を阻まれ、副議長に席を譲って退席することを余儀なくされるさまが報告されている。ルヴェールはこの騒動について、王家の墓を開くこと、ヴァンデの破壊、マリー・アントワネットのコンシエルジュリへの移送を承認させようとした国民公会の要請に、サドがピック地区議長として反対意見を表明したためだとしている。ここにおいて、オンフレの情報が恣意的に操作されていると言わざるを得ない。
同じく恣意的な情報によって、公正さを欠いた攻撃の犠牲となるのがバタイユだ。ナチス同様の加虐者(bourreau)であるはずのサドに、バタイユが犠牲者(victime)を見出すことが逆鱗に触れる。バタイユはリベルタンが犠牲者の苦痛を自分のものとすることで快楽に変換するものとし、これがドゥルーズの「サドの言語は犠牲者の言語である」というテーゼに至る。しかし、「正確さや真実、歴史」が、「具体(concret)、現実(réel)」と「血肉を備えた(en chair et en os)」人間の日常によってのみ構成されるとするオンフレは、牢獄で贅沢をしていたサドが犠牲者のはずがない、という次元の論理で存在論的、言語論的解釈を粛清する。こうしてアポリネールとサド本人、バタイユに連なる68年以降の「テル・ケル」派、構造主義、ポスト構造主義が一刀両断に片付けられてしまう。
サドに魅了されることを許さないオンフレであるが、彼自身はサドやサドに魅了された人々の残した醜行にファンタスムの喜びを見出すようだ。サドの行動に小説を重ね、バタイユがシュルレアリストたちと耽った奇妙な秘密結社的儀式や、フーコーの暴力的同性愛者としての醜態を記述するオンフレの筆致は、サドのスキャンダルを暴き立てたジャナンやレチフの文章を彷彿させる。こうした記述によって、善男善女をブランショやバルトの魅力的なテクストから遠ざけてしまうことの罪は重い。
ただ一つ、オンフレの功績を挙げるならば、19世紀から現代に至るまでのサドを中心とする一つの文学史を誰にでも分かるように明快に示したことである。そうした意味でオンフレはランソンに勝ると言えるだろう。
2 アニー・ル・ブラン『太陽を攻撃したい』
オンフレとは逆に、ル・ブランはサドの影響力を肯定的に拡大する。この豪華な図録には、広範囲に及ぶ多量の美術作品が収録されている。大衆路線のオンフレとは違い、ガリマール書店や欧米の美術館の協力を得て、アカデミックな研究者を除くフランスの文化エリートが総力を結集したかのようなこの企画が対象とするのは、教養豊かな芸術愛好家だ。
図録のタイトルは『ソドムの120日』の4人のリベルタンの一人、キュルヴァル法院長が「太陽を攻撃」できないことを嘆く言葉からの引用である。ブランショやバルトが指摘したように、リベルタンが実行可能な犯罪=サドが書くことのできる犯罪の矮小さに慨嘆する、というのはサド=リベルタンの永遠のテーマだ。ル・ブランも類似した表現を繰り返す。例えば、サドは造形芸術を「表象不可能なものを表象することへの挑戦」に導くという具合だが、「想像不可能なものを想像すること」というバルトによるサドのエクリチュールについての表現とさして変わらない。ル・ブランのサドはオンフレの文学史で分類するなら、アポリネールからシュルレアリスト、そして「テル・ケル」派までに相当する。サドの本質的な部分については異論がないとしても、問題はそれがどのように造形芸術に結びつくかである。
ポヴェール亡き後、シュルレアリスム最後の世代を担うル・ブランは、19世紀文学に多大な影響と与えたサドの造形芸術への影響を示すことをこの企画の目的としたというが、収録されているのは19世紀絵画やシュルレアリストの作品だけではない。ヴァン・ローやマン・レイの有名な肖像画は当然としても、ボッティチェッリの「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」とこれに啓発されてドガが描いたという「中世の戦争場面」を見ると首を傾げたくなる。ドガの弟を戦慄させたというこの絵を、ル・ブランは展覧会の象徴となる絵だと述べる。ドガがボッティチェッリを参照したことは容易に納得でき、ここからゴヤの「戦争の悲惨」が連想される、というのも了解可能だ。しかし、なぜサドに結びつくのか。サドはボッティチェッリのこの絵について言及していない。ドガがサドを読んだかも不明だ。ル・ブランとしては「暴力」や「凶暴性(férocité)」によってサドと結びつくとしているようだ。じっさい彼女は、サドが見たか見ていないか、「画家がサドを読んだか否かを」収録の基準としていないと言う。芸術家でサド研究者であるル・ブランの中でサドと結びつく造形芸術であれば良いらしい。そのため、肉体に執着するアングルやロダン、極限状態の群像を描いたジェリコーやドラクロワなどの作品の他に、バタイユの使用したものよりも残忍な処刑の写真までが掲載されている。
より奇妙なのは、アンリ・ルソーの「戦争」という作品の存在とその周りの文章だ。作品の下に、サドが戦争の原因としての宗教を批判した文章の引用がある。左のページではル・ブランが、1793年12月6日にピック地区代表としてサドが書いたとする文章を数行引用し、これが8日のサドの逮捕に関わりがあるかのように示唆する。たしかに、サドはエベールらの反宗教運動に乗じて、11月21日にロベスピエールがこれを禁ずる直前までキリスト教批判の文書を書いた。しかし、ロベスピエールがエベール派粛清のために反宗教運動に終止符を打ってからもサドがキリスト教批判を書いたとするのは、ポヴェールとル・ブランだけだ。ポヴェールは出典をダニエル・ゲランの『第一共和国における階級闘争』としているが、ゲランはサドの名前を挙げていない。この文書をサドのものとする根拠は薄く、彼の戦争批判とアンリ・ルソーの作品の関係も不明だ。
とはいえ、第一章「肉体の夜を覗く」では画像と文章が見事に響き合う。ル・ブランはサドの『イタリア旅行記』を引用しながら、サドがイタリアで出会った美術や展示物とサドの関心を紹介する。この章はミケランジェロに対するサドの批判から始まり、マデルノの彫刻「聖セシリアの殉教」、ジャック・ファビアン・ゴーティエ・ダゴティやオノレ・フラゴナールの医学解剖図や蝋製の解剖人体の図が並ぶ。このすべてをサドが見たわけではないが、解剖学者たちの眼差しはサドの眼差しを雄弁に具体化し、それをル・ブランの文章がたどる。イタリア旅行での見聞を、サドは『イタリア旅行記』として作品にしようと考え、出版には至らなかったものの、25年後、『ジュリエットの物語』において主人公の旅の中に描き込み、これをル・ブランが美しい図録に収めた。この図録がすべてこの一章のような緻密さでサドと結びつくものであれば、この図録もサド没後200年を寿いで余りある快挙となっていただろう。
それにしても、サドと一緒にイタリアを歩き、『旅行記』のための挿絵を描いた画家ティエルスの名前が黙殺されていることが生前に発表されなかった作品だけに惜しまれる。
3 ミシェル・ドゥロン 『サドのいくつもの生:I 彼が生きた時代のサド、サドの後のサド;II 仕事中のサド』
「生」が複数になっているのは、サドが生きた時代における生と死後の受容における生(この二つの生が第I巻)、そして、草稿を書くサドの生(これが第II巻)という意味だ。
第I巻第一部が秀逸である。ドゥロンはこれまでサドを取り囲んできた毀誉褒貶の言説を退け、「サドがわたしたちに提供しうる唯一の確かなもの、すなわち彼のエクリチュールの現実に立ち戻る」という方針に従い、サドとその時代に密接に関わる図版を提示しながら、サド家の由来(U ne lignée)に始まり、晩年も読書と執筆を遂行しつつ、若い娘との性行為を書き付け、「最後の瞬間まで自分自身に忠実であった」サドの死(Ultime combat)までの年月を27章に分けて丹念にたどる。注目すべきはドゥロンの言うサドの「自分自身」が文学と肉体の両方であることだ。
青年期の放蕩を語るドゥロンはオンフレ同様、サドを「軽犯罪者(délinquant)」と呼びながらもその「犯罪」を断罪しない。「犯罪」がひたすら書くことに収斂していくからだ。ドゥロンは、サドが自分の悪名高い「伝説」を悪用し、被害者を怖がらせて面白がっていただろうと想像しながら、「サドが小説の中に生きていた」と書く。
獄中で執筆に耽るサドについて、ドゥロンは、「牢獄は彼に独特のステイタスを与えた、すなわち、道を踏み外し、懲罰を受ける、一族の息子という身分であり、彼はいくつもの顔と仮面でそれに応えた」と言う。彼の言語生成を追いながらドゥロンは獄中のサドと当時の文学との関わりに注目する。『ソドム』の清書形態が巻物なのは隠匿のためであるとした上で、ドゥロンはこれをディドロの『運命論者ジャックとその主人』における普遍的決定論と自然の不可避性のイメージとしての「天上の大巻物(le Grand Rouleau)」と重ね、

恐怖政治下のピック地区での活躍については新しい情報は提供されていないが、アッシニア紙幣問題の判事になった際にサドが書いた手紙の「このわたしが判事だぞ」という有名な文面を引用しながら、ドゥロンも「永遠の被告が判事になること、これこそが
個人的には強かな健闘を見せるサドであるが、社会的には人生の節目ごとに帯剣貴族没落の刻印が押されている。1763年のジャンヌ・テスタル事件は2週間の拘禁で落着したのに対し、1768年のアルクイユ事件が大スキャンダルとなったことについて、「貴族の放蕩は事実であると同時に、世論のファンタスムの産物であったが、世論は次第に特権という原理を認めなくなっていた」とドゥロンは説明する。あるいはまた、1772年のマルセイユ事件で二度のイタリア逃亡旅行から帰国した後の1777年、モンペリエで数人の少女を雇い入れ、その一人にジュスチーヌという名前の少女がいたこと、主人の操行の正しさを保証するという修道士によって少女たちが集められてきたこと等を挙げて、ドゥロンは「この現実はすでにフィクションのようだ」と喜ぶが、それだけでは終わらない。サドの悪名を知っていたジュスチーヌの父親が娘を連れ戻しにやってくる。サドが城主の権限で追い返すと、職人であった父親は裁判所に訴え、サドは南仏を去ることを余儀なくされる。ドゥロンはこの事件に「ブルジョワの道徳と貴族の特権の対立」を見る。いずれ革命が起こるのは必至であった。革命後、無一文となったサドはついにラ・コストの城まで売却する羽目になる。城を購入したロヴェールは侯爵の爵位を金で買い、国民議会の代議士に成上ったならず者だ。ここにドゥロンは、「ブルジョワが貴族の城を奪い取る」という時代の縮図を見るが、ロヴェールがサドに支払ったのは価値が下落する一方のアッシニア紙幣であった。
困窮の中でサドは『新ジュスチーヌ』を1799年、『ジュリエットの物語』を1801年に出版する。しかし、革命で封鎖されていたノートルダム寺院再開のために教皇庁との和解を予定していた権力の注目するところとなり、同年5月、警察がマッセ書店を捜索した際に、居合わせたサドも草稿と註を書き込んだ初版本を携えたまま逮捕され、サント・ペラジー獄に送られる。彼は獄中で若い囚人男性を誘惑しようとしたためにビセートルに移送され、やがてシャラントンの精神病院に送られる。自宅からは『フロルベルの対談録(Entretiens de Florbelle)』の草稿が押収され、警察によって廃棄されてしまう。シャラントンで、サドが患者たちを登場させて演劇活動を行い、ナポレオンの妨害に遭いながらも歴史物語を執筆し、「最後の瞬間まで自分自身に忠実であった」のは最初に述べたとおりだ。
続く第二部のサドの受容の部分においては、第一部で排除されたサドをめぐる言説が網羅的に16グループに分類される。最終章でサドを題材にした現代小説を紹介した後、最後の段落でやはり、サドその人に戻らずにはいられない。2004年初公開の『ソドム』の草稿(幅11.5cm、長さ12m)を語るドゥロンの筆致は急に生気を取り戻す。「長いガラスケースの中に侯爵の注意深い筆使いがある。筆を運ぶ彼の手の動きが突然見えだし、彼の肉体と思考が現前する」。
第II巻は、サドが残したノート1と4の草稿写真とその書き写しである。すでにリーヴル・プレッシュー版等で部分的に発表されていたものであるが、これを初めて連続したテクストとして提示することで、エクリチュールの過程を可能な限り忠実な画像として見せるものである、とドゥロンは自負する。
後半のノート4では、ダランベールとヴォルテールの文章の抜粋と、その上か下にサドの考察が書かれ、サドと哲学者の対話が読みとれる。
前半のノート1は、短編と最初のジュスチーヌ『美徳の不運』の企画と草稿に加え、形式の混在が草稿になる以前の作家の営為をも見せてくれるが、文学的記述の頁の間に突然、監獄の役人への手紙の下書きや薬酒等に関する日常的な覚書が挿入される。この提示が世界初であることをドゥロンは誇るが、ここにはサドの「肉体と思考の現前」を感じられないのが残念だ。
草稿という観点からは、1995年に彼の弟子アブラモヴィシが出版した『美徳の不運』(Les Infortunes de la vertu, Zlma)を措いてないだろう。そこでは、サドが2週間で書き上げたノート9から12までの部分について、すべて草稿写真とその書き写しが並べられている。日常生活の覚書などなくとも、ジュスチーヌを直撃する落雷の場面に、サドが後から「1788年7月13日のあの恐ろしい雷雨」と書き加えた文字を見るだけで、わたしたちの前に「彼の肉体と思考が現前する」。