前古典主義演劇―悲喜劇、田園劇の魅力
『フランス十七世紀演劇集 悲喜劇・田園劇』中央大学人文科学研究所 翻訳叢書12 「十七世紀演劇を読む」チーム(伊東洋、皆吉郷平、橋本能、冨田高嗣、鈴木美穂、戸口民也、野池恵子)訳、中央大学出版部、2015年
榎本恵子(大妻女子大学文学部専任講師)
中央大学人文科学研究所「十七世紀演劇を読む」チームによる三部作『フランス十七世紀演劇集』喜劇編(2010年)、悲劇編(2011年)に続く三冊目にあたり、田園劇と悲喜劇4作の翻訳を収録している。
一般にフランス17世紀演劇といえば、三大劇作家を思い浮かべる。コルネイユとラシーヌの悲劇とモリエールの喜劇である。しかし、コルネイユが喜劇から悲劇へとその方向性を変え、モリエール、ラシーヌの作品が現れるまで好まれて上演されていた演劇ジャンルに田園劇と悲喜劇があった。その全盛期は短く、悲喜劇は17世紀前半に興隆し、全盛期を迎え、1666年頃衰退していった。田園劇に至っては1631年を境に早々に衰退してしまった。定義することが難しく、当時の劇作家たちですら、その定義づけに幅がある。ところが一見馴染みのないジャンルである悲喜劇は、実は、我々のイメージする演劇に近いものを持つのだが、その悲喜劇を理解するためには、演劇が、悲劇、喜劇の二つに峻別されていて、この二つが相容れることがなかったということを把握しなければならない。
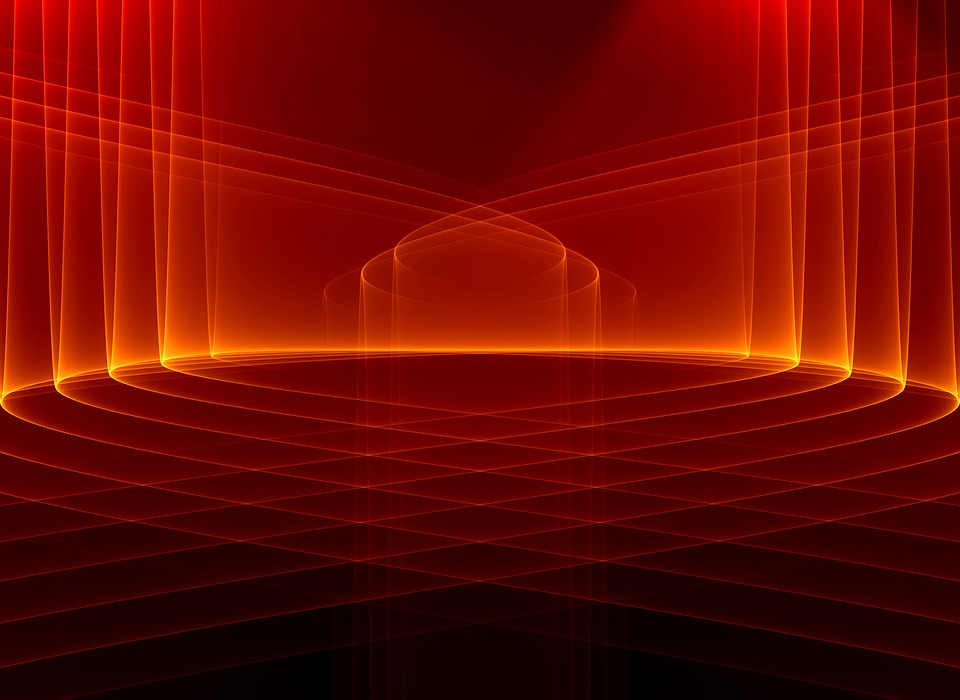
我々は高邁な英雄的理想を描いたコルネイユの悲劇や抗いがたい情念に飲み込まれ自ら不幸の中に堕ちていくラシーヌの悲劇の主人公たちに感動し、涙しながら、何か枠に嵌った形式美を感じることがあるだろう。またモリエールの主人公たちに自らの日常を重ね、笑い、時に憤りを感じながら、なぜか限定された環境設定をもどかしく感じることはないだろうか。なぜこの時代の悲劇の登場人物が神々や王侯なのか、そして恋の障害に悩み葛藤し、幸せをつかむ話がないのかと疑問に持つことがあるだろう。それは、悲劇と喜劇が厳格な規則に則ったものであるからだ。悲劇は神々や王侯など高貴な人物を登場させ、全編を悲劇的な調子で進行させ、最後は不幸な結末にしなければならない。そして喜劇は市井の人々を登場させ、日常の一場面を切り取ったものであり、最後は幸福な結末へと導かなければならなかった。
当然この時代の人々も、同じ思いがあったと考えられる。ルイ14世を頂点とする絶対君主制の確立した17世紀後半に全盛期を迎える古典主義演劇を前に、宗教改革の後、宗教的、理論的、政治的、科学的秩序といった既成概念が崩壊した中で、観客が求めるものは、型に嵌った形式美もさることながら、迸る激情や荒々しさであったことは容易に頷ける。方や人々はより暴力的なものを求め、方や変装や夢想、幻影の中に理想郷(アルカディア)を求めた。その表れが、田園劇であり、悲喜劇である。悲喜劇とは「大きな不幸に見舞われた著名な人物のあいだの崇高な恋愛事件を観客の前に示すもので、最後は幸せな結末に終わるもの(シャピュゾー、本著19頁)」であり、そこには高貴な人物あるいは市井の若者の前に立ちはだかる予想外の出来事を乗り越えていくという波乱万丈の冒険、恋の障害を乗り越えていく話が描かれる。田園劇は音楽やバレエと融合することによって音楽劇への道を開くことになるのだが、「羊飼いの若い男女(その心理の動きなどは宮廷人そのものだが)が恋に落ち、様々な妨害、障害を乗り越えて結ばれる(本著44頁)」までを描いたもので、悲劇的、喜劇的な内容が包括されたものもある。
本著では、これら田園劇、悲喜劇の性質を歴史的背景において俯瞰し、その変遷において文学史的位置づけを確認させるだけでなく作品そのものの面白さを堪能できるように構成されている。前半で田園劇、悲喜劇の概観が端的にまとめられ、混沌としたこれらのジャンルが整理される。そしてまず、田園劇全盛期、悲喜劇の興隆期にあたる作品として、悲喜劇の構造の中に田園劇風の筋が展開する入れ子構造のメレの田園悲喜劇『シルヴィ』(1626年初演)を紹介する。次に、バロック的要素の一つである変装、入れ替わり、取り違えをふんだんに用いたスキュデリーの『変装の王子』(1635年初演)、そしてロトルーの『ヴァンセスラス』(1647年初演)で緊張感を保持しつつ「ハッピーエンドの悲劇」に三単一の規則が遵守された古典主義の前章としての悲喜劇を紹介し、キノーの悲喜劇『アマラゾント』(1657年初演)を以って、劇作家の才能と同様に時代が喜劇から悲喜劇、悲劇を経て音楽悲劇へとシフトしていく時代の流れを紹介している。
文学を理解することは作品を読むことにあり、すべての理解は原典を紐解くことにある。文学史的知識だけでなく、実際の作品に触れることで、劇作家の才能はもちろんのこと、当時の観客が求めていたもの、感じていた同じ感動を味わうことができる。17世紀の文学には脈々と続くフランス文学の原点の一つが在る。だからこそ研究書に限らず、作品の翻訳は、知識を体感していくためのデータベースとしてとても大切な試みであると思う。